はじめに
2025年現在、ホテル業界はかつてないほどの変化と進化の渦中にあります。テクノロジーの導入、サステナビリティへの意識向上、そして何よりもゲストの多様化するニーズへの対応が求められています。そのような中で、ゲストがホテル滞在中に「うっかり」やってしまう失敗や、ホテル側が意図せずゲストに不便を感じさせてしまうケースは、依然としてホスピタリティの質を問う重要な側面として存在します。
今回は、ホテルビースイーツ(大阪市中央区)が公式TikTokアカウントで紹介した「ホテル宿泊時にやりがちな“5つの失敗”」に関するニュース記事を深掘りし、これらの「失敗」がホテル運営にもたらす課題と、それを乗り越えてより豊かなゲスト体験を創造するためのホスピタリティのあり方について考察します。無理にテクノロジーに絡めるのではなく、このニュースが示すゲストとホテルの間の「見えないギャップ」に焦点を当て、運用現場の泥臭い課題や、現場スタッフ・エンドユーザーのリアルな声も拾いながら、本質的なホスピタリティの深化について探ります。
引用元記事:「ホテル」宿泊時は気を付けて! やりがちな“5つの失敗”とは?(オトナンサー) – Yahoo!ニュース
この記事では、ホテルビースイーツが公式TikTokで発信した、ゲストがホテル滞在中に陥りがちな5つの失敗について紹介しています。具体的には、チェックイン時刻の遅れ、朝食時間の見落とし、備品の持ち帰り、騒音問題、忘れ物といった項目が挙げられており、これらは多くのホテルで日常的に発生しうる事象です。
ゲストの「5つの失敗」が示すもの:見えない期待値のギャップ
ニュース記事で挙げられた「5つの失敗」は、単なるゲストの不注意と片付けられない、ホテルとゲストの間に存在する「見えない期待値のギャップ」を浮き彫りにします。それぞれの失敗が、どのようなゲスト心理から生じ、ホテル運営にどのような影響を与えているのかを深掘りしてみましょう。
1. チェックイン時刻の遅れ
「チェックイン時刻を過ぎてしまい、ホテルに連絡し忘れる」という失敗は、ゲストの「まだ大丈夫だろう」という安易な思い込みと、ホテル側の情報伝達の不十分さが交錯する点にあります。現代の旅行者は、移動中に観光や食事を楽しむことが多く、予定通りにホテルに到着できないことは珍しくありません。しかし、その際にホテルへの連絡を忘れてしまうと、ホテル側はゲストの安否確認や、清掃・準備スケジュールの調整に影響が出ます。
現場のフロントスタッフからは、「お客様からの連絡がないまま深夜になり、心配して電話をかけることも少なくありません。特にインバウンドのお客様の場合、言葉の壁もあり、連絡が取れないと焦ります」といった声が聞かれます。また、「チェックインが遅れると、その分、客室の準備が遅れ、次のゲストへの影響も懸念されます」とハウスキーピングとの連携の難しさも指摘されています。
ゲストの立場からすれば、「予約時に遅れる可能性を伝えているから大丈夫だろう」「少しの遅れなら問題ないだろう」という心理が働くこともあります。しかし、ホテル側にとっては、遅延の連絡がないことは、客室の準備や人員配置に影響を及ぼすだけでなく、最悪の場合、ノーショー(無連絡不泊)と判断せざるを得ない状況にも繋がります。
2. 朝食時間の見落とし
「朝食の時間を過ぎてしまい、食べられない」という失敗は、情報過多による見落としと、ホテル側の情報提供の「質」が問われるケースです。チェックイン時に口頭で説明されても、多くの情報が一度に入ってくるため、全てを記憶するのは困難です。また、客室に置かれた案内も、多忙な旅行者には見落とされがちです。
「朝食会場で『もう終わりですか?』と尋ねられることは日常茶飯事です。特に団体客や小さなお子様連れのお客様は、時間の管理が難しいようです」とレストランスタッフは語ります。朝食終了間際に駆け込むゲストへの対応は、時には他のゲストの迷惑になったり、片付け作業に支障をきたしたりすることもあります。
エンドユーザーのリアルな声としては、「チェックインの時に説明されたけど、移動で疲れていて頭に入っていなかった」「部屋に案内があったけど、細かい字で読む気がしなかった」といった意見がよく聞かれます。ホテル側は、朝食の情報を伝えるだけでなく、それがゲストに確実に届き、理解されるための工夫が求められます。
3. 備品の持ち帰り
「アメニティー以外に、ドライヤーやタオル、リモコンなどを持ち帰ってしまう」という事例は、「これは持ち帰っていいものなのか?」というゲストの判断基準の曖昧さと、ホテル側の明確な線引きの欠如が原因となることがあります。
「ブランドロゴ入りのタオルや、デザイン性の高いカップなどがよくなくなります。備品リストと照合するハウスキーピングの作業は、手間がかかる上に、紛失が発覚すると補充コストも発生します」とハウスキーピングの責任者は頭を抱えます。特に高価な備品や、ホテルのコンセプトを象徴するようなアイテムの紛失は、ホテルにとって大きな痛手となります。一方で、ゲスト側には悪意がない場合も多く、「記念に」「うっかり」といった心理が背景にあることも少なくありません。
この問題は、ホテルのおもてなしと持続可能な運営の両立を考える上で重要な課題です。過去記事「客室備品「無断持ち帰り」の現実:ホテルのおもてなしと持続可能な運営の両立」でも言及されているように、ゲストの善意と現場の負担のバランスは常に問われています。
4. 騒音問題
「夜中に部屋で騒いでしまい、他の宿泊客に迷惑をかける」という問題は、ゲストの「非日常」における解放感と、ホテルにおける「共存」のルールの衝突です。特にグループ客や若年層のゲストに多く見られ、旅行先での高揚感から、普段よりも声が大きくなったり、深夜まで談笑が続いたりすることがあります。
「隣の部屋から騒音がすると、ゲストからのクレームがフロントに入ります。夜勤スタッフが注意に伺うこともありますが、注意してもすぐに収まらないこともあり、対応に苦慮します」と夜勤のフロントスタッフは語ります。騒音問題は、他のゲストの滞在体験を著しく損なうだけでなく、ホテルのレピュテーションにも悪影響を及ぼしかねません。しかし、ゲストに直接注意することは、トラブルに発展するリスクも伴うため、現場スタッフにとっては非常にデリケートな対応が求められます。
「海外のホテルは寝るところではない?!絶対に眠らせない!ボローニャの恐怖」というニュース記事のように、海外では文化的な違いから騒音に対する許容度が異なる場合もありますが、日本では特に、静かな環境を求めるゲストが多い傾向にあります。
5. 忘れ物
「帰宅してから忘れ物に気づき、ホテルに連絡する」という失敗は、ゲストのチェックアウト時の慌ただしさと、ホテル側の忘れ物管理の煩雑さが浮き彫りになります。充電器、アクセサリー、衣類、化粧品など、忘れ物の種類は多岐にわたり、その対応は現場スタッフにとって大きな負担となります。
「忘れ物の問い合わせは毎日何件もあります。特に多いのは充電器ですね。お客様の滞在中に気づけばお渡しできますが、チェックアウト後だと、ハウスキーピングが発見し、フロントに届け、お客様に連絡して、郵送手続きをする、という一連の作業が発生します」とフロントスタッフは説明します。忘れ物の管理は、紛失のリスク、個人情報保護、郵送費用、そして何よりもスタッフの貴重な時間を奪うため、ホテル運営における見えないコストとして存在します。
忘れ物に関する課題は、過去記事「忘れ物が語るホテルの真価:現場の苦悩から生まれる持続可能な運営戦略」でも詳しく論じられています。ゲストの「うっかり」をホテルの「おもてなし」でカバーする努力は尊いものの、その裏側には現場の泥臭い努力とコストが隠されています。
現場スタッフの視点:見えない「失敗」への泥臭い対応
これらの「5つの失敗」は、表面上はゲストの行動に起因するように見えますが、その裏側ではホテルスタッフが日々、多大な労力と精神力を使って対応しています。彼らの泥臭い努力とリアルな声に耳を傾けることは、ホスピタリティの真髄を理解する上で不可欠です。
フロントスタッフの葛藤
チェックインの遅延連絡がないゲストへの対応は、安否確認から始まり、客室の再調整、時にはノーショー処理の判断まで、精神的な負担が大きい業務です。また、騒音クレームの対応では、ゲスト間のトラブルを避けつつ、双方に配慮した解決策を見つけるための高度なコミュニケーション能力が求められます。「お客様同士のトラブルは、ホテル全体の雰囲気を悪くします。注意する側もされる側も気持ちよくない。もっと事前に防ぐ手立てはないかと常に考えています」とあるベテランフロントスタッフは語ります。
「ホテルのトラブル対応最前線2025:人間力とテクノロジーで築くホスピタリティ」でも述べたように、トラブル対応はホテルの人間力が試される瞬間です。
ハウスキーピングの隠れた労力
備品の紛失や忘れ物の発見・管理は、ハウスキーピングの日常業務に大きな負荷をかけています。清掃時間を圧迫するだけでなく、一つ一つの忘れ物に対して、いつ、どこで、誰が、何を忘れたのかを正確に記録し、適切に保管する作業は、非常に細かく神経を使うものです。特に、貴重品や個人情報が含まれる可能性のある忘れ物には、細心の注意が必要です。
「お客様がチェックアウトされた後、部屋に入ると、思わぬものが残されていることがあります。充電器や衣類はまだしも、パスポートや財布などが見つかると、すぐにフロントに報告して、お客様に連絡が取れるよう手配します。でも、その一つ一つの作業が、次の部屋の清掃開始を遅らせることにも繋がります」とハウスキーピングのスタッフは打ち明けます。
レストランスタッフの柔軟性
朝食時間の見落としによる「食べられない」ゲストへの対応は、ホテルのポリシーとゲストへの配慮の間でバランスを取る必要があります。終了間際に来たゲストに、どこまで柔軟に対応できるかは、スタッフの判断に委ねられる部分も大きく、それがサービス品質のばらつきに繋がる可能性もあります。「残っている料理を少しでも提供しようと努力しますが、衛生面やコストを考えると限界もあります。もう少し早めに案内ができていれば、といつも思います」とレストランのマネージャーは語ります。
エンドユーザーのリアルな声:期待と現実のギャップ
ゲストの「失敗」の背景には、ホテルに対する期待と、実際の情報提供やサービスとの間に存在するギャップがあります。SNSや口コミサイトでは、以下のようなリアルな声が散見されます。
- 「チェックイン時に説明されたけど、情報量が多すぎて覚えきれなかった。紙の案内も小さくて見づらい。」
- 「朝食の時間が終わっていたのは自分のせいだけど、もう少し分かりやすく教えてくれるか、融通を利かせてほしかった。」
- 「リモコンを持ち帰ってしまったのは完全にうっかり。でも、部屋で使うものと持ち帰れるものの区別がもっと明確だと助かる。」
- 「隣の部屋がうるさくて眠れなかった。もっと早くホテルに言えばよかったけど、言いにくかった。」
- 「充電器を忘れたことに気づいた時、本当にショックだった。ホテルから連絡が来て助かったけど、自分で気づけたはずなのにと後悔。」
これらの声からは、ゲストがホテルに対して「もっと分かりやすい情報提供」と「困った時に寄り添ってくれる柔軟な対応」を求めていることが伺えます。特に「フロントに聞くのは恥ずかしい」というゲスト心理は、「「フロントに聞くのは恥ずかしい」:ゲストの隠れた心理に応えるホテルのおもてなし戦略」でも指摘されているように、ホテル側が見過ごしてはならない重要なポイントです。
「失敗」を「成功体験」に変えるホスピタリティの再構築
ゲストの「失敗」を単なるクレームやコストと捉えるのではなく、ホスピタリティを深化させる機会として捉え直すことが、2025年以降のホテル業界には求められます。そのためには、以下の3つの柱でホスピタリティを再構築することが重要です。
1. 情報提供の最適化とパーソナライゼーション
情報過多の時代において、ゲストに「必要な情報」を「適切なタイミング」で「分かりやすい形」で提供することが不可欠です。
- チェックイン前: 予約確認メールや専用アプリを通じて、チェックイン時刻の厳守、朝食時間、アメニティに関する注意喚起などを事前に複数回通知する。特に、遅れる場合の連絡方法を明確に伝える。
- チェックイン時: 口頭での説明は簡潔にし、重要な情報はQRコードやデジタルサイネージ、客室内のタブレットなどでいつでも確認できるようにする。視覚的に分かりやすいピクトグラムや多言語対応も必須です。
- 滞在中: 客室内のタブレットやスマートスピーカーを通じて、朝食時間のカウントダウン表示や、騒音に関する注意喚起(ただし、ゲストのプライバシーに配慮し、押し付けがましくない形)を行う。
これは「2025年ホテル戦略:データと人間力で拓くパーソナライゼーション」にも通じる考え方です。ゲストの行動履歴や好みに基づいて、必要な情報をパーソナライズして提供することで、見落としや誤解を防ぎ、よりスムーズな滞在をサポートできます。
2. スタッフの教育と権限委譲:人間力の最大化
どんなに情報提供を最適化しても、ゲストの「失敗」は発生します。その際に問われるのが、現場スタッフの対応力、すなわち「人間力」です。
- 共感と傾聴: ゲストが「失敗」を報告してきた際に、まずは非難せずに共感し、話をじっくり聞く姿勢が重要です。ゲストが「困っている」という感情に寄り添うことで、信頼関係が築かれます。
- 問題解決能力の向上: マニュアル通りの対応だけでなく、状況に応じて柔軟な解決策を提案できる能力を養うためのトレーニングが必要です。例えば、朝食時間を過ぎてしまったゲストに対して、代替の軽食提供や近隣のカフェの紹介など、可能な範囲での選択肢を提示できる権限をスタッフに与えることが有効です。
- 部門間の連携強化: フロント、ハウスキーピング、レストランなど、各部門が密に連携し、情報共有を徹底することで、忘れ物や騒音クレームなどへの迅速かつ効果的な対応が可能になります。
「2025年ホテル「人財不足」の深層:人間力で築く持続可能なホスピタリティ」で強調されているように、人材不足が深刻化する中で、一人ひとりのスタッフが持つ人間力を最大限に引き出し、ゲストに最高のホスピタリティを提供できる環境を整えることが、ホテルの持続的成長には不可欠です。
3. デジタルツールとアナログサービスの融合
テクノロジーは、ゲストの「失敗」を未然に防ぎ、発生後の対応を効率化するための強力なツールとなり得ます。しかし、それはあくまで人間によるホスピタリティを補完するものでなければなりません。
- AIチャットボット・FAQシステムの導入: ゲストが「フロントに聞くのは恥ずかしい」と感じるような些細な疑問や、よくある質問に対して、24時間いつでも回答できるシステムを導入します。これにより、ゲストは気軽に情報を得られ、フロントスタッフはより複雑な問題解決に集中できます。
- 忘れ物管理システムのデジタル化: 忘れ物の情報を写真付きでデータベース化し、検索性を高めることで、問い合わせへの対応時間を短縮し、紛失のリスクを低減します。お客様自身が忘れ物を登録・検索できるようなシステムも有効です。
- 客室備品の明確化: 持ち帰り可能なアメニティと、持ち帰り不可の備品を、視覚的に分かりやすい表示(例:QRコードで詳細情報を表示、持ち帰り可能なものには専用の袋を用意するなど)で明確に区別します。
デジタルツールは、情報伝達の効率化や定型業務の自動化に貢献しますが、最終的には、困っているゲストに寄り添い、心温まるサービスを提供する「人間」の役割が不可欠です。テクノロジーと人間力が融合することで、ゲストは「失敗」を恐れることなく、安心して滞在を楽しめるようになります。
未来への展望:ゲストとホテルが共に創る価値
ゲストの「5つの失敗」は、ホテル業界にとって、単なる運用上の課題に留まりません。それは、ゲストがホテルに何を求め、どのような体験を期待しているのかを深く理解するための貴重なフィードバックです。ホテル側がこれらの「失敗」を真摯に受け止め、改善へと繋げることで、ゲストとの間に強固な信頼関係を築き、リピーターへと繋がる真のロイヤリティを育むことができます。
2025年、ホテルは単なる宿泊施設ではなく、ゲストの人生に寄り添い、記憶に残る体験を提供する「体験創造業」へと進化しています。ゲストの「失敗」を「成功体験」に変えるホスピタリティの再構築は、その進化の重要な一歩となるでしょう。ゲストが「うっかり」やってしまっても、ホテルが「さすが」の対応で乗り越える。そのような関係性が、持続可能なホスピタリティの未来を築く礎となるはずです。
ホテルは、ゲストを「教育」するのではなく、「理解」し「寄り添う」姿勢を常に持ち続けることが求められます。そして、ゲストもまた、ホテルのルールやスタッフの努力を理解し、お互いに尊重し合うことで、より豊かな滞在体験が生まれることを認識する。このような「共創」の精神こそが、これからのホテル業界が目指すべき姿ではないでしょうか。
このニュース記事が示す「5つの失敗」は、ホテル業界がゲストとの対話を通じて、サービスの本質を問い直し、より人間中心のホスピタリティを追求するための貴重な示唆を与えてくれています。

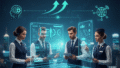
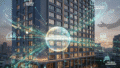
コメント