はじめに
2025年、ホテル業界はコロナ禍からの劇的な回復を遂げ、国内外からの観光客で活況を呈しています。特に訪日外国人旅行者数(インバウンド)は回復基調にあり、多くのホテルが稼働率の向上を享受していることでしょう。しかし、この喜ばしい状況の裏側で、ホテル運営の現場では依然として深刻な課題が横たわっています。それは、単なる「人手不足」から「人財不足」へと質的な変化を遂げた、根深い問題です。
先日発表された総務省の労働力調査(2025年7月)によると、宿泊・飲食業の就業者数は前年同月比で3万人増加し、409万人に達したと報じられました。コロナ禍前の2019年同月比でも3万人増というこの数字は、一見すると業界の人手不足が解消されつつあるかのように見えます。しかし、現場で働くホテリエやマネージャーからは、「数字は増えたが、業務負担は一向に減らない」「むしろ教育コストが増え、疲弊している」といった声が聞かれます。このギャップは一体どこから生まれるのでしょうか。
本稿では、この「見かけ上の就業者数増加」の裏に潜むホテル運営の課題を深掘りし、テクノロジーに頼らず、人間力と現場の視点から、持続可能なホスピタリティを追求するために今、ホテルが考慮すべきことについて考察していきます。
宿泊・飲食業の就業者数増加が示す、現場の「質」の課題
まずは、今回取り上げるニュース記事を確認しましょう。
-
タイトル: 宿泊・飲食業の就業者数 前年比3万人増加 総務省調査 7月 – 観光経済新聞
URL: https://kankokeizai.com/2509170900kks
この記事は、総務省が発表した2025年7月の労働力調査において、宿泊業および飲食サービス業の就業者数が前年同月比で3万人増加し、合計409万人になったことを報じています。これはコロナ禍前の2019年同月と比較しても3万人増であり、業界全体での雇用回復の兆しと捉えることができます。
この数字は、コロナ禍で大きく落ち込んだ観光需要が回復し、それに伴い雇用が創出されていることを示唆しています。しかし、現場の肌感覚とは異なる部分があるのも事実です。多くのホテルでは、依然として「人が足りない」という悲鳴が上がっており、特に経験豊富なベテランスタッフの不足は深刻です。増えた就業者の中には、異業種からの転職者や、短期間のアルバイト・パートスタッフが多く含まれている可能性があり、彼らがホテル業務に慣れるまでには時間と教育が必要です。この「数」と「質」のギャップこそが、ホテル運営において今、最も深く考慮すべき点なのです。
現場の「泥臭い」現実:人手不足から「人財不足」へ
「人が増えたのに、なぜこんなに忙しいんだ?」
これは、あるシティホテルのフロントマネージャーが漏らした言葉です。就業者数が増加したという統計データとは裏腹に、多くのホテル現場では、スタッフ一人当たりの業務負担が軽減されたという実感は薄いのが現状です。その背景には、以下のような「泥臭い」現実があります。
1. 経験とスキルのミスマッチ
コロナ禍で多くのベテランホテリエが業界を去り、その穴を埋める形で新たな人材が流入しています。しかし、ホテル業務は多岐にわたり、単に「人がいる」だけでは質の高いサービスは提供できません。特に、ゲストの多様なニーズを汲み取り、臨機応変に対応する「人間力」は、一朝一夕で身につくものではありません。新人スタッフは基本的な業務マニュアルをこなすことで精一杯になりがちで、クレーム対応や特別な要望への対応といった、経験と判断力が求められる場面では、既存のベテランスタッフに負担が集中してしまいます。
2. 新人教育の負担増大
新しいスタッフが増えることは喜ばしいことですが、同時に教育コストも増大します。既存スタッフは自身の業務をこなしながら、新人へのOJT(On-the-Job Training)を行わなければなりません。これは時間的にも精神的にも大きな負担となり、結果として既存スタッフの疲弊を招きます。「教える側」のスキルも求められるため、単に業務をこなすだけでなく、指導者としての役割も担うことになります。この教育の質が、新人の定着率や成長速度に直結するため、手を抜くわけにもいきません。
3. サービス品質の維持と向上への影響
経験不足のスタッフが増えることで、サービスの均一性が保てなくなるリスクも高まります。例えば、チェックイン時の手続きに時間がかかったり、レストランでのオーダーミスが増えたり、客室清掃の質にばらつきが出たりといった問題が発生しやすくなります。ゲストは「人が増えたからサービスが良くなる」と期待しているため、このギャップは直接的に顧客満足度の低下につながりかねません。現場スタッフは、限られたリソースの中で、いかに高いサービス品質を維持するかというプレッシャーに常に晒されています。
4. 離職率の高さと悪循環
このような状況は、新人スタッフの早期離職にもつながります。十分な教育を受けられず、業務の難しさやプレッシャーに直面することで、「自分には向いていない」と感じてしまうケースも少なくありません。また、既存スタッフも、負担の増加やキャリアパスの不透明さから、モチベーションを維持できずに離職を選ぶことがあります。これは、再び「人財不足」の悪循環を生み出し、ホテルの持続的な運営を困難にします。
ホテル業界における人材の確保と定着は、常に重要なテーマです。過去の記事でも、総務人事部が果たすべき役割や、人材流動性への対応について考察しています。例えば、「ホテルGMの人間力と戦略的リーダーシップ:総務人事部が支える人材確保と成長戦略」では、GMと総務人事部が連携し、人材を「コスト」ではなく「戦略的資産」として捉える重要性を説いています。また、「ホテル人材流動性の再定義:循環型キャリアとアルムナイで築く持続可能戦略」では、業界特有の流動性をポジティブに捉え、アルムナイ(卒業生)との関係構築を通じて、新たな人材確保の道を模索する視点も提示しています。
ホテル運営における「人間力」の再定義
テクノロジーが進化し、自動化が進む現代においても、ホテル業界の核となるのは、やはり「人間力」です。特に、人手が増えたにもかかわらず現場が疲弊している現状は、この人間力の重要性を改めて浮き彫りにしています。
1. マニュアルを超えたホスピタリティ
ホテルにおけるサービスは、単に決められた手順をこなすだけではありません。ゲストの表情や言葉のニュアンスから潜在的なニーズを察知し、期待を超えるサービスを提供することこそが、真のホスピタリティです。例えば、雨の日に傘を貸すだけでなく、「お帰りになる頃には止んでいると良いですね」と一言添える。体調が悪そうなゲストに、さりげなく温かいお茶を差し出す。こうした細やかな気遣いは、マニュアルには書かれていない「人間力」があってこそ生まれるものです。経験の浅いスタッフがこれらを実践するには、日々のOJTと、先輩スタッフによる手厚いサポートが不可欠となります。
2. ゲストの「不」を先読みする能力
ゲストが言葉にする前に、その「不便」や「不満」を察知し、解決に導く能力は、熟練のホテリエにしかできない芸当です。チェックイン時に少し戸惑っている様子のゲストがいれば、すぐに声をかけ、手助けをする。レストランでメニュー選びに悩んでいるゲストには、好みを聞きながらおすすめを提案する。これらの「先読み」は、ゲストに「自分のことをよく見てくれている」という安心感と信頼感を与えます。これは、「顧客の「不」を先読みする運営戦略:人間力で高めるホテルのブランド価値」でも述べた通り、ホテルのブランド価値を高める上で極めて重要な要素です。
3. 現場で培われる「対応力」
予期せぬトラブルや緊急事態が発生した際、冷静かつ的確に対応できる能力もまた、人間力の賜物です。客室設備の故障、他のゲストとのトラブル、急病人の発生など、ホテルでは様々な事態が起こり得ます。マニュアル通りの対応では解決できない状況において、現場スタッフが自ら判断し、最善策を講じる「対応力」が問われます。これは、経験豊富なスタッフが持つ「引き出しの多さ」であり、新人スタッフがベテランから学ぶべき最も重要なスキルの一つです。
4. 従業員間の連携とチームワーク
ホテル運営は、フロント、ハウスキーピング、レストラン、ベル、コンシェルジュなど、様々な部署のスタッフが連携して初めて成り立ちます。それぞれの部署がプロフェッショナルとして機能し、密にコミュニケーションを取りながら、ゲストにシームレスな体験を提供することが求められます。この連携を円滑にするのも、スタッフ間の「人間力」です。互いを尊重し、助け合う文化が根付いているホテルでは、たとえ人手が増えたとしても、その「質」がサービスの向上に直結します。
過去の記事では、ゲストの期待値と現場の現実のギャップを埋める対話の重要性も指摘されています。「善意が現場の負担となるホテル業界:期待値のギャップを埋める対話戦略」では、ゲストの「善意」が必ずしも現場の負担軽減につながらないケースを取り上げ、双方の理解を深めることの重要性を強調しています。また、「2025年ホテル業界の変革期:価格以上の価値を創る人間中心ホスピタリティ」では、価格競争に陥らず、人間中心のホスピタリティで真の価値を創造することの意義を論じています。これらの視点は、まさに「人財」の質を高め、その人間力を最大限に引き出す運営のあり方を考える上で不可欠です。
持続可能な人材戦略の構築:現場視点からの提言
就業者数が増加しているにもかかわらず、現場が「人財不足」に陥っている現状を打破し、持続可能なホテル運営を実現するためには、より現場に寄り添った人材戦略の構築が不可欠です。以下に、具体的な提言を挙げます。
1. 採用段階でのミスマッチ防止と期待値調整
「人が欲しい」という一心で、どんな人材でも採用してしまうと、結果的に早期離職や既存スタッフへの負担増につながります。採用活動においては、単に人数を確保するだけでなく、ホテルの文化や業務内容を明確に伝え、候補者が自身の適性やキャリアパスを具体的にイメージできるよう支援することが重要です。
- 具体的な業務内容の明確化: 求人票や面接で、華やかなイメージだけでなく、清掃や重い荷物の運搬、夜勤など、ホテル業務の泥臭い側面も包み隠さず伝える。
- 適性検査の導入: ホスピタリティ精神やストレス耐性、チームワークを重視する姿勢など、ホテル業務に求められる資質を客観的に評価するツールを活用する。
- 現場体験の機会提供: 短期間のインターンシップやアルバイトを通じて、実際の業務を体験してもらうことで、入社後のギャップを最小限に抑える。
2. OJTの質の向上と既存スタッフへの負担軽減
新人教育は、既存スタッフの「善意」に頼るだけでは持続しません。OJTの体系化と、教育担当者への適切なサポートが必要です。
- 教育担当者の育成とインセンティブ: OJT担当者を明確に定め、指導スキル向上のための研修を行う。また、教育への貢献度を評価し、昇給や手当などのインセンティブを設ける。
- 新人向け研修プログラムの充実: 入社直後の座学研修に加え、ロールプレイングやシミュレーションを通じて、実践的なスキルを習得させる。
- メンター制度の導入: 新人一人ひとりに先輩スタッフをメンターとしてつけ、業務だけでなく精神面でのサポートも行う。定期的な面談の機会を設けることで、悩みを早期に発見し、解決に導く。
こうした取り組みは、「2025年ホテル人材育成の鍵:テクノロジーと人間力でエンゲージメントを高める」でも言及されているように、従業員のエンゲージメント向上に直結します。テクノロジー抜きで考えるならば、人間同士の密なコミュニケーションと、組織的なサポート体制が不可欠です。
3. キャリアパスの明確化とモチベーション維持
ホテリエが長く働き続けたいと思えるようなキャリアパスを提示し、成長を実感できる機会を提供することが重要です。
- 多部署での経験機会: フロント、レストラン、ハウスキーピングなど、複数の部署を経験できるジョブローテーション制度を導入し、幅広いスキルと視点を養う。
- スキルアップ支援: 語学研修、サービススキル研修、マネジメント研修など、従業員のキャリア目標に合わせた学習機会を提供する。
- 評価制度の透明化: 評価基準を明確にし、定期的なフィードバックを通じて、自身の成長と貢献が正当に評価されていると感じられるようにする。
4. 従業員のウェルビーイングへの配慮
労働環境の改善は、従業員の定着率向上に直結します。
- 労働時間の適正化: シフト管理の最適化や、有給休暇の取得促進により、過重労働を防ぎ、ワークライフバランスを重視する。
- 福利厚生の充実: 食事補助、交通費補助、従業員割引、健康診断の充実など、従業員が安心して働ける環境を整備する。
- コミュニケーションの促進: 上司と部下、部署間の垣根を越えたコミュニケーションを促進し、風通しの良い職場環境を作る。定期的な懇親会や社内イベントの開催も有効です。
従業員のウェルビーイングは、ゲストへのホスピタリティの質にも影響します。過去の記事でも、「2025年ホテルは充足感創造業へ:PERMAHモデルで実現する従業員とゲストのウェルビーイング」で、従業員の幸福度がゲスト体験に与える影響について深く考察しています。疲弊したスタッフからは、真の笑顔や心からのサービスは生まれません。従業員が充足感を感じながら働ける環境こそが、最高のホスピタリティを生み出す土壌となるのです。
5. 現場の声を取り入れた運営改善
最も重要なのは、現場で働くスタッフの声を経営層が真摯に聞き、運営改善に活かすことです。
- 定期的な意見交換会: 部署ごとのミーティングだけでなく、部署横断的な意見交換会を定期的に開催し、業務改善提案や課題意識を吸い上げる。
- 匿名での意見提出システム: 従業員が安心して意見を言えるよう、匿名で提案できる仕組みを導入する。
- 改善策の実行とフィードバック: 提案された意見に対しては、実行の可否にかかわらず、必ずフィードバックを行う。実行された場合は、その効果を共有し、スタッフのモチベーション向上につなげる。
ゲストの「あるある」からその心理を読み解くように、「ホテル「あるある」から読み解くゲスト心理:無意識のニーズに応える人間力ホスピタリティ」、現場スタッフの「あるある」にも、運営改善のヒントが隠されています。現場の泥臭い課題にこそ、ホテル運営の本質的な改善点があるのです。
まとめ:人財が織りなすホスピタリティの未来
2025年、ホテル業界は大きな転換期を迎えています。就業者数の増加という明るいニュースの裏側で、私たちは「人手」と「人財」の質的なギャップという、より深刻な課題に直面しています。この課題を乗り越え、持続可能な成長を実現するためには、単に頭数を揃えるだけでなく、一人ひとりのスタッフを「人財」として育成し、その人間力を最大限に引き出す運営が不可欠です。
テクノロジーが進化する現代においても、ホテルが提供する「感動」や「癒やし」は、最終的には人間の温かい心と、きめ細やかなサービスによってもたらされます。現場の泥臭い課題に目を向け、スタッフの声を真摯に聞き、彼らが安心して働き、成長できる環境を整えること。これこそが、ゲストに最高のホスピタリティを提供し、ホテルのブランド価値を高めるための唯一無二の道筋なのです。
2025年以降、ホテル業界が目指すべきは、単なる宿泊施設ではなく、「人財が織りなす感動体験の創造拠点」です。このビジョンを実現するためには、経営層から現場スタッフまで、ホテルに関わる全ての人間が、ホスピタリティの本質とは何かを常に問い直し、日々の業務に人間力を注ぎ込む努力を惜しまないことが求められます。
私たちは、この「人財」という宝を大切に育み、その力が最大限に発揮されるホテル運営を追求することで、業界の未来を切り拓いていけるはずです。


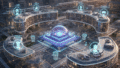
コメント