はじめに
2025年現在、日本のホテル市場においてオンライン旅行代理店(OTA)は、もはや単なる予約チャネルという枠を超え、集客戦略の根幹をなす存在となっています。国内外からの旅行需要が多様化し、情報収集から予約、決済までがオンラインで完結する現代において、OTAの存在感は増すばかりです。しかし、その一方で、OTAに過度に依存することによる手数料負担やブランド価値の希薄化、価格競争の激化といった課題も顕在化しています。
本記事では、ホテル業界に精通したアナリストの視点から、日本のホテル市場における主要な国内OTAと海外OTAを具体的に挙げ、それぞれの特徴、売り上げ規模、利用者の国籍比率などを徹底的に比較・解説します。さらに、運用現場で直面する泥臭い課題や、現場スタッフ、エンドユーザーのリアルな声を拾い上げながら、ホテルがOTAと賢く共存し、持続的な成長を遂げるための戦略について深掘りしていきます。
OTAの台頭と日本のホテル市場への影響
OTAが日本のホテル市場で不可欠な存在となった背景には、インターネットとスマートフォンの普及による旅行予約行動の変化が大きく関わっています。かつては旅行代理店の店頭や電話予約が主流でしたが、今や多くの旅行者がPCやスマホで複数のホテルを比較検討し、最安値や最適なプランを探すのが当たり前です。OTAは、このニーズに応える形で、多種多様な宿泊施設を一元的に検索・予約できるプラットフォームを提供し、その利便性から急速に市場を拡大しました。
ホテル側から見れば、OTAは広範な顧客層、特に自社のマーケティングではリーチしにくい層への露出を可能にする強力な集客ツールです。特に、インバウンド需要の増加に伴い、海外からの旅行者にとって、多言語対応や国際的な決済手段を提供する海外OTAは、日本への旅行を計画する上で不可欠な窓口となっています。
しかし、この集客力と引き換えに、ホテルはOTAに予約手数料を支払う必要があります。この手数料は、一般的に宿泊料金の10%から25%程度に及び、ホテルの利益を圧迫する大きな要因となっています。特に、稼働率を上げたい時期や、競合との価格競争が激しい市場では、OTAへの依存度が高まり、結果として収益性の低下を招く「OTA依存症」とも呼ばれる状況に陥るホテルも少なくありません。
主要な国内OTAとその特徴
日本のホテル市場において、国内OTAは日本人旅行者の予約行動に深く根ざしています。主なプレイヤーとしては、じゃらんnet、楽天トラベル、一休.comなどが挙げられます。
じゃらんnet
リクルートグループが運営するじゃらんnetは、国内旅行市場において圧倒的な知名度と利用率を誇ります。その特徴は、日本全国津々浦々の宿泊施設を網羅する掲載数と、地域に特化した特集記事や観光情報が充実している点にあります。ユーザーは、温泉地やテーマパーク周辺など、具体的な旅行の目的や場所から宿を探しやすく、詳細なレビューや写真も豊富です。
- 売上規模:国内旅行市場においてトップクラスの流通総額を誇り、特に個人旅行者の利用が多いです。
- 利用者の国籍比率:ほぼ日本人利用者に特化しています。国内旅行のニーズを深く捉え、季節ごとのイベントや地域振興キャンペーンなど、日本人の嗜好に合わせたプロモーションを積極的に展開しています。
- ホテル市場からの視点:
- メリット:日本国内の幅広い顧客層にリーチできるため、安定した集客が見込めます。リクルートポイントとの連携もユーザーにとって魅力的です。
- デメリット:価格競争が激しくなりがちで、手数料も一定水準かかります。特定の時期には掲載順位を上げるための広告費も考慮する必要があります。
楽天トラベル
楽天グループが運営する楽天トラベルは、楽天経済圏との強力な連携が最大の強みです。楽天ポイントの獲得・利用が可能であるため、日常的に楽天サービスを利用するユーザーにとっては非常に魅力的な選択肢となります。じゃらんnetと同様に国内旅行者に強く、出張利用などビジネスユースにも対応したプランが豊富です。
- 売上規模:じゃらんnetと並び、国内旅行市場の二強を形成しています。楽天ポイント経済圏の拡大と共に、その流通総額も成長を続けています。
- 利用者の国籍比率:主に日本人利用者が中心ですが、近年は楽天グループのグローバル展開に伴い、一部の外国人旅行者による利用も見られます。
- ホテル市場からの視点:
- メリット:楽天会員という強固な顧客基盤からの集客が期待でき、ポイント付与によるリピーター育成にもつながります。システム連携も比較的スムーズな場合が多いです。
- デメリット:こちらも価格競争が激しく、ポイント還元率を考慮した料金設定が求められることがあります。
一休.com
一休.comは、高級ホテルや旅館、レストランに特化したOTAとして独自の地位を築いています。ハイクラスな宿泊体験を求める富裕層や記念日利用のカップル層に支持されており、厳選された施設のみを掲載することで、ブランドイメージを高く保っています。
- 売上規模:掲載施設数は大手OTAより少ないものの、高単価な予約が多いため、流通総額は一定の規模を維持しています。
- 利用者の国籍比率:ほぼ日本人利用者が中心です。
- ホテル市場からの視点:
- メリット:高単価な顧客層にアプローチでき、ホテルのブランド価値を損なわずに集客が可能です。掲載基準が厳しいため、競合が限定的になることもあります。
- デメリット:掲載には一定の基準を満たす必要があり、手数料も高めに設定されている傾向があります。
国内OTA運用現場の声
国内OTAは、日本の商習慣や文化に根ざしているため、比較的スムーズな運用が可能です。しかし、現場スタッフからは以下のような声が聞かれます。
「じゃらんも楽天も、日本人のお客様にとっては使い慣れたサイトだから、集客力は本当に助かっています。でも、やっぱり手数料は大きいですね。特に週末や祝日など、稼働率が高い日でも手数料を払うのは正直もったいないと感じることもあります。あと、ポイント還元率を高く設定しないと、なかなか予約が入らない時期もあって、価格競争に巻き込まれがちです。自社サイトからの予約を増やしたいのですが、なかなか難しいのが現状です。」(都内ビジネスホテル支配人)
「システム連携は国内OTAの方がトラブルが少ない印象です。ただ、直前割引やクーポン配布など、頻繁なプロモーション変更に対応するのが大変です。特に人手不足の時は、各OTAの管理画面を開いて設定を変更するだけでもかなりの時間と手間がかかります。」(地方温泉旅館予約担当)
主要な海外OTAとその特徴
海外OTAは、日本のホテルにとってインバウンド集客の生命線とも言える存在です。特にコロナ禍後のインバウンド回復期においては、その重要性が再認識されています。主なプレイヤーとしては、Booking.com、Expedia Group、Agoda、そして近年ホテル市場への進出を強化するAirbnbが挙げられます。
Booking.com
オランダに本社を置くBooking Holdings傘下のBooking.comは、世界最大級のOTAであり、特に欧米からのインバウンド旅行者にとっての主要な予約チャネルです。多言語対応はもちろんのこと、幅広い価格帯の宿泊施設を網羅し、ユーザーフレンドリーなインターフェースが特徴です。
- 売上規模:世界中の旅行市場で圧倒的な流通総額を誇ります。日本市場においてもインバウンド予約で非常に大きなシェアを持っています。
- 利用者の国籍比率:欧米からの旅行者が中心ですが、アジア圏を含む世界中の国籍の利用者がいます。日本のホテルにとっては、多様な国籍のインバウンド集客に不可欠です。
- ホテル市場からの視点:
- メリット:グローバルな集客力は圧倒的で、自社ではリーチできない世界中の顧客にアプローチできます。多言語対応のカスタマーサポートも充実しています。
- デメリット:手数料率が国内OTAよりも高い傾向にあります。また、無料キャンセル期間が長く設定されることが多く、ノーショーのリスクや直前キャンセルによる機会損失が発生しやすいという課題もあります。支払いサイトが長いことも、キャッシュフローに影響を与える可能性があります。
Expedia Group (Expedia, Hotels.comなど)
アメリカに本社を置くExpedia Groupは、Expedia.com、Hotels.com、Vrboなど複数のブランドを展開する世界最大級のOTAです。航空券やレンタカーとのパッケージ販売に強みがあり、特に北米からの旅行者に人気があります。日本市場においても、アジア太平洋地域からのインバウンド集客に貢献しています。
- 売上規模:Booking.comと並び、グローバル市場の二強を形成しています。パッケージ販売による流通総額も大きいです。
- 利用者の国籍比率:北米、欧州、オーストラリアなどからの旅行者が多く、特に長期滞在や周遊旅行を計画する層に利用されます。
- ホテル市場からの視点:
- メリット:航空券とのバンドル販売は、ホテル単体での集客では難しい顧客層を獲得するチャンスとなります。多様なプロモーションツールが提供されています。
- デメリット:手数料率は高めであり、無料キャンセルポリシーもBooking.comと同様に課題となることがあります。また、システムや管理画面が複雑に感じられることもあります。
Agoda
シンガポールに本社を置くAgodaは、Booking Holdings傘下であり、特にアジア市場に強いOTAです。日本を含むアジア圏からのインバウンド旅行者に広く利用されており、モバイルアプリの使いやすさや、アジアの文化圏に合わせたプロモーションが特徴です。
- 売上規模:アジア太平洋地域において高いシェアを持ち、日本への旅行を計画するアジア人旅行者にとって主要なプラットフォームの一つです。
- 利用者の国籍比率:中国、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポールなど、アジア圏からの利用者が圧倒的に多いです。
- ホテル市場からの視点:
- メリット:アジアからのインバウンド需要を効果的に取り込むことができます。モバイル予約に力を入れているため、若年層の集客にも繋がります。
- デメリット:手数料はBooking.comやExpedia Groupと同様に高めです。また、アジア市場特有の決済方法や文化的な背景を理解した対応が求められることがあります。
Airbnb
民泊のイメージが強いAirbnbですが、近年はホテルや旅館といった伝統的な宿泊施設も積極的に取り込み、OTAとしての存在感を高めています。特にユニークな宿泊体験や地域に根ざした滞在を求める層に人気があり、他のOTAとは異なる客層を獲得できる可能性があります。
- 売上規模:民泊市場で圧倒的なシェアを持つ一方、ホテル・旅館の掲載も増え、その流通総額は拡大傾向にあります。
- 利用者の国籍比率:多様な国籍の利用者がいますが、特に欧米からの個人旅行者や、長期滞在を希望する層に利用されることが多いです。
- ホテル市場からの視点:
- メリット:他のOTAでは見つからないような、体験価値を重視する顧客層にアプローチできます。ホテルの個性やストーリーを伝えるのに適しています。
- デメリット:民泊との差別化が難しい場合があり、ホテルとしてのブランドイメージをどのように保つかが課題となることもあります。料金体系が他のOTAと異なるため、運用に慣れが必要な場合があります。
海外OTA運用現場の声
海外OTAはインバウンド集客に不可欠である一方、現場では特有の課題に直面しています。
「Booking.comやExpediaは、外国人のお客様が日本のホテルを見つける上で本当に強いです。特にゴールデンウィークや紅葉の時期など、インバウンドの需要が高まる時期には、海外OTAからの予約が全体の半分以上を占めることも珍しくありません。ただ、手数料が国内OTAより高いのがネックです。あと、無料キャンセル期間が長いプランが多くて、ノーショーや直前キャンセルにヒヤヒヤすることも。部屋を空けて待っていたのに、直前でキャンセルされると、その部屋の売上を失うだけでなく、他の予約を受けられなかった機会損失も発生します。支払いサイクルも国内より長いので、資金繰りの面でも注意が必要です。」(観光地ホテル予約担当)
「Agodaはアジア圏のお客様が多いので、サイトの言語対応や決済方法の多様性は助かります。しかし、外国人のお客様からの問い合わせは、英語だけでなく中国語や韓国語など多言語に対応する必要があり、フロントスタッフの負担は大きいです。翻訳ツールを使っても、ニュアンスが伝わらなかったり、緊急時の対応が遅れたりすることもあります。」(国際空港近郊ホテルフロントスタッフ)
「Airbnbは民泊のイメージが強いですが、最近はうちのような旅館も掲載を始めています。面白いお客様が多いですが、他のOTAとは少し客層が違いますね。よりパーソナルな体験を求める方が多く、問い合わせも個性的です。ただ、システムが他のOTAとは少し違うので、慣れるまで時間がかかりました。」(古民家再生旅館女将)
国内OTAと海外OTAの徹底比較
日本のホテル市場から見た国内OTAと海外OTAの比較は、それぞれの特性を理解し、戦略的な活用を考える上で不可欠です。
集客力とターゲット層
- 国内OTA:主に日本国内の旅行者をターゲットとしており、国内旅行市場での集客力は非常に高いです。地域密着型コンテンツや日本人向けのプロモーションに強みがあります。
- 海外OTA:世界中の旅行者をターゲットとし、特にインバウンド集客において圧倒的な力を持ちます。Booking.comは欧米、Agodaはアジアといったように、それぞれ得意な地域があります。
手数料率
- 国内OTA:一般的に10%~15%程度のレンジが多く見られます。
- 海外OTA:一般的に15%~25%程度と、国内OTAに比べて高めに設定されている傾向があります。これは、グローバルなマーケティング費用や多言語対応、国際的な決済システム維持コストなどが反映されているためと考えられます。
プロモーションと露出
- 国内OTA:日本人向けの季節ごとの特集、ポイントキャンペーン、クーポン配布などが頻繁に行われます。掲載順位を上げるための広告枠購入も一般的です。
- 海外OTA:早期割引、連泊割引、モバイル限定割引など、グローバルスタンダードなプロモーションが中心です。特に、Geniusプログラム(Booking.com)やVIP Access(Expedia)などのロイヤルティプログラムを通じて、リピーターを囲い込む戦略が特徴です。
システム連携と運用負荷
- 国内OTA:日本のホテルシステム(PMSやチャネルマネージャー)との連携は比較的スムーズな場合が多いです。管理画面も日本語対応が充実しており、操作性は高いです。
- 海外OTA:多機能ゆえに管理画面が複雑に感じられることや、システム連携において細かな調整が必要な場合があります。多言語対応の必要性から、運用スタッフの負担が増すこともあります。
支払いサイクルとキャンセルポリシー
- 国内OTA:比較的支払いサイクルが短く、ノーショー対策も日本独自の文化(当日連絡なしキャンセルへの対応など)に合わせた設定が可能です。
- 海外OTA:無料キャンセル期間が長く設定されることが多く、ノーショーや直前キャンセルによるリスクが高いです。支払いサイクルも国内OTAに比べて長い傾向があり、キャッシュフロー管理に注意が必要です。
カスタマーサポート
- 国内OTA:日本語でのサポートが充実しており、問題発生時の対応も比較的迅速です。
- 海外OTA:多言語対応のサポートを提供していますが、担当者によって対応品質にばらつきがあったり、時差の関係で連絡が取りづらい時間帯があったりすることもあります。
データ活用
- 各OTA:それぞれ予約データや顧客属性データを提供していますが、その粒度や分析のしやすさは異なります。ホテル側はこれらのデータを自社のレベニューマネジメントやマーケティング戦略にどう活かすかが問われます。
OTA依存からの脱却と新たな集客戦略
OTAの集客力は魅力的ですが、手数料負担や価格競争の激化、ブランド価値の希薄化といった課題から、ホテルはOTAへの過度な依存から脱却し、多様な集客チャネルを構築する必要があります。その中心となるのが直販の強化であり、近年注目されているのがソーシャルコマースの台頭です。
直販の強化
自社ウェブサイトからの直接予約は、手数料がかからないため、最も収益性の高い予約チャネルです。ホテルのウェブサイトを魅力的に作り込み、SEO対策やリスティング広告、SNS連携などを通じて、より多くのユーザーを自社サイトに誘導することが重要です。また、リピーター育成のためのCRM(顧客関係管理)戦略も不可欠です。過去の宿泊履歴や嗜好に基づいたパーソナライズされたオファーは、顧客ロイヤルティを高め、直販への誘導に繋がります。
詳細については、ホテル直販強化の真価:非テクノロジーで顧客ロイヤルティを育む人間力の記事もご参照ください。
ソーシャルコマースの台頭
2025年現在、InstagramやTikTokといったソーシャルメディアは、単なる情報発信ツールではなく、直接的な購買行動へと繋がる「ソーシャルコマース」の場として進化を遂げています。特にホテル業界においては、視覚的に魅力的なコンテンツが宿泊意欲を掻き立てるため、ソーシャルメディアは強力な集客チャネルとなり得ます。
ここで、OTAとソーシャルコマースの対比について触れている興味深いニュース記事を紹介します。
世間のニュース記事からの深掘り: Airbnb、ホテル拡大準備してOTAsと競争 – 観光経済新聞
記事タイトル: Navigating the Next Frontier of Social Commerce in Hospitality – Hospitality Net
URL: https://www.hospitalitynet.org/news/4128848.html
このニュース記事では、OTAとソーシャルメディア(特にTikTok)におけるホテルの見え方の違いについて、以下のように述べています。
引用文: “On an OTA, hotels compete in a grid of thumbnails, prices, and star ratings. On TikTok, a property appears in a story told through a creator’s lens, a couple waking up to a panoramic view, a family exploring the pool, or a solo traveller sharing a personal highlight. The result is emotional, experiential, and immediate in a way static listings rarely achieve. […] of dealing directly with the hotel can transform an otherwise anonymous OTA booking into the start of a genuine relationship. […] any paid OTA placement.”
日本語訳: 「OTAでは、ホテルはサムネイル、価格、星評価のグリッドの中で競争します。TikTokでは、クリエイターのレンズを通して語られる物語として、パノラマビューで目覚めるカップル、プールを探検する家族、個人的なハイライトを共有する一人旅の旅行者として、施設が登場します。その結果は、静的なリストではめったに達成できない、感情的で、体験的で、即時的なものです。[…] ホテルと直接取引することで、匿名的なOTA予約が本物の関係の始まりへと変わる可能性があります。[…] 有料のOTA掲載とは異なります。」
この引用が示唆するように、OTAが「機能と価格」で比較される場であるのに対し、ソーシャルメディアは「感情と体験」を訴求する場です。ホテルは、単なる宿泊施設ではなく、「体験創造業」として、その魅力を物語として発信することで、ユーザーの心に深く響く集客が可能になります。特にTikTokのようなプラットフォームでは、動画コンテンツを通じてホテルの雰囲気、サービス、周辺の魅力などをリアルに伝えることができ、ユーザーは「ここに泊まりたい」という強い感情を抱きやすくなります。そして、この感情が直接予約へと繋がる可能性を秘めています。
ソーシャルコマースの活用は、OTAに支払う手数料を削減し、ホテルと顧客の間に直接的な関係を築く上で非常に有効な戦略です。ホテルは、クリエイターとのコラボレーションや、UGC(User Generated Content)の活用を通じて、よりオーセンティックな魅力を発信し、ブランドロイヤルティを高めることができるでしょう。
ソーシャルメディアを活用した集客戦略については、TikTokが変えるホテル集客2025:AIとデータ分析で最大化するブランド価値も参考になります。
現場のリアルな声と泥臭い課題
OTAは集客の強い味方である一方、運用現場では様々な「泥臭い課題」に直面しています。
- OTA手数料が経営を圧迫する現実:
「稼働率を上げるためにOTAに頼るのは仕方ないですが、正直、毎月何百万円も手数料として消えていくのを見ると、ため息が出ます。特に高単価な客室がOTA経由で予約されると、その分利益が大きく削られるわけで、どうにか直販を増やしたいと常に考えています。」(シティホテル総支配人)
- 価格競争の激化によるブランド価値の希薄化:
「OTAでは価格比較が容易なので、どうしても『一番安いホテル』という見方をされがちです。私たちのホテルはサービスや体験にこだわっているのに、価格だけで判断されるのは心外です。ブランドイメージを保ちつつ、OTAで集客するのは本当に難しいバランス感覚が求められます。」(リゾートホテルマーケティング担当)
- ノーショー(無断キャンセル)問題:
「海外OTAからの予約で、無料キャンセル期間が長いプランは、本当にノーショーが多いです。特に連休前など、満室なのに実際には来ないお客様が数組いると、他の予約を受けられたはずの機会損失が大きすぎます。キャンセルポリシーの厳格化も検討しますが、お客様の利便性を考えると踏み切れない部分もあります。」(ビジネスホテル予約担当)
- レビュー管理の難しさ:
「OTAのレビューは集客に直結するので、常にチェックして返信するようにしています。でも、中には事実と異なる内容や、理不尽な評価もあり、どう対応すべきか悩むことも。特に海外のお客様からのレビューは、文化的な背景の違いから誤解が生じることもあり、多言語での丁寧な対応が求められます。」(ホテル広報担当)
- チャネルマネージャーの運用負担と人手不足:
「複数のOTAに掲載していると、料金や在庫の管理が本当に大変です。チャネルマネージャーを導入していますが、それでも設定ミスがないか常に目を光らせる必要があります。特に、急な空室が出た場合など、リアルタイムで全チャネルの在庫を更新するのは、人手不足の現場では大きな負担です。」(宿泊部門マネージャー)
チャネルマネージャーの効率的な運用は、2025年ホテル業界の最前線:PMSクラウド化が導く顧客・従業員・収益の革新にも関連する重要なテーマです。
- 多言語対応の必要性:
「インバウンドのお客様が増えるのは嬉しいですが、予約時の問い合わせからチェックイン、滞在中、チェックアウトまで、あらゆる場面で多言語対応が求められます。特に海外OTAからの予約は、特殊なリクエストや現地でのトラブル対応など、英語以外の言語でのコミュニケーションが必要になることも多く、現場スタッフの語学力向上は喫緊の課題です。」(フロントデスク責任者)
2025年、ホテルがOTAと共存し、成長するための戦略
OTAは今後もホテル集客の重要なチャネルであり続けるでしょう。2025年のホテル業界において、OTAと賢く共存し、持続的な成長を遂げるためには、以下の戦略が不可欠です。
1. OTAを「集客ツール」と割り切り、戦略的に活用する
OTAは、あくまでホテルの存在を広く知らしめ、新規顧客を獲得するための「ツール」と捉えるべきです。特に、認知度が低いホテルや、新たな市場(例えば特定の国からのインバウンド層)に参入する際には、OTAの強力な集客力を最大限に利用します。ただし、その際も手数料に見合うだけの価値があるか、常に費用対効果を検証することが重要です。
2. ブランド価値を高め、直販への誘導を強化する
OTA経由でホテルを知った顧客を、次の予約からは自社サイトへ誘導する戦略が不可欠です。ホテルのウェブサイトを魅力的にデザインし、OTAでは提供できない限定プランや特典(例:直販限定アメニティ、レイトチェックアウトなど)を用意することで、直販の優位性を示します。また、ホテル滞在中に顧客に最高の体験を提供し、リピート意欲を高めることで、次回の予約を直販に繋げます。これは、ホテル業界の「テクノロジーギャップ」:人間力と融合で創るシームレスな体験にも通じる、人間力による差別化の真骨頂です。
3. データに基づいたレベニューマネジメントの徹底
各OTAから得られる予約データや顧客データを統合し、AIを活用したレベニューマネジメントシステムを導入することで、最適な価格設定と在庫管理を実現します。これにより、OTA手数料を支払っても十分に利益が出るような、戦略的な価格設定が可能になります。需要予測に基づき、OTAへの在庫配分を最適化し、稼働率と収益の最大化を図ります。
この分野については、2025年ホテル業界の戦略的進化:AIと人間力が創るレベニューマネジメントで詳しく解説しています。
4. チャネルマネージャーの最適化と自動化
複数のOTAを一元管理するチャネルマネージャーは、運用負担を軽減し、オーバーブッキングを防ぐ上で不可欠なツールです。最新のチャネルマネージャーはAIを活用し、最適な在庫配分や価格調整を自動で行う機能も備えています。これにより、人為的なミスを減らし、スタッフがより顧客対応に集中できる環境を整えます。
5. 人間力による差別化と顧客体験の向上
OTAが提供するのは、あくまで「宿泊」という商品情報です。しかし、ホテルが提供するのは、その場所での「体験」と「ホスピタリティ」です。チェックインからチェックアウトまで、スタッフの温かいおもてなし、パーソナライズされたサービス、そしてホテル独自の魅力的なコンテンツを通じて、顧客に忘れられない体験を提供することが、最終的にOTAとの差別化に繋がります。OTAのレビューに左右されない、本物の顧客ロイヤルティを築くためには、テクノロジーだけでは届かない「人間力」が不可欠です。
まとめ
2025年の日本のホテル市場において、OTAは依然として強力な集客チャネルであり続けます。国内OTAは日本人旅行者、海外OTAはインバウンド旅行者という明確なターゲット層を持ち、それぞれがホテルの売上に大きく貢献しています。しかし、手数料負担、価格競争、運用負荷といった課題も無視できません。
ホテルは、OTAを単なる予約サイトとしてではなく、戦略的なマーケティングツールとして位置づけ、その特性を最大限に活用しつつ、過度な依存から脱却する道を模索する必要があります。直販の強化、ソーシャルコマースの活用、データに基づいたレベニューマネジメント、そして何よりも「人間力」による唯一無二の顧客体験の提供が、これからのホテル経営において不可欠な要素となるでしょう。
OTAと共存し、競争力を高めるためには、テクノロジーの進化を積極的に取り入れながらも、ホテルの本質である「おもてなし」の心を決して忘れてはなりません。デジタルとアナログ、効率と人間力を融合させたハイブリッドな戦略こそが、日本のホテル業界が未来へ向けて飛躍するための鍵となるのです。


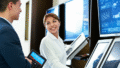
コメント