はじめに
2025年を迎えた現在、ホテル業界は未曾有の人材確保の課題に直面しています。特に、コロナ禍を経て回復基調にある観光需要に対し、現場を支えるスタッフの採用と定着は喫緊の経営課題です。総務人事部には、単なる採用活動に留まらず、従業員が長期的にキャリアを築き、組織に貢献し続けるための戦略的な人材マネジメントが求められています。従来の画一的な採用手法や研修プログラムでは、多様化する労働市場のニーズに応えきれないのが現状です。ホテル業界特有の業務負荷や不規則な勤務体系、そしてキャリアパスの不明瞭さが、離職率の高さに拍車をかけている側面も否定できません。
このような状況下で、既存の枠にとらわれない革新的な人材戦略を展開し、成果を上げている事例は、総務人事部にとって貴重な示唆を与えます。本稿では、特定のホテルチェーンが実践するユニークな「支配人・副支配人制度」に焦点を当て、その採用、育成、そして離職率低減への効果を深く掘り下げていきます。この事例から、総務人事部が学ぶべき具体的な戦略と、持続可能な組織を構築するためのヒントを探ります。
スーパーホテル「Super Dream Project」が示す新たな人材戦略
ホテル業界における人材戦略の成功事例として、スーパーホテルの「Super Dream Project」は注目に値します。このプロジェクトは、一般的な従業員採用とは一線を画し、ビジネスオーナーとしての独立を志向する夫婦を対象とした支配人・副支配人制度を基盤としています。マイナビニュースの記事「スーパーホテル「Super Dream Project」に、それぞれの夢を持って挑戦した3組のカップルの現在地」では、この制度に挑戦したカップルの実情が具体的に紹介されています。
この制度の最大の特徴は、単にホテルスタッフを雇用するのではなく、夫婦でホテルの運営を任せるという点にあります。契約社員としてホテル運営を経験し、その期間中にビジネススキルやホスピタリティを習得。契約満了後には、スーパーホテルでの再契約や、独立して別の事業を始めるなど、多様なキャリアパスが用意されています。これは、従来のホテル業界における「従業員」という枠組みを超え、「ビジネスパートナー」として人材を捉える視点であり、総務人事部が抱える採用難や早期離職といった課題に対し、新たな解決策を提示するものです。
この制度がなぜホテル業界の課題解決に有効なのか。それは、従業員に「働く意味」と「明確な将来像」を与えることに成功しているからです。一般的なホテルスタッフの仕事は、ルーティン業務が多く、キャリアの天井が見えやすいと感じる人も少なくありません。しかし、この制度では、自らがホテルの経営を担うという責任と裁量が与えられ、その成果が直接報酬に反映されるため、高いモチベーションを維持しやすい構造になっています。また、夫婦で協力して事業を運営するという点は、相互のサポート体制を強化し、精神的な負担を軽減する効果も期待できます。
「夫婦支配人・副支配人制度」がもたらす採用の優位性
スーパーホテルの「夫婦支配人・副支配人制度」は、従来のホテル業界の採用手法とは異なる、明確な優位性を持っています。
ターゲット層の明確化と「生き方」の提案
この制度の採用ターゲットは、「ビジネスオーナーとして独立したい」「夫婦で協力して何かを成し遂げたい」という強い意欲を持つカップルです。これは、単に「ホテルで働きたい」という動機だけでなく、「自身の夢を実現したい」という、より深い願望に訴えかけるものです。総務人事部が採用活動を行う際、求職者に提供できる価値は給与や福利厚生、職務内容だけではありません。スーパーホテルの事例は、「働く」という行為を通じて、求職者の「生き方」そのものを提案するという、新たな採用戦略の可能性を示しています。
これにより、応募者は単なる労働力としてではなく、自身のキャリアや人生設計の一部としてこの制度を捉えるため、入社後のミスマッチが起こりにくく、高いエンゲージメントが期待できます。一般的なホテル業界では、入社後のキャリアパスが不明瞭であると感じ、早期に離職してしまうケースも少なくありません。しかし、この制度では、契約期間満了後の選択肢が明確に提示されており、それが求職者の安心感とモチベーションに繋がっています。
採用プロセスにおける実践的な研修設計
採用プロセス自体も、候補者の適性を見極め、かつ実践的なスキルを習得させるように設計されています。マイナビニュースの記事にもあるように、本社での接客基礎や言葉遣いを学ぶ座学研修に加え、先輩支配人・副支配人夫婦の指導のもと、ホテルに泊まり込んで実地研修が行われます。
この実地研修の価値は計り知れません。実際のホテル運営の現場で、お客様対応、清掃管理、売上管理、スタッフマネジメントなど、多岐にわたる業務を体験することで、机上の知識だけでは得られない「生きたスキル」を身につけることができます。また、先輩夫婦からの直接指導は、成功事例や失敗談、そして夫婦で働く上でのコミュニケーションのコツなど、実践的なノウハウを学ぶ絶好の機会となります。これにより、研修期間中に、候補者は自身がホテル運営に向いているか、夫婦で協力してやっていけるかを見極めることができ、企業側も候補者の適性をより深く評価することが可能になります。
これは、単にスキルを教えるだけでなく、「ビジネスオーナーとしてのマインドセット」を醸成する上でも非常に効果的です。研修を通じて、責任感、問題解決能力、そしてお客様に最高の体験を提供するための主体性が自然と育まれます。
関連する記事として、総務人事部が新入社員の離職を防ぐために、凡庸な作業に「意味」を与える戦略の重要性を説く「新入社員の離職を防ぐ:凡庸な作業に「意味」を与える総務人事戦略」も参考になるでしょう。スーパーホテルの制度は、この「意味付け」を最初から内包していると言えます。
自律と成長を促す育成モデル
スーパーホテルの支配人・副支配人制度は、採用段階から「ビジネスオーナー」としての意識を育むことを重視していますが、その育成モデルもまた、従業員の自律性と成長を最大限に引き出すように設計されています。
現場でのOJTと権限移譲の重要性
研修期間を終え、実際にホテル運営を任されるようになると、支配人・副支配人夫婦には大きな裁量が与えられます。これは、一般的なホテル従業員が経験するOJT(On-the-Job Training)とは質が異なります。彼らは、単に指示された業務をこなすだけでなく、売上目標の達成、コスト管理、顧客満足度向上、スタッフ採用・育成といった、ホテルの経営全般にわたる責任を負います。
この広範な権限移譲は、短期間でビジネススキルを飛躍的に向上させる原動力となります。例えば、清掃スタッフのシフト管理一つをとっても、コストと品質のバランスを考慮し、自ら最適な解を見つけ出す必要があります。お客様からのクレーム対応も、マニュアル通りではなく、その場の状況に応じて最適な解決策を判断し、実行する力が求められます。これらの経験は、実践的な問題解決能力、意思決定能力、そしてリーダーシップを養う上で不可欠です。
現場での成功と失敗を通じて、彼らは自身の強みと弱みを認識し、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善を図ります。この「自律的な学び」のプロセスこそが、真のビジネスオーナーとしての成長を促すのです。
研修期間中のサポート体制と独立後のフォロー
しかし、大きな裁量を与える一方で、企業側は適切なサポート体制を構築しています。研修期間中は先輩夫婦からの指導に加え、本社の担当者による定期的なフォローアップも行われます。これにより、夫婦支配人が孤立することなく、困った時には相談できる環境が確保されています。また、運営マニュアルやITシステムといったインフラも整備されており、彼らが円滑に業務を遂行できるよう支援しています。
さらに、この制度の魅力は、契約期間満了後のキャリアパスが明確に示されている点にあります。再契約して引き続きスーパーホテルの運営を担う道もあれば、ホテル運営で培った経験やスキルを活かして、飲食業や小売業など、全く異なる分野で独立開業する道も開かれています。企業側は、単に契約期間中の労働力を確保するだけでなく、彼らの「夢」の実現をサポートするという長期的な視点を持っています。この手厚いサポートと明確な将来展望が、支配人・副支配人夫婦のモチベーションを高く維持し、結果としてホテル全体のサービス品質向上にも繋がっています。
総務人事部にとって、このような育成モデルは、従業員に「成長の機会」と「キャリアの選択肢」を明確に提示することの重要性を示唆しています。画一的な研修ではなく、個々の成長段階や意欲に応じた、よりパーソナライズされた育成プログラムの設計が、これからの時代には不可欠となるでしょう。
離職率低減と定着を実現する制度設計
ホテル業界の総務人事部が最も頭を悩ませる課題の一つが、高い離職率です。スーパーホテルの「夫婦支配人・副支配人制度」は、この課題に対して、いくつかの有効な解決策を提供しています。
成果報酬型賃金体系とモチベーション維持
この制度の根幹をなすのが、成果報酬型の賃金体系です。支配人・副支配人夫婦の報酬は、ホテルの売上や利益、顧客満足度といった具体的な成果に連動します。これにより、彼らは単なる給与所得者ではなく、自らの努力が直接収入に反映される「ビジネスオーナー」としての強い意識を持つことができます。
一般的なホテル従業員の場合、どれだけ努力して成果を出しても、基本給や手当に大きな差が出にくいことがあります。これが、モチベーションの低下や、より良い条件を求めての離職に繋がる一因となります。しかし、成果報酬型であれば、自らの創意工夫や努力が明確な形で報われるため、仕事へのエンゲージメントが格段に高まります。「自分たちのホテル」という意識が芽生え、コスト削減やサービス改善にも積極的に取り組むようになります。この高いモチベーションが、結果として離職率の低減に大きく貢献しているのです。
夫婦で働くことのメリットと課題
夫婦で働くという形態は、多くのメリットをもたらします。まず、相互のサポート体制が強固になる点です。ホテル運営は多岐にわたる業務があり、一人で全てをこなすのは困難です。夫婦であれば、お互いの得意分野を活かし、協力して業務を分担することができます。例えば、一方がフロント業務に集中している間に、もう一方が清掃状況の確認や備品の発注を行うなど、柔軟な連携が可能です。
また、精神的な支えとしての役割も大きいでしょう。ホテル運営には予期せぬトラブルやお客様からの厳しい意見もつきものです。そのような時、最も身近なパートナーが隣にいることで、ストレスを共有し、乗り越える力を得ることができます。これは、単身で働く従業員には得難いメリットです。
一方で、夫婦で働くことには課題も存在します。仕事とプライベートの境界線が曖昧になりがちであること、意見の対立が仕事だけでなく家庭生活にも影響を及ぼす可能性などです。総務人事部は、このような潜在的な課題を認識し、夫婦間のコミュニケーションを円滑にするためのアドバイスや、時にはメンタルヘルスサポートの提供も検討する必要があるでしょう。しかし、スーパーホテルの事例では、この「夫婦で働く」という点が、むしろ一体感と責任感を高め、高い定着率に繋がっていることが示唆されています。
「ホテル人材の定着戦略:総務人事が築く「成長」と「意味」の育成ロードマップ」(https://hotelx.tech/?p=2331)でも述べられているように、従業員が仕事に「意味」を見出し、「成長」を実感できる環境を提供することが、定着には不可欠です。スーパーホテルの制度は、その両方を高いレベルで満たしていると言えます。
契約期間満了後の多様なキャリアパス
この制度は、契約期間が2年間と定められています。しかし、この期間が終了した後も、支配人・副支配人夫婦には多様な選択肢が用意されています。一つは、スーパーホテルとの契約を更新し、引き続き支配人・副支配人としてホテル運営を続ける道です。これは、安定した収入と、これまでの経験を活かせるメリットがあります。
もう一つは、スーパーホテルで培ったホテル運営のノウハウ、ビジネススキル、そして独立開業に必要な資金を元手に、全く新しい事業を立ち上げる道です。飲食業、小売業、コンサルティング業など、その可能性は無限大です。スーパーホテルは、彼らが独立して成功することを応援しており、これは「Super Dream Project」という名称が示す通り、彼らの夢の実現を支援する企業文化の表れです。
このような明確で多様なキャリアパスが提示されていることは、従業員の離職率低減に非常に有効です。多くのホテル従業員は、将来のキャリアが見えにくいと感じ、他の業界への転職を考えることがあります。しかし、スーパーホテルの制度は、「2年間でビジネスオーナーとしてのスキルを身につけ、その後の人生を自由にデザインできる」という、非常に魅力的な展望を提供します。これは、従業員が短期的な視点ではなく、長期的な視点で自身のキャリアを考え、スーパーホテルでの経験をそのステップとして捉えることを可能にします。結果として、契約期間中のモチベーションが維持され、高い定着率に繋がっているのです。
この点は、総務人事部が「見える」キャリアパスを描くことの重要性を指摘する「ホテル早期離職を断つ:総務人事が描く「見える」キャリアパスと持続経営」(https://hotelx.tech/?p=2347)とも深く関連しています。スーパーホテルは、そのキャリアパスを制度設計そのものに組み込んでいる点で先進的です。
現場のリアルな声:成功体験と制度の魅力
マイナビニュースの記事では、実際にこの制度に挑戦したカップルの声が紹介されています。ある夫婦は、「お客様から直接感謝の言葉をいただいた時、この仕事のやりがいを強く感じた」と語っています。また、別の夫婦は、「夫婦で協力して目標を達成する喜びは、何物にも代えがたい」と述べています。これらの声は、この制度が単なる労働契約ではなく、「自己成長」「達成感」「パートナーシップ」といった、より深い価値を提供していることを示しています。
現場の支配人・副支配人夫婦は、自分たちのホテルを「我が家」のように大切に運営し、お客様を「家族」のように迎え入れるという意識を持っています。これは、彼らがビジネスオーナーとしての責任を自覚し、同時にホスピタリティの本質を深く理解している証拠です。このような成功体験が、新たな挑戦者を惹きつけ、制度全体の魅力を高める好循環を生み出しています。
総務人事が学ぶべき「Super Dream Project」の本質
スーパーホテルの「Super Dream Project」は、単なる一企業のユニークな採用事例に留まらず、ホテル業界全体の総務人事部が持続可能な人材戦略を構築する上で、多くの示唆に富んでいます。
「人材」を「人財」として捉える視点
このプロジェクトの最も重要な本質は、従業員を単なる「人材(労働力)」としてではなく、「人財(企業の資産、未来を創る存在)」として捉える視点です。短期的な労働力の確保に終始するのではなく、彼らの成長と夢の実現を支援することで、長期的に企業価値を高めるという思想が根底にあります。
総務人事部は、採用活動において、候補者のスキルや経験だけでなく、その「潜在能力」や「成長意欲」、そして「人生における目標」にまで目を向ける必要があります。そして、入社後も、従業員一人ひとりが自身のキャリアを主体的にデザインできるよう、多様な選択肢と成長機会を提供することが求められます。これは、従業員が企業に貢献するだけでなく、企業も従業員の人生に貢献するという、相互扶助の関係性を築くことに繋がります。
キャリアパスの「見える化」と「意味付け」
前述の通り、この制度は契約期間満了後のキャリアパスが明確に提示されており、それが高い定着率に貢献しています。総務人事部は、スーパーホテルの事例から、従業員が自身の将来像を描けるよう、キャリアパスを具体的に「見える化」することの重要性を学ぶべきです。
例えば、一般社員からマネージャー、そして支配人へと昇進する明確なルートを示すだけでなく、専門職としてのキャリアパス(例:マーケティング専門職、収益管理専門職)や、他部署への異動、あるいはグループ内での独立支援制度など、多様な選択肢を提示することが有効です。また、日々の業務がどのような形で自身の成長やキャリアに繋がるのかを具体的に説明し、「意味付け」を行うことも不可欠です。これにより、従業員は目の前の業務に高いモチベーションで取り組むことができます。
これは、まさに「ホテル総務人事の変革戦略:採用・育成・定着で拓くホスピタリティの未来」(https://hotelx.tech/?p=2237)で提唱されているような、戦略的な人材マネジメントの一環と言えるでしょう。
画一的な研修ではなく、自律性を尊重した育成
スーパーホテルの育成モデルは、座学研修と実地研修の組み合わせに加え、現場での大きな裁量と責任を与えることで、従業員の自律的な成長を促します。これは、画一的な研修プログラムに終始するのではなく、個々の従業員の能力や意欲に応じた、よりパーソナライズされた育成アプローチの重要性を示唆しています。
総務人事部は、従業員が自ら課題を発見し、解決策を考え、実行する機会を積極的に提供すべきです。メンター制度の導入、クロスファンクショナルなプロジェクトへの参加、外部研修への派遣など、多様な学びの機会を設計することが求められます。そして、最も重要なのは、「失敗を許容する文化」を醸成することです。従業員が安心して挑戦し、そこから学びを得られる環境があってこそ、真の自律的な成長が実現します。
テクノロジー活用とのバランス
本稿ではスーパーホテルのユニークな制度に焦点を当てましたが、現代のホテル運営においてテクノロジーの活用は不可欠です。しかし、スーパーホテルの事例は、「人」が中心となるホスピタリティ産業において、テクノロジーはあくまで「人の力を最大限に引き出すためのツール」であるべきという、重要なメッセージを投げかけています。
例えば、ホテル運営におけるルーティン業務やデータ分析をAIやIoTに任せることで、支配人・副支配人夫婦は、よりお客様とのコミュニケーションや、サービス品質の向上といった、人間にしかできない業務に集中することができます。総務人事部は、テクノロジーを導入する際にも、それが従業員の業務負荷を軽減し、彼らがより創造的で価値の高い仕事に時間を費やせるようになるか、という視点を持つべきです。テクノロジーと人の役割を適切にバランスさせることで、従業員の満足度と生産性の双方を高めることが可能になります。
まとめ
2025年、ホテル業界の総務人事部が直面する人材確保と定着の課題は、従来の常識にとらわれない革新的なアプローチを求めています。スーパーホテルの「Super Dream Project」は、その一つの成功事例として、私たちに多くの学びを提供してくれました。
この制度の本質は、従業員を単なる労働力としてではなく、「ビジネスオーナーとしての成長を支援するビジネスパートナー」として位置づけている点にあります。明確なキャリアパス、成果に連動する報酬体系、そして自律性を尊重した育成モデルは、高いモチベーションとエンゲージメントを生み出し、結果として離職率の低減と持続的な組織成長に繋がっています。
総務人事部は、この事例から、採用活動において「働く意味」と「生き方」を提案する視点、キャリアパスを具体的に「見える化」し「意味付け」することの重要性、そして画一的ではない自律的な成長を促す育成プログラムの設計を学ぶべきです。また、テクノロジーを適切に活用し、従業員がより価値の高い業務に集中できる環境を整備することも不可欠です。
ホテル業界の未来は、いかに「人」を「人財」として育成し、定着させるかにかかっています。スーパーホテルの事例は、そのための具体的な道筋と、総務人事部が果たすべき戦略的な役割を明確に示していると言えるでしょう。

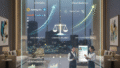

コメント