はじめに:ホテル朝食が迎える大きな転換点
旅行の楽しみは数多くありますが、その中でも「ホテルの朝食」を重視する人は少なくありません。宿泊予約サイトの口コミでも、朝食の評価がホテル全体の印象を大きく左右する光景は日常茶飯事です。かつてホテルの朝食といえば、好きなものを好きなだけ楽しめる「バイキング(ビュッフェ)形式」が主流でした。しかし、その常識が今、静かに、しかし確実に変わりつつあります。
きっかけは、SNSの浸透と社会的な価値観の変化です。特にInstagramなどのビジュアル重視のプラットフォームでは、「#ホテル朝食」といったハッシュタグが人気を集め、宿泊体験の一部として積極的に共有されるようになりました。そんな中、明治大学の研究グループが発表した「ホテル朝食は『バイキングより定食が映える』」という研究結果は、業界に大きな示唆を与えています。この記事では、この研究結果を糸口に、なぜ今「映える定食」が注目されるのか、そしてそれがホテルのビジネスやマーケティングにどのような変革をもたらすのかを深掘りしていきます。これは単なる食事スタイルの話ではなく、顧客体験、経営効率、そしてブランド戦略の未来を占う重要なテーマです。
長年のスタンダード「バイキング形式」の功罪
ホテルの朝食バイキングは、長年にわたり多くの宿泊客に愛されてきました。その理由は明確です。和食、洋食、サラダ、フルーツ、デザートまで、多彩なメニューがずらりと並び、宿泊客は自分の好みやその日の気分に合わせて自由に組み合わせることができます。この「選択の自由」と「満腹感」は、特にレジャー客やファミリー層にとって大きな魅力でした。
ホテル側にとっても、バイキング形式にはメリットがありました。ピークタイムに合わせて大量に調理しておくことで、個別のオーダーに対応するよりも効率的にサービスを提供できる面があったのです。
しかし、その裏側で深刻な問題も抱えていました。最大の課題は「フードロス」です。農林水産省の調査によれば、日本の食品ロス量は年間523万トン(令和3年度推計値)にのぼり、その中には外食産業からの廃棄も多く含まれます。バイキングでは、客の食べ残しはもちろん、見栄えを保つために常に料理を補充し続ける必要があり、結果として手つかずのまま廃棄される料理が大量に発生します。これは食材コストの増大に直結するだけでなく、環境負荷の観点からも持続可能なモデルとは言えません。
さらに、マーケティングの観点からも弱点を露呈し始めています。どのホテルも似たようなメニュー構成になりがちで、「朝食」で他施設との差別化を図ることが難しくなっています。そしてSNS時代において決定的ともいえるのが、「映え」の問題です。宿泊客自身が料理を皿に盛り付けるため、ホテル側が意図した美しいビジュアルで写真に撮ってもらうことが極めて困難なのです。結果として、せっかくの食事がSNS上で魅力的に伝わらず、プロモーションの機会を逃しているケースが少なくありません。
「映える定食」がもたらす戦略的メリット
バイキング形式が抱える課題を解決する一手として注目されるのが、「定食(セットメニュー)形式」への転換です。特に、見た目の美しさを追求した「映える定食」は、ホテル経営に3つの大きなメリットをもたらします。
メリット1:圧倒的なSNS訴求力によるマーケティング効果
定食形式の最大の強みは、ホテル側が料理のビジュアルを完全にコントロールできる点にあります。旬の食材を使い、彩り豊かに、計算された器に盛り付けられた朝食は、それ自体がアート作品のようになります。宿泊客は、テーブルに運ばれてきた完成された一皿を、ただスマートフォンで撮影するだけ。誰が撮っても「映える」写真が撮れるのです。
こうして撮影された写真は、「#〇〇ホテルでの朝食」「#贅沢モーニング」といったハッシュタグと共にSNSで拡散されます。これは、ホテルが費用をかけずに行える最高の宣伝活動です。さらに、地域の特産品を使った「おばんざい御膳」や、ホテルのコンセプトを反映した「ウェルネスプレート」など、ストーリー性のあるメニューを提供することで、単なる食事ではなく「そこでしかできない体験」として顧客の記憶に深く刻み込まれ、強力なブランドイメージを構築します。
メリット2:フードロス削減と経営効率の向上
定食形式は、フードロス問題に対する極めて有効な解決策です。提供する人数分の食材だけを用意するため、過剰な調理や廃棄を劇的に減らすことができます。これは、SDGs(持続可能な開発目標)の目標12「つくる責任 つかう責任」に直接的に貢献する取り組みであり、環境意識の高い顧客層への強力なアピールとなります。
経営面では、食材の仕入れ量を正確に予測できるため、原価管理が容易になり、収益性の改善に繋がります。バイキング形式で発生していた見えないコスト(廃棄コスト、過剰な人件費)を削減し、その分を食材の質の向上や、他のサービスに再投資することも可能になるのです。
メリット3:パーソナライズされた顧客体験(CX)の向上
バイキングの喧騒から離れ、着席したままサービスを受けられる定食形式は、顧客に落ち着いた上質な時間を提供します。「自分のために特別に用意された食事」という感覚は、顧客満足度を大きく高めます。料理が運ばれてくる際には、スタッフが食材の産地や調理法のこだわりを説明することもでき、コミュニケーションの機会が生まれます。
また、事前にアレルギーや食事制限の有無を確認し、個別に対応したメニューを提供することも比較的容易です。このようなパーソナライズされた「おもてなし」は、顧客ロイヤルティを高め、リピート利用へと繋がる重要な要素となります。
テクノロジーは「魅せる朝食」をどう進化させるか
「映える定食」への転換は、単に提供スタイルを変えるだけではありません。最新のテクノロジーを活用することで、その効果を最大化し、より洗練されたサービスへと進化させることができます。
1. 予約システムとの連携による事前オーダー
宿泊予約時に、公式サイトや予約アプリ上で朝食のメニュー(例:和食御膳/アメリカンブレックファスト)を事前に選択してもらう仕組みを導入します。これにより、ホテルは正確な需要予測に基づいた食材発注と仕込みが可能になり、フードロスを限りなくゼロに近づけることができます。アレルギー情報もこの段階で収集できるため、当日の対応もスムーズです。
2. CRM/顧客データ活用によるパーソナライゼーション
CRM(顧客関係管理)システムに蓄積された顧客データを活用し、リピーター客に対して前回とは異なるメニューを提案したり、誕生日などの記念日には特別な一品を追加したりといった、パーソナライズされたサービスを提供します。顧客は「自分のことを覚えてくれている」という特別感を感じ、ホテルへの愛着を深めるでしょう。
3. SNSマーケティングツールの活用
顧客が投稿した朝食の写真を自動で収集・分析するツールを活用し、どのメニューが人気か、どのような写真が「いいね」を集めやすいかをデータで把握します。この分析結果を基に、メニュー開発や盛り付けの改善に活かすことができます。また、優れた写真を投稿した顧客に特典を提供するなど、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を促進するキャンペーンも効果的です。
4. テーブルオーダーシステムの導入
メインの定食に加え、ドリンクのおかわりや追加のサイドメニューなどを、各テーブルに設置されたタブレットから注文できるシステムを導入します。これにより、顧客はスタッフを呼ぶ手間なく気軽に注文でき、ホテル側は客単価の向上(アップセル)と省人化を同時に実現できます。
まとめ:朝食から始めるホテルブランディングの新時代
SNS時代の到来とSDGsへの関心の高まりは、ホテル業界における「朝食」の価値を根底から変えようとしています。かつての「量と種類の豊富さ」を誇るバイキングから、一皿一皿に物語と美学を込めた「質と体験」の定食へ。このシフトは、単なるトレンドではなく、これからのホテルが生き残るための重要な経営戦略です。
「映える定食」は、フードロスという社会課題の解決に貢献しながら、SNSを通じてホテルの魅力を拡散し、最終的には顧客満足度とブランド価値を高めるという、まさに「三方良し」の施策と言えます。もちろん、すべてのホテルが明日からバイキングを廃止すべきだというわけではありません。施設の規模やターゲット顧客、ブランドコンセプトに応じて、バイキングと定食の長所を組み合わせたハイブリッド形式や、特定のメニューだけを強化したセミビュッフェなども有効な選択肢でしょう。
重要なのは、自社のホテルが提供すべき「最高の朝食体験」とは何かを再定義し、それを実現するための最適な方法を、テクノロジーも活用しながら模索し続ける姿勢です。朝食という日常的なサービスの中にこそ、ホテルの未来を切り拓く大きなヒントが隠されています。

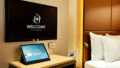

コメント