好景気の今こそ考えるべき、ホテルの「高単価戦略」とは
昨今、インバウンド需要の回復に牽引され、日本のホテル業界は活況を呈しています。東京商工リサーチが発表した上場ビジネス・シティホテルの調査によれば、多くのホテルで客室単価(ADR)と稼働率(OCC)が上昇し、それに伴いRevPAR(販売可能な客室1室あたりの収益)も高い水準で推移しています。このニュースは業界にとって喜ばしい限りですが、私たちはこの好機を単なる「売上回復」で終わらせてはなりません。
人件費や光熱費、原材料費といった運営コストの高騰が続く中、稼働率の追求だけに依存した経営モデルは、いずれ限界を迎えます。現場の疲弊を招き、サービスの質の低下につながるリスクも否定できません。今こそ、目先の稼働率に一喜一憂するのではなく、持続的な成長と高い収益性を実現するための「高単価戦略」、すなわち「高付加価値戦略」へと舵を切るべき重要な局面にあると言えるでしょう。本記事では、なぜ今、客室単価の向上が重要なのか、そしてそれを実現するための具体的な戦略について深掘りしていきます。
なぜ「稼働率」より「客室単価」が重要なのか?
ホテルの収益性を測る最も重要な指標の一つがRevPARです。これは「RevPAR = 客室単価(ADR) × 稼働率(OCC)」という式で表されます。多くのホテルが稼働率を上げることに注力しがちですが、稼働率には100%という物理的な上限が存在します。一方で、客室単価には理論上の上限はありません。提供する価値を高めることができれば、価格もそれに伴って引き上げることが可能です。
コスト上昇が続く現代において、利益を確保するためには価格転嫁が不可欠です。しかし、単に値上げをするだけでは顧客離れを招きかねません。顧客が「この価格を支払う価値がある」と心から納得できるだけの付加価値を提供すること。これが、高単価戦略の本質です。
また、高単価戦略はブランド価値の向上にも直結します。安売り競争から脱却し、価格に見合った、あるいはそれ以上の体験を提供することで、顧客満足度は飛躍的に高まります。満足した顧客はロイヤルティの高いリピーターとなり、安定した収益基盤を築いてくれるのです。さらに、少ないゲストで高い収益を上げるビジネスモデルは、スタッフの負担を軽減し、より質の高いサービス提供を可能にします。これは、近年問題視されているオーバーツーリズムに対する一つの解決策にもなり得ます。
高単価を実現する「高付加価値戦略」の柱
では、具体的にどのようにして付加価値を高め、客室単価の向上につなげていけばよいのでしょうか。ここでは、テクノロジーの活用を前提とした4つの戦略的アプローチをご紹介します。
1. 究極のパーソナライゼーション
「自分だけのために用意されたおもてなし」は、顧客に最も強い感動を与える要素の一つです。これを実現するためには、顧客データの活用が欠かせません。PMS(ホテル管理システム)やCRM(顧客関係管理システム)に蓄積された過去の宿泊履歴、予約時のリクエスト、問い合わせ内容などを統合・分析することで、顧客一人ひとりの嗜好を深く理解することができます。
例えば、以下のようなアプローチが考えられます。
- 事前準備の徹底: 以前の滞在で利用したアメニティや好みの枕を事前に客室に用意しておく。寒がりの顧客であれば、チェックイン前に少し室温を上げておく。
- パーソナライズされたコミュニケーション: 記念日での宿泊と分かれば、AIチャットボットを通じてサプライズの提案をしたり、客室タブレットに合わせたメッセージを表示したりする。
- 個別のレコメンデーション: 顧客の興味関心に合わせて、館内施設や周辺のアクティビティを提案する。アート好きの顧客には近隣の美術館の企画展情報を、美食家の顧客には隠れた名店の予約サポートを提供するなど、画一的ではない情報提供が価値を生みます。
こうしたきめ細やかな対応は、顧客に「大切にされている」という実感を与え、価格以上の満足感につながります。
2. 「そこでしかできない」体験コンテンツの造成
宿泊を「寝る場所」から「特別な体験をする場所」へと昇華させることも、高付加価値戦略の重要な柱です。ホテルが持つ独自の資源や、立地する地域の文化を最大限に活用し、ユニークな体験コンテンツを企画・提供します。
- 文化体験: 地元の職人を招いた伝統工芸のワークショップ、ホテルシェフによる郷土料理教室、酒蔵と連携した日本酒のテイスティングイベントなど。
- ウェルネスプログラム: 眺めの良い場所での朝ヨガ、専門家によるメディテーション(瞑想)セッション、パーソナルトレーナー付きのフィットネスプログラムなど、心身の健康に焦点を当てた体験。
- 知的好奇心を刺激する企画: 歴史家を招いた地域の歴史散策ツアー、天体観測イベント、著名なアーティストによるミニコンサートなど。
これらの体験は、宿泊プランに組み込んでパッケージ料金を高めに設定したり、魅力的な有料オプションとして提供したりすることで、客単価(宿泊以外の収益を含む)を大きく向上させることができます。
3. DXを活用したアップセル・クロスセルの高度化
アップセル(より高価格な商品への誘導)とクロスセル(関連商品の合わせ買い推奨)は、客単価向上のための古典的な手法ですが、テクノロジーの活用でその効果を最大化できます。
重要なのは「タイミング」と「提案内容の最適化」です。予約が完了した直後からチェックインまでの期間は、顧客の旅行への期待感が最も高まっているゴールデンタイムです。この時期に、メールや専用アプリを通じて、「眺望の良い角部屋へのアップグレードはいかがですか?」「ご到着に合わせ、シャンパンをお部屋にご用意します」といった魅力的な提案を自動で行います。
ここでもAIが活躍します。顧客の属性や過去の行動データに基づき、AIが「この顧客には、スパの割引よりもレイトチェックアウトの方が響くだろう」と判断し、パーソナライズされた提案を自動生成します。強引な押し売りではなく、顧客が「ちょうど欲しかった」と感じるようなスマートな提案が、自然な形で単価向上へと導きます。
4. データドリブンなダイナミックプライシング
需要と供給に応じて価格を変動させるダイナミックプライシングは、もはやホテル業界の常識です。しかし、その精度をどこまで高められるかが、収益を大きく左右します。
最新のRMS(レベニューマネジメントシステム)は、自社の予約状況や過去の実績だけでなく、競合ホテルの価格変動、航空券の予約状況、地域のイベント情報、天候予報、さらにはSNSでの言及数といった膨大な外部データを取り込み、AIが分析します。これにより、「3週間後に開催されるコンサートの影響で、特定の日程の需要が急増する」といった兆候をいち早く察知し、機会損失を最小限に抑えながら収益を最大化する最適な価格をリアルタイムで算出することが可能になります。
これは単なる値上げではなく、需要に基づいた「適正価格」への最適化です。需要が低い時期には価格を抑えて集客を促し、高い時期にはしっかりと収益を確保する。このメリハリの効いた価格戦略こそが、年間の収益性を高める鍵となります。
まとめ:価値創造こそが、未来を拓く
ホテル業界を取り巻く環境は、インバウンド需要という追い風が吹く一方で、コスト高騰や人手不足といった厳しい向かい風にも晒されています。このような時代において、かつてのような薄利多売の稼働率競争に未来はありません。
今、ホテル経営者に求められるのは、自社の提供価値を徹底的に見つめ直し、それを最大化するための戦略を描くことです。パーソナライゼーション、体験コンテンツ、スマートなアップセル、データに基づいた価格戦略。これらの高付加価値戦略を推進する上で、テクノロジーの活用はもはや避けて通れない必須要素となっています。
現在の好景気を、単なる短期的な回復で終わらせるのではなく、ビジネスモデルそのものを変革する絶好の機会と捉えること。そして、価格に見合う、あるいはそれを超える価値を創造し続けること。それこそが、不確実な未来を乗り越え、持続的に成長していくための唯一の道筋と言えるでしょう。

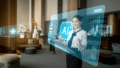

コメント