はじめに
2025年現在、ホテル業界はかつてないほどの変化と挑戦に直面しています。インバウンド需要の回復、多様化するゲストのニーズ、そして慢性的な人手不足。こうした状況下で、ホテル運営の現場では、ゲストとの間に生じる「認識のギャップ」が新たな課題として浮上しています。特に、スタッフが「宿泊時にやってほしくない行為」としてSNSで発信するケースが増え、これが大きな話題を呼んでいます。今回は、ECナビのニュース記事「【ホテル】スタッフが教える“宿泊時にやってほしくない行為”にSNS悲鳴「本当にやめてほしい」」を基に、この認識ギャップが現場にもたらす具体的な影響と、ホテルが取るべきコミュニケーション戦略について深く掘り下げていきます。
現場が直面する「やってほしくない行為」とその影響
ECナビの記事で取り上げられた内容は、多くのホテル現場で日常的に発生している問題の氷山の一角を示しています。具体的には、「コインランドリーに洗濯物を放置する」「アメニティを過剰に持ち帰る」「清掃不要札を無視して清掃を依頼する」といった行為が挙げられています。これらは一見些細なことに思えるかもしれませんが、現場のスタッフにとっては大きな負担となり、ホテル運営全体に深刻な影響を与えます。
コインランドリーの放置
共有スペースであるコインランドリーでの洗濯物放置は、次の利用者の迷惑になるだけでなく、ホテルの管理業務を煩雑にします。放置された洗濯物を移動させるのは、清掃スタッフやフロントスタッフの追加業務です。特に、多忙な時間帯に発生すると、他の業務に支障をきたし、結果としてゲストへのサービス提供が遅れる原因にもなります。また、放置された衣類に関するクレーム対応も、スタッフの心理的負担を増大させます。
アメニティの過剰持ち帰り
歯ブラシやカミソリといった使い捨てアメニティは、ゲストの快適な滞在のために用意されています。しかし、これらを必要以上に持ち帰る行為は、ホテルの備品コストを押し上げます。特に、環境配慮の観点からアメニティの見直しが進む中で、過剰な持ち帰りはサステナビリティへの取り組みを阻害する要因ともなりかねません。現場では、補充の頻度や量の調整に苦慮し、場合によっては在庫不足を招くこともあります。
清掃不要札の無視と清掃依頼
「清掃不要」の意思表示をしているにもかかわらず、後から清掃を依頼するケースも現場を困惑させます。清掃スケジュールは効率的に組まれており、急な依頼は他の客室の清掃遅延やスタッフの労働時間延長に直結します。清掃スタッフは限られた時間で多くの客室を担当しており、予期せぬ対応は作業計画を大きく狂わせます。これは、次のゲストのチェックイン時間にも影響を及ぼし、結果として全体的なゲスト満足度の低下につながる可能性があります。
これらの行為は、単に「迷惑」という感情的な問題に留まらず、次のゲストへのサービス品質の低下、運営コストの増加、スタッフの士気低下、備品管理の煩雑化といった連鎖的な悪影響を引き起こします。ホテルは、単に宿泊施設を提供するだけでなく、快適な体験と円滑な運営を両立させるために、こうした課題に真摯に向き合う必要があります。
ゲストとの認識ギャップの深層
なぜゲストは、ホテルスタッフが「やってほしくない」と考える行為をしてしまうのでしょうか。その背景には、ホテル側とゲスト側の間に存在する深い「認識のギャップ」があります。このギャップを理解することが、問題解決の第一歩となります。
「これくらいなら大丈夫だろう」という軽い気持ち
多くのゲストは、悪意を持って行動しているわけではありません。「コインランドリーは後で誰かが片付けてくれるだろう」「アメニティはたくさんあるから少し多めに貰っても問題ないだろう」といった、ホテル運営の実態に対する無理解や、「これくらいなら許されるだろう」という軽い気持ちが、問題行動につながることが少なくありません。ホテルは「サービス」を提供する場であるという認識から、ゲストは「多少の無理は聞いてもらえる」と考えがちです。
ホテルの運営コストや現場の労働実態への無理解
ゲストは、ホテルの客室料金やサービス料を支払っているため、その対価として「最大限のサービス」を受ける権利があると感じることがあります。しかし、そのサービスがどのように提供され、どれだけのコストや労働力がかかっているかを知る機会はほとんどありません。例えば、アメニティの過剰持ち帰りが環境負荷やコストに直結すること、急な清掃依頼が清掃スタッフの過酷な労働環境に拍車をかけることなどは、ゲストの想像の範囲外であることがほとんどです。
ゲスト行動が招く「見えない損失」:ホスピタリティ再定義と持続可能な運営でも触れたように、ゲストの行動がホテルに与える「見えない損失」は決して小さくありません。
情報伝達の不足
ホテルのルールやマナーが、ゲストに明確に伝わっていないことも大きな要因です。チェックイン時の口頭説明は聞き流されやすく、客室内の案内も隅々まで読まれるとは限りません。特に、多言語対応が不十分な場合や、デジタルネイティブ世代のゲストに対して紙の案内だけでは情報が届きにくいこともあります。情報が適切に伝わらないことで、ゲストは「知らなかった」という認識で、ホテル側が望まない行動をしてしまうのです。
ホテルが提供する「おもてなし」は、ゲストにとって「自由」や「快適さ」として受け取られることが多いですが、その「自由」が過度になると、現場に負担をかけ、結果的に他のゲストやホテル全体のサービス品質に影響を及ぼすことになります。このギャップを埋めるためには、ホテル側からの一方的な「禁止」ではなく、ゲストに共感と理解を促すための、より戦略的なコミュニケーションが不可欠です。
ホテルが取り組むべきコミュニケーション戦略
現場スタッフが抱える「やってほしくない行為」の課題を解決するためには、単に「やめてください」と伝えるだけでは不十分です。ゲストにホテルの運営実態やスタッフの努力を理解してもらい、共感と協力を促すための、より洗練されたコミュニケーション戦略が求められます。
情報提供の明確化と多角化
まず、ホテルのルールやマナーに関する情報を、ゲストに明確かつ多角的に提供することが重要です。
- チェックイン時の説明強化: 口頭での説明に加え、重要なポイントを記載したカードやQRコードを渡し、客室で詳細を確認できるようにする。
- 客室内の案内改善: 従来の紙媒体だけでなく、客室タブレットやデジタルサイネージを活用し、動画やイラストを交えて分かりやすく説明する。特に、環境への配慮やスタッフの負担軽減といった「なぜそうしてほしいのか」という理由を伝えることが効果的です。
- ウェブサイト・予約サイトでの事前情報提供: 予約段階で、ホテルのポリシーやマナーに関する情報を掲載し、ゲストが事前に確認できるようにする。
ポジティブなメッセージング
禁止事項として羅列するのではなく、ゲストへの感謝と協力を促すポジティブなメッセージで伝える工夫が必要です。「~しないでください」ではなく、「~していただけると助かります」「ご協力ありがとうございます」といった表現を用いることで、ゲストは「ホテルに貢献している」という意識を持ちやすくなります。例えば、アメニティの持ち帰りについては、「環境保護のため、必要な分だけお持ち帰りください。ご協力に感謝いたします」といったメッセージが考えられます。
SNSを活用した啓発活動
今回のように、ホテルスタッフがSNS(特にTikTokなど)で現場のリアルな声を共有することは、ゲストとの距離を縮め、共感を呼ぶ上で非常に有効です。ただし、単なる不満の表明ではなく、ユーモアを交えたり、具体的な影響を分かりやすく伝えたりする工夫が必要です。例えば、「コインランドリーは次のゲストも気持ちよく使えるよう、ご利用後は速やかに回収をお願いします!」といった形で、ポジティブな行動を促すコンテンツを発信できます。
ホテルが直面するゲストとの「認識ギャップ」:TikTokが創る「共感」と「共生戦略」でも述べたように、SNSは単なる集客ツールではなく、ホテルとゲストの間に「共感」と「共生」を生み出す強力なプラットフォームとなり得ます。
スタッフへの教育と権限委譲
現場スタッフが、ゲストに直接、かつ丁寧に、状況を説明できるようなトレーニングも不可欠です。問題が発生した際に、スタッフが自信を持ってゲストに働きかけられるよう、対応マニュアルの整備やロールプレイング研修を行うべきです。また、柔軟な対応ができるよう、一定の権限を委譲することも重要です。例えば、コインランドリーの放置物に対しては、ホテル側で一時的に保管するなどの対応ルールを明確にし、スタッフが迷うことなく行動できるようにします。
これらのコミュニケーション戦略は、単にホテルの負担を減らすだけでなく、ゲストにホテルの「想い」や「価値観」を伝え、より深い信頼関係を築くことにもつながります。ホテルとゲストが互いを尊重し、協力し合うことで、より快適で持続可能なホスピタリティが実現できるのです。
持続可能なホスピタリティの追求
ホテルスタッフがSNSで発信した「やってほしくない行為」は、ホテル業界が直面する多層的な課題の一端を浮き彫りにしています。これは単なる「マナー違反」の問題ではなく、ホテルの運営効率、コスト管理、スタッフの労働環境、そして何よりもゲスト体験の質に直接関わる重要なテーマです。
現代のホテルは、単に宿泊を提供するだけでなく、地域社会との共生、環境への配慮、従業員のエンゲージメント向上といった多角的な視点から、持続可能な運営モデルを構築していく必要があります。ゲストとの間に生じる認識ギャップを解消し、互いに協力し合う関係を築くことは、この持続可能なホスピタリティを実現する上で不可欠な要素です。
ホテル側が一方的にルールを押し付けるのではなく、「なぜそのルールが必要なのか」「ゲストの協力がどのようにホテルや他のゲスト、そして地球環境に良い影響を与えるのか」を具体的に伝え、共感を呼び起こすことが重要です。これにより、ゲストは単なる「宿泊客」ではなく、ホテルの価値創造に「参加」するパートナーへと意識を変えていくでしょう。
現場スタッフのリアルな声に耳を傾け、それを改善に繋げるためのコミュニケーション戦略を練ることは、ホテルが未来に向けて成長していくための重要な投資です。テクノロジーの活用も有効ですが、最終的には「人」と「人」との間に信頼と理解を築くことが、真のホスピタリティを追求する上で最も重要な要素となります。
まとめ
ホテルスタッフがSNSで発信した「宿泊時にやってほしくない行為」は、ホテル運営の現場が抱える泥臭い課題と、ゲストとの間に存在する認識ギャップを浮き彫りにしました。コインランドリーの放置、アメニティの過剰持ち帰り、清掃不要札の無視といった行為は、一見些細でも、現場の負担を増大させ、次のゲストへのサービス品質を低下させる原因となります。
この課題を乗り越えるためには、ホテル側からの明確で多角的な情報提供、ポジティブなメッセージング、そしてSNSを活用した共感を生むコミュニケーションが不可欠です。ゲストに「なぜその協力が必要なのか」を伝え、共に快適な滞在空間を創り出す「共生」の意識を育むことが、持続可能なホスピタリティを実現する鍵となります。
ホテルとゲストが互いを尊重し、理解し合うことで、より質の高いサービスが提供され、結果としてホテル業界全体の価値向上に繋がるでしょう。2025年、ホテルは単なる宿泊施設ではなく、ゲストと共に未来を創るパートナーシップの場へと進化を続けています。


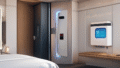
コメント