「敵は隣のホテル」という常識の終わり
ホテル業界と聞けば、多くの人が熾烈な価格競争や顧客獲得競争を思い浮かべるでしょう。隣接するホテルはライバルであり、その一挙手一投足に気を配り、いかにして差別化を図り、自社を選んでもらうか。それが、これまでのホテル経営における「常識」でした。しかし、その常識が今、静かに、しかし確実に変わりつつあります。その象徴的な動きが、本来であれば競合関係にあるホテル同士が手を取り合う「ホテル間連携」です。
最近、非常に興味深いプレスリリースが発表されました。広島市内の5つのホテルが、共通価格のランチとスタンプラリーを共同で実施するという取り組みです。
参考:【リーガロイヤルホテル広島】広島市内5ホテルで共通価格のランチとスタンプラリーを実施OK!!広島(おいしいけぇ、ひろしま)×味めぐり』
参加するのは、リーガロイヤルホテル広島、ANAクラウンプラザホテル広島、グランドプリンスホテル広島、シェラトングランドホテル広島、ホテルグランヴィア広島。いずれも広島を代表する名門ホテルです。個々が強力なブランド力と集客力を持つこれらのホテルが、なぜあえて手を組むのでしょうか。この動きは、単なる一過性のイベントではありません。これからのホテル業界が直面する大きな課題と、その解決策を示唆する重要なトレンドなのです。本記事では、この広島の事例を切り口に、「競合連携」がなぜ今求められるのか、そのメリットと乗り越えるべき課題、そして成功の鍵について深く考察していきます。
なぜ今、「競合」が手を組むのか?
熾烈な競争を繰り広げてきたホテル同士が連携する背景には、個々のホテルの努力だけでは解決が難しい、業界全体を取り巻く構造的な課題が存在します。
1. 「パイの奪い合い」から「パイの創造」へ
従来のホテル経営は、特定のエリアや特定の顧客層という限られた「パイ」を、競合ホテルといかに奪い合うかというゼロサムゲームの側面が強いものでした。しかし、OTA(Online Travel Agent)への手数料の高騰や、過度な価格競争による収益性の悪化は、多くのホテルを疲弊させています。個々のホテルが消耗戦を繰り広げるのではなく、連携して地域全体の魅力を高めることで、観光客の総数を増やす、つまり「パイそのものを大きくする」という発想への転換が求められています。
広島の事例は、まさにこの発想の転換を体現しています。スタンプラリーという形で複数のホテルを周遊させることで、観光客は「広島に滞在する楽しみ」をより多角的に体験できます。これは、単に1つのホテルに宿泊する以上の付加価値を生み出し、「また広島に来たい」「次は別のホテルにも泊まってみたい」というリピート需要や、新たな観光需要を掘り起こす可能性を秘めているのです。
2. 顧客体験価値の向上と多様化するニーズへの対応
現代の旅行者は、単に宿泊する場所を求めているわけではありません。その土地ならではのユニークな「体験」を求めています。しかし、1つのホテルが提供できる体験には限界があります。例えば、Aホテルは絶景のバーが自慢、Bホテルは歴史ある庭園が魅力、Cホテルは地元食材を活かしたレストランが人気、といった具合に、各ホテルには独自の強みがあります。
ホテル間が連携し、互いの強みを活かした共同プランや周遊パスのようなものを提供できれば、ゲストは滞在中に複数のホテルの魅力を「はしご」することが可能になります。これは、ゲストにとって選択肢が増え、滞在全体の満足度を飛躍的に向上させることに繋がります。まさに、「体験」が収益を生む時代において、極めて有効な戦略と言えるでしょう。
3. 業界共通の課題への共同対処
人手不足、オーバーツーリズム、サステナビリティへの対応など、ホテル業界は多くの共通課題を抱えています。これらの課題は、一施設の努力だけでは解決が困難です。例えば、人材育成において、複数のホテルが合同で研修プログラムを実施すれば、より質の高い教育を効率的に行うことができます。また、オーバーツーリズム対策として、観光客が特定のホテルやエリアに集中しないよう、連携して周遊を促すような情報発信やプランニングを行うことも可能です。このように、競合という垣根を越えて協力することで、業界全体の持続可能性を高めることができるのです。
ホテル間連携のメリットと乗り越えるべき「壁」
競合連携は多くの可能性を秘めていますが、その実現は決して簡単ではありません。ここでは、具体的なメリットと、避けては通れない課題を整理します。
連携がもたらす4つのメリット
1. マーケティング効果の最大化: 共同でプロモーション活動を行うことで、単独ではリーチできなかった顧客層にアプローチできます。広告費や販促コストを分担できるため、一施設あたりの負担を軽減しつつ、より大きなインパクトを生み出すことが可能です。
2. 新たな商品・サービスの開発: 各ホテルの強み(例:Aホテルのスパ、Bホテルのレストラン)を組み合わせた、これまでにない宿泊プランや体験コンテンツを創造できます。これは、価格競争からの脱却に繋がる高付加価値化の鍵となります。
3. ノウハウの共有と人材育成: 定期的な情報交換会や合同研修を通じて、各ホテルが持つオペレーションのノウハウや成功事例を共有できます。これは、組織全体のサービスレベル向上や、スタッフのモチベーションアップに大きく貢献します。
4. 地域への貢献とブランドイメージ向上: ホテル群が一体となって地域活性化に取り組む姿勢は、地域社会からの信頼を得るとともに、「地域と共生するホテル」としてポジティブなブランドイメージを構築します。これは、DMO(Destination Management Organization)との連携にも繋がり、より大きなムーブメントを生み出すきっかけにもなります。
乗り越えるべき3つの「壁」
1. 利害関係の調整: 最も大きな壁が、各ホテルの利害調整です。ホテルの規模、ブランド、ターゲット顧客、経営方針が異なれば、目指す方向性や優先順位も当然異なります。共同事業のコスト負担や利益配分を巡って、合意形成が難航するケースは少なくありません。
2. 情報共有のジレンマ: 連携を深めるには、ある程度の情報開示が必要です。しかし、稼働率や顧客データといった機密情報を競合相手にどこまで開示するかは、非常にデリケートな問題です。相互の信頼関係がなければ、連携は表面的なものに留まってしまいます。
3. 意思決定プロセスの複雑化: 参加するホテルが増えれば増えるほど、意思決定のスピードは遅くなる傾向があります。市場の変化に迅速に対応するためには、誰が最終的な決定権を持つのか、どのようなプロセスで合意を形成するのか、あらかじめ明確なルール作りが不可欠です。
競合連携を成功に導く3つの鍵
では、これらの壁を乗り越え、連携を成功させるためには何が必要なのでしょうか。
1. 「共通の敵」と「共通の目標」を明確にする
連携を成功させる第一歩は、「我々の敵は隣のホテルではない」という共通認識を持つことです。真の競合は、他の観光地であり、旅行者の可処分時間を奪う他のレジャー産業かもしれません。その上で、「地域の観光消費額を5年で10%増加させる」といった、具体的で測定可能な共通目標(KGI/KPI)を設定することが重要です。「地域活性化」のような漠然としたスローガンだけでは、各ホテルの足並みは揃いません。
2. 強力なファシリテーターと事務局機能
異なる意見や利害を調整し、プロジェクトを前進させるためには、中立的な立場のファシリテーターや、実務を担う事務局の存在が不可欠です。地域の観光協会やDMOがその役割を担うことも有効でしょう。参加ホテルから少し距離を置いた客観的な視点から、全体の最適解を模索し、議論をリードする役割が求められます。
3. スモールスタートと成功体験の共有
最初から大規模で複雑な連携を目指す必要はありません。広島の事例のように、まずはランチ企画や小規模な共同イベントから始める「スモールスタート」が現実的です。小さな成功体験を積み重ね、参加ホテル間で「連携すれば、これだけのメリットがある」という手応えを共有することが、信頼関係を醸成し、より大きな連携へとステップアップしていくための土台となります。まさに、「単独」で戦う時代は終わったのです。
まとめ:競争から「共創」へ。ホテル業界の新たな地平
広島の5つのホテルが始めた小さな一歩は、ホテル業界が「競争」から「共創」へとパラダイムシフトしていく大きな潮流の表れです。もちろん、健全な競争がサービスの質を高めてきたことも事実であり、競争がなくなるわけではありません。しかし、それと同時に、業界共通の課題に立ち向かい、地域全体の価値を高めていくためには、競合という垣根を越えた協力が不可欠な時代になっています。
自社の利益だけを追求する視点から、地域全体の持続可能性を考える視点へ。この視点の転換こそが、これからのホテル、そしてホテリエに求められる最も重要な資質なのかもしれません。あなたのホテルは、隣のホテルとどのような「共創」を描けるでしょうか。その対話の先に、業界の新たな未来が拓けているはずです。


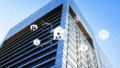
コメント