はじめに:客室を売るビジネスモデルの限界
ホテルの収益の柱は、長らく「客室の販売」でした。いかに稼働率を上げ、客室単価(ADR)を引き上げるか。この問いが、多くのホテル経営者やマーケターの頭を悩ませてきたことは言うまでもありません。しかし、その常識が大きく揺らぎ始めています。単に「泊まる場所」を提供するだけでは、価格競争の渦に巻き込まれ、持続的な成長は見込めません。この流れは当ブログでも以前「『客室』を売る時代の終焉。『体験』が収益を生む4つのメカニズム」と題した記事で論じましたが、そのトレンドを裏付ける衝撃的なデータが発表されました。
今回取り上げるのは、英国の旅行業界ニュースメディア「トラベルボイス」が報じたこちらの記事です。
ホテルの「体験コンテンツ」販売は、宿泊客の消費額2割増に、英国企業が新指標「体験インデックス」で分析
https://travelvoice.jp/20250818-157977
この記事によれば、ホテル内で提供される「体験コンテンツ」を購入した宿泊客は、そうでない客に比べてホテル内での総消費額が平均で19%も高くなるというのです。これは、体験コンテンツが単なる「付帯サービス」や「客寄せの道具」ではなく、ホテル全体の収益を押し上げる強力なエンジンとなりうることを明確に示しています。本記事では、このニュースを深掘りし、「体験」がなぜ消費を促すのか、そして日本のホテルがこのトレンドをどう捉え、戦略に落とし込むべきかを考察します。
衝撃のデータ:「体験インデックス」が示す新たな収益源
まず、ニュースの核心である英国のギフト・体験提供企業「Red Letter Days」の分析について詳しく見ていきましょう。同社は、ホテルが提供する体験コンテンツの販売実績と、宿泊客のホテル内での総消費額との相関関係を分析し、「体験インデックス」という新たな指標を提唱しました。
調査の結果、明らかになったのは以下の2点です。
- 消費額の増加: 体験コンテンツを購入した宿泊客は、購入しなかった宿泊客と比較して、ホテル滞在中の総消費額(宿泊費以外)が平均19%高かった。
- 収益貢献度の可視化: 「体験インデックス」を用いることで、これまで曖昧だった体験コンテンツの販売が、ホテル全体の収益にどれだけ貢献しているかを具体的に測定できるようになった。
特に注目すべきは、19%という具体的な数字です。これは誤差の範囲とは言えない、明確な差です。例えば、あるゲストが宿泊費以外にレストランやスパで20,000円を消費したとします。もしそのゲストが体験コンテンツを購入していれば、消費額は23,800円に増加する可能性があるということです。これが数百、数千というゲスト単位で積み重なれば、ホテル全体の収益に与えるインパクトは計り知れません。
これまで多くのホテルでは、アクティビティやイベントといった体験コンテンツは、マーケティング部門やコンシェルジュデスクが担当する「コストセンター」と見なされがちでした。つまり、直接的な利益を生むというよりは、顧客満足度を高め、宿泊予約を促進するための費用という認識です。しかし、このデータは、体験コンテンツ部門がれっきとした「プロフィットセンター」になりうることを示唆しています。もはや「付帯サービス」という考え方は時代遅れであり、体験コンテンツを収益戦略の核に据えるべき時代が到来したのです。
なぜ「体験」はゲストの財布の紐を緩めるのか?
では、なぜ体験コンテンツの購入が、ゲストの他の消費行動にまで影響を与えるのでしょうか。そのメカニズムを3つの側面から考察します。
1. 滞在価値の向上と時間消費の転換
魅力的な体験コンテンツは、ゲストのホテルでの滞在時間を長く、そして濃密にします。例えば、「地元の職人と一緒に伝統工芸品を作るワークショップ」や「ホテルのシェフと行く市場ツアー&クッキングクラス」といった体験があれば、ゲストはわざわざホテルの外で時間とお金を使う必要がなくなります。
ホテル内で過ごす時間が増えれば、自然と館内施設への接触機会も増えます。ワークショップの後にラウンジで一息ついたり、クッキングクラスで意気投合した他のゲストとバーで一杯飲んだり、といった行動が生まれます。これは、ゲストの「時間消費」をホテル内で喚起し、結果として「金銭消費」に転換させる効果があると言えます。ゲストは「ホテルに“泊まる”」のではなく、「ホテルで“過ごす”」という意識に変わり、滞在そのものを楽しむようになります。この意識の変化が、レストラン、バー、スパ、ショップなど、あらゆる収益ポイントでの消費を促すのです。
2. 心理的エンゲージメントとブランドへの愛着
体験は、単なるサービスの提供を超えて、ゲストの感情に深く働きかけます。ユニークで記憶に残る体験は、ゲストに強い満足感や高揚感を与え、ホテルに対するポジティブな印象を植え付けます。これは「心理的エンゲージメント」と呼ばれる状態で、ホテルとゲストとの間に情緒的なつながりを生み出します。
エンゲージメントが高まったゲストは、そのホテルを「ただの宿泊施設」ではなく、「特別な場所」として認識するようになります。その結果、「この素晴らしいホテルでもっと楽しみたい」「このホテルのレストランなら間違いないだろう」といった信頼感が醸成され、追加の消費に対する心理的なハードルが著しく下がります。これは、顧客ロイヤルティの向上にも直結し、リピート利用や好意的な口コミの拡散にも繋がります。まさに、ホテルCRMが目指す次世代マーケティングの理想的な形と言えるでしょう。
3. 新たな消費機会の創出(アップセル&クロスセル)
体験コンテンツは、それ自体が収益源であると同時に、他のサービスへの強力な導線(クロスセル)となり得ます。例えば、ソムリエが案内するワインテイスティング体験を提供すれば、参加者が気に入ったワインをレストランで注文したり、お土産として購入したりする可能性が高まります。
また、体験をフックにしたアップセル戦略も有効です。例えば、「スパのトリートメント体験付き宿泊プラン」を予約したゲストに対し、チェックイン時に「追加料金で、より長時間のデラックスコースに変更しませんか?」と提案する。すでに体験への期待値が高まっているゲストにとって、この種の提案は受け入れられやすいでしょう。このように、体験コンテンツを起点とすることで、これまでアプローチできなかった新たな消費機会を自然な形で創り出すことができるのです。重要なのは、タビマエ・ナカ・アトの各段階で戦略的に体験を設計し、ゲストの期待感を醸成していくことです。
日本のホテルが「体験戦略」を成功させるための4つの視点
この「体験が収益を生む」というトレンドは、もちろん日本も例外ではありません。しかし、単に流行りのアクティビティを導入するだけでは成功はおぼつきません。日本のホテルがこの流れに乗り、成果を出すためには、以下の4つの視点が不可欠です。
1. 収益管理(レベニューマネジメント)の再定義
従来のホテル収益管理は、RevPAR(販売可能な客室1室あたりの収益)を最大化することに主眼が置かれてきました。しかし、体験コンテンツが収益の柱となる時代には、この指標だけでは不十分です。今後は、TRevPAR(販売可能な客室1室あたりの総収益)や、さらに踏み込んで顧客一人あたりの総消費額、そして顧客生涯価値(LTV)といった指標を重視する必要があります。収益管理の思想を「客室」から「顧客」へとシフトさせ、ゲストが滞在中に生み出すトータルの価値を最大化する「プロフィットマネジメント」の発想が求められます。
2. 「地域」という最強コンテンツの活用
ホテル単体で提供できる体験には限界があります。しかし、一歩外に目を向ければ、日本には世界に誇るべき多様な文化、歴史、自然、食があります。これらの「地域資産」こそ、最もユニークで模倣困難な体験コンテンツの源泉です。地元の観光協会やDMO(観光地域づくり法人)と連携し、地域ならではの魅力を掘り起こし、ホテルがハブとなってゲストに提供する。この視点こそが、他にはない独自の価値を創造する鍵となります。もはやホテルは閉ざされた空間ではなく、地域と一体となって価値を創造するプラットフォームとなるべきなのです。
3. DXによるパーソナライズとシームレスな提供体制
ゲスト一人ひとりのニーズが多様化する現代において、画一的な体験コンテンツを並べるだけでは響きません。CRMや予約データからゲストの嗜好を分析し、「このゲストはアートに興味があるから、美術館の特別鑑賞ツアーを提案しよう」「前回ファミリーで来られたから、今回はお子様向けのクラフト教室をおすすめしよう」といった、パーソナライズされた提案が不可欠です。また、体験の発見、予約、決済、そして参加後のフィードバックまで、一連のプロセスをスマートフォンアプリや客室タブレットで完結できるような、シームレスなデジタル環境の構築も急務です。DXの力で、ゲストの「やってみたい」を「すぐにできる」に変えることが、体験の利用率を大きく左右します。
4. 専門人材の育成と組織体制の見直し
魅力的な体験を企画・造成し、ゲストに提供するためには、専門的なスキルを持つ人材が必要です。「エクスペリエンス・マネージャー」や「アクティビティ・ディレクター」といった専門職を設置し、その育成に投資することが重要になります。彼らは、地域の魅力を発掘するキュレーターであり、ゲストを惹きつけるイベントのプロデューサーであり、時には自らがガイド役もこなす多才な能力が求められます。また、部門間の連携も不可欠です。マーケティング、宿泊、料飲、スパといった各部門が縦割りで動くのではなく、体験コンテンツを中心に横断的に連携し、全社一丸となってゲストの総消費額を高めるための戦略を実行する組織体制へと変革していく必要があります。
まとめ:体験はコストではなく、未来への投資
今回取り上げたニュースは、ホテル業界におけるパラダイムシフトを象徴するものです。「体験コンテンツ」は、もはや単なる選択肢の一つではありません。それは、ホテルの収益構造を根本から変え、ブランド価値を決定づける戦略的なコア要素へと進化しています。宿泊客の消費額を約2割も押し上げるという事実は、そのポテンシャルの大きさを何よりも雄弁に物語っています。
客室の稼働率と単価を睨みながら、OTAの手数料に頭を悩ませる日々から脱却し、ゲストの心に残る「体験」を創造し、提供することにこそ、これからのホテルの活路はあります。それは、単なる売上増に留まらず、ゲストとの長期的な関係を築き、スタッフの働きがいをも創出する、未来への最も確かな投資と言えるでしょう。あなたのホテルでは、ゲストの記憶に残るどんな「体験」をデザインしますか?その問いから、新たな成長戦略が始まるはずです。


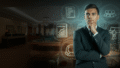
コメント