はじめに
2025年のホテル業界は、国際的な旅行需要の回復と国内観光の活性化が相まって、かつてないほどの活況を呈しています。しかし、その一方で、激化する競争、慢性的な人手不足、そして多様化するゲストのニーズといった複雑な課題に直面しているのも事実です。このような状況下で、ホテルが持続的な成長を遂げ、ゲストに選ばれ続けるためには、その根幹にある「おもてなし」の質をいかに高めるかが、これまで以上に重要になっています。
日本が世界に誇る「おもてなし」の文化は、その繊細さや心遣いによって多くのゲストを魅了してきました。しかし、この「おもてなし」という概念は、しばしば抽象的で、個々のホテリエの経験や感性に委ねられがちです。その結果、サービス品質にばらつきが生じたり、新人教育が困難になったり、あるいは従業員が自身の提供するサービスの価値を明確に認識できないといった課題が顕在化しています。
本稿では、この「おもてなし」という曖昧な概念を、ホテル運営の現場でいかに具体化し、組織全体で共有可能な「言語」として確立していくかについて深く考察します。テクノロジーに頼らず、人間本来のホスピタリティを最大限に引き出すための「おもてなしの言語化」が、2025年以降のホテル業界において、いかに競争優位性を確立し、持続可能な成長を支える鍵となるのかを掘り下げていきます。
「おもてなし」の曖昧さがもたらすホテル運営の課題
「おもてなし」という言葉を聞いて、多くの人が「気配り」「心遣い」「先回りしたサービス」といったイメージを抱くでしょう。しかし、これらの概念は非常に主観的であり、具体的な行動指針として従業員に伝えることが難しいという課題を常に抱えています。
属人化とサービス品質のばらつき
「おもてなし」が属人的なスキルに依存すると、特定の優秀な従業員がいれば素晴らしいサービスが提供される一方で、そうでない従業員の場合には質が低下するという事態を招きます。これは、ゲストにとって一貫性のない体験となり、ホテルのブランドイメージ全体に悪影響を及ぼしかねません。あるゲストは最高の感動を味わい、別のゲストは期待外れと感じる。このような品質のばらつきは、リピーターの獲得を阻害し、新規顧客の獲得にも影響を与えます。
従業員教育の困難性
「おもてなし」の属人化は、特に新人教育の現場で大きな障壁となります。「見て覚えろ」「肌で感じろ」といった指導は、経験豊富なベテランにとっては当たり前のことかもしれませんが、新入社員にとっては具体的な行動に移しにくい抽象的な指示に過ぎません。何が「良いおもてなし」で、何がそうでないのか、その判断基準が不明確なままでは、成長の機会を奪い、早期離職の原因ともなり得ます。人手不足が深刻化する2025年のホテル業界において、効率的かつ質の高い人材育成は喫緊の課題であり、曖昧な「おもてなし」の概念は、その解決を妨げる要因となっています。
人材育成については、過去記事でも触れています。「待ち」の育成では人は育たない。従業員の「キャリア自律」を促す新・人材開発論もぜひご参照ください。
従業員のモチベーション低下とストレス
「おもてなし」の基準が不明確であることは、従業員自身のモチベーションにも影響を与えます。自分が提供したサービスが本当にゲストにとって「おもてなし」として認識されたのか、正解が分からないままでは、達成感を得にくくなります。また、常に「ゲストの期待に応えなければならない」という漠然としたプレッシャーは、精神的な負担となり、結果として離職に繋がる可能性もあります。自身の仕事の価値や意義を明確に理解できない状況は、プロフェッショナルとしての成長を阻害し、キャリアパスを描きにくくします。
ブランド価値の希薄化
ホテルが提供する「おもてなし」が言語化されず、従業員個人の裁量に任されすぎると、そのホテルの持つ独自のブランド価値がゲストに伝わりにくくなります。特定のホテルチェーンや独立系ホテルが持つべき「らしさ」や「哲学」が、サービスを通じて一貫して表現されないため、競合との差別化が難しくなります。結果として、「価格」のみで選ばれるホテルとなり、利益率の低下やブランド力の低下を招くことにも繋がりかねません。
「おもてなしの言語化」とは何か?
これらの課題を解決する鍵となるのが、「おもてなしの言語化」です。これは、単にサービスマニュアルを作成することとは一線を画します。サービスマニュアルが「何をすべきか」という手順を記すものであるのに対し、「おもてなしの言語化」は、その行動の背景にある「なぜそれをするのか」という意図や、ゲストにどのような「価値」を提供したいのかという本質を明確にすることに焦点を当てます。
具体的には、ゲストの感情、期待、行動パターンを深く洞察し、それに対してホテリエがどのような意識を持ち、どのような具体的な行動をとるべきかを、誰もが理解できる言葉で表現するプロセスです。これにより、抽象的だった「おもてなし」が、組織全体で共有・実践可能な具体的な指針へと昇華されます。
この「おもてなしの言語化」の重要性について、まさに核心を突くニュースが2025年8月に発表されました。それは、「一流ホテルで2000名の若手育成実績を持つ著者が「おもてなし」の曖昧さを解剖!! 書籍『サービスを言語化する』本日発売!」というものです。
この書籍は、長年ホテル業界で若手育成に携わってきた著者が、「おもてなし」の曖昧さを具体的な言葉で解き明かし、現場のリーダーがサービスを指導する上での指針を提供しているとされます。この動きは、まさにホテル業界が直面する「おもてなし」の課題に対し、非テクノロジーの側面から本質的な解決策を提示しようとするものです。サービスを言語化することで、経験や勘に頼りがちだった「おもてなし」を、誰もが学び、実践し、さらに発展させられる普遍的なスキルへと高めることが期待されます。
言語化は、単なる言葉の定義に留まりません。それは、ホテルの哲学や価値観を従業員一人ひとりの行動に落とし込み、ゲストとのあらゆる接点で一貫したブランド体験を創出するための強力なツールとなります。このプロセスを通じて、ホテルは自らの「おもてなし」を再定義し、その独自性を際立たせることができるのです。
言語化がホテル運営にもたらす具体的なメリット
「おもてなしの言語化」は、ホテル運営の様々な側面に多大なメリットをもたらします。ここでは、その具体的な効果について深掘りしていきます。
サービス品質の均一化と向上
「おもてなし」が言語化されることで、従業員は「どのような状況で、どのような意図を持って、どのような行動をとるべきか」を明確に理解できます。これにより、個々のスキルレベルに依存することなく、ホテル全体として一定水準以上のサービスを提供することが可能になります。例えば、「ゲストがチェックイン時に疲れている様子であれば、まず温かいおしぼりを提供し、座って手続きができるよう促す」といった具体的な行動指針が共有されていれば、誰が対応しても同様の気配りが実現します。
この均一化は、特に複数の施設を運営するホテルチェーンにおいて、ブランドイメージの一貫性を保つ上で不可欠です。どのホテルに宿泊しても、同じ質の「おもてなし」を受けられるという安心感は、ゲストのロイヤルティを高める重要な要素となります。
従業員教育の効率化と定着促進
言語化された「おもてなし」は、新人教育の強力なツールとなります。抽象的な概念を具体的な言葉や行動例で示すことで、新入社員は短期間でサービスの基本を習得し、実践に移すことができます。ロールプレイングやケーススタディを通じて、様々な状況での対応をシミュレーションし、自信を持って現場に立つことができるようになります。
また、自身の仕事の意義や目的を明確に理解できることは、従業員のエンゲージメント向上にも繋がります。単なる作業の繰り返しではなく、自身の行動がゲストにどのような価値を提供しているのかを認識することで、仕事へのモチベーションが高まり、長期的な定着に寄与します。これは、人手不足が深刻化するホテル業界において、非常に重要なメリットと言えるでしょう。
従業員のキャリア自律を促すことは、定着に不可欠です。詳しくは「待ち」の育成では人は育たない。従業員の「キャリア自律」を促す新・人材開発論で解説しています。
顧客満足度の向上とロイヤルティ構築
一貫性のある質の高い「おもてなし」は、ゲストの期待を上回り、深い感動を与えます。ゲストは、単に宿泊施設を利用するだけでなく、心温まる体験を求めてホテルを選びます。言語化されたサービスが、ゲスト一人ひとりのニーズに寄り添い、期待を超える瞬間を創出することで、高い顧客満足度へと繋がります。
高い顧客満足度は、リピーターの増加だけでなく、ポジティブな口コミやSNSでの拡散にも繋がります。現代において、口コミは新たなゲストを獲得するための最も強力なマーケティングツールの一つです。言語化された「おもてなし」によって生み出される感動体験は、ホテルの評判を高め、持続的な成長を支える基盤となります。
口コミの重要性については、口コミが拓く、ホテル体験の未来でも詳しく考察しています。
ブランド価値の明確化と強化
ホテル独自の「おもてなし」を言語化することは、そのホテルのブランドアイデンティティを明確にするプロセスでもあります。「私たちはどのようなホテルであり、ゲストにどのような体験を提供したいのか」という問いに対する答えを、具体的な言葉で表現することで、ホテル独自の価値提案(Value Proposition)が確立されます。これは、マーケティング活動においても強力なメッセージとなり、ターゲット顧客層に響くブランドイメージを構築する上で不可欠です。
明確なブランド価値は、価格競争に巻き込まれることなく、ホテルの魅力を高め、より高い客室単価を設定することを可能にします。ゲストは、単なる宿泊施設ではなく、「そのホテルでしか得られない体験」を求めて、多少高くてもそのホテルを選ぶようになるでしょう。
ブランドエクイティの重要性については、「価格」で選ばれる時代の終焉。ホテルの無形資産「ブランドエクイティ」の高め方も参考になるでしょう。
従業員のモチベーション向上と主体性の醸成
「おもてなし」が言語化され、その意図や目的が明確になることで、従業員は自身の仕事がホテルのブランド価値やゲストの満足度にどのように貢献しているかを理解しやすくなります。これは、仕事への誇りや責任感を育み、モチベーションの向上に繋がります。
また、言語化は、従業員が「なぜこのサービスが必要なのか」を理解する手助けをします。これにより、単に指示されたことをこなすだけでなく、自ら考えてより良いサービスを提供しようとする主体性が醸成されます。予期せぬ状況に直面した際にも、言語化された「おもてなしの精神」に基づき、適切な判断を下し、柔軟に対応できるようになるでしょう。
「おもてなしの言語化」実践ステップ
「おもてなしの言語化」は、一朝一夕に達成できるものではありません。組織全体でのコミットメントと、体系的なアプローチが必要です。ここでは、その実践ステップを具体的に解説します。
ステップ1: 理想の「おもてなし」の定義
まず、ホテルの経営層と各部門のリーダーが中心となり、「私たちはどのようなホテルでありたいか」「ゲストにどのような体験を提供したいか」という根本的な問いに向き合います。ホテルのコンセプト、ターゲット顧客層、立地、提供するサービスの特徴などを踏まえ、理想の「おもてなし」像を具体的に描きます。
- ホテルの哲学・ビジョンの再確認: 私たちのホテルが最も大切にしている価値観は何か?
- ターゲットゲストの深掘り: どのようなゲストに来てほしいか?彼らは何を求め、何に感動するのか?
- 競合との差別化ポイント: 他のホテルにはない、私たち独自の「おもてなし」とは何か?
この段階では、抽象的な言葉でも構いません。例えば、「心温まる」「安らぎ」「驚きと感動」「効率的で快適」など、キーワードを出し合い、ホテルの目指す方向性を共有することが重要です。
ステップ2: 既存サービスの棚卸しと課題抽出
次に、現在のサービス状況を客観的に評価します。良い点、改善すべき点を洗い出すために、多角的な視点からの情報収集を行います。
- ゲストからのフィードバック分析: 口コミサイト、アンケート、SNS、直接の意見など、ゲストの声は最も貴重な情報源です。特に、感動した点や不満に感じた点を詳細に分析します。
- 従業員からのヒアリング: 現場でゲストと接する従業員は、「おもてなし」の最前線にいます。彼らの経験や感じている課題、成功事例などを吸い上げます。
- 覆面調査(ミステリーショッパー): 外部の視点から客観的にサービスを評価してもらうことで、内部では気づきにくい問題点を発見できます。
- サービスジャーニーマップの作成: ゲストがホテルに到着してから出発するまでの全ての接点を洗い出し、各段階での感情や期待、ホテリエの対応を可視化します。
このステップで、理想の「おもてなし」と現状とのギャップを明確にし、言語化すべき具体的なテーマを特定します。
ステップ3: 具体的行動への落とし込み
いよいよ、抽象的な「おもてなし」を具体的な行動レベルに落とし込む作業です。ステップ1で定義した理想の「おもてなし」を実現するために、各部門、各従業員がどのような意識を持ち、どのような行動をとるべきかを記述します。
- キーワードの分解: 例として「気配り」というキーワードを考えます。「気配り」とは具体的にどのような状況で、どのような行動を指すのか?
- 5W1Hで具体化: 「いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、誰に(Whom)、何を(What)、どのように(How)するのか」を明確にします。
- 意図と効果の明記: その行動がゲストにどのような感情や価値を提供するのか、その意図を必ず添えます。これにより、従業員は単に指示に従うだけでなく、その行動の目的を理解し、主体的にサービスを提供できるようになります。
具体例:
抽象的な「おもてなし」: 「ゲストに寄り添った気配り」
言語化された「おもてなし」:
「
【チェックイン時】
- 行動: ゲストがロビーに到着した際、荷物の多さや表情から疲労度を察知し、声かけの前にまず着席を促す。温かいおしぼりと冷たいお茶をさりげなく提供する。
- 意図: 長旅の疲れを癒し、到着直後からリラックスできる環境を提供することで、ホテルでの滞在への期待感を高める。ゲストが「自分のことを見てくれている」と感じることで、安心感と信頼感を醸成する。
【レストランでの食事中】
- 行動: ゲストの食事の進み具合や会話の区切りを見計らい、適切なタイミングで飲み物の追加や次の料理の提供を提案する。小さな子供連れのゲストには、子供用の食器やエプロンを、リクエストされる前に用意する。
- 意図: 食事を中断させることなく、スムーズで心地よい時間を提供し、食事体験を最大限に楽しんでいただく。ゲストが「言わなくても分かってくれる」と感じることで、深い満足感と感動を与える。
このように、具体的な状況と行動、そしてその背景にある意図をセットで言語化することが重要です。
ステップ4: 共有と浸透
言語化された「おもてなし」は、全従業員に共有され、組織文化として浸透しなければ意味がありません。
- 全社研修の実施: 経営層から現場スタッフまで、全員が参加する研修を定期的に実施し、言語化された「おもてなし」の理念と具体的な行動指針を共有します。
- ロールプレイングとフィードバック: シナリオを用いたロールプレイングを通じて、実践的なスキルを習得させ、互いにフィードバックし合うことで理解を深めます。
- 社内報や掲示物での啓蒙: 定期的に「今月のベストおもてなし事例」などを紹介し、成功体験を共有することで、良い行動を奨励し、学習を促進します。
- OJT(On-the-Job Training)の強化: ベテラン従業員が新人に対し、言語化された基準に基づいた具体的な指導を行うことで、現場での実践力を高めます。
ステップ5: 定期的な見直しと改善
「おもてなし」は生き物であり、ゲストのニーズや市場環境は常に変化します。一度言語化して終わりではなく、定期的に見直し、改善していくサイクルを確立することが重要です。
- フィードバックシステムの構築: ゲストからの直接的なフィードバックはもちろん、従業員からの意見や提案を吸い上げる仕組みを設けます。
- 定例会議での議論: 各部門の定例会議で「おもてなし」の事例や課題について議論し、改善策を検討します。
- 市場トレンドの把握: 競合ホテルの動向や、旅行業界全体のトレンドを常に把握し、自ホテルの「おもてなし」が時代に即しているかを確認します。
このPDCAサイクルを回すことで、「おもてなしの言語化」は常に進化し、ホテルの競争力を維持・向上させていくことができます。
言語化における注意点と課題
「おもてなしの言語化」は多くのメリットをもたらしますが、その実践にはいくつかの注意点と課題も存在します。これらを認識し、適切に対処することが成功の鍵となります。
画一化の罠と個性の尊重
最も懸念されるのが、言語化がサービスを画一化し、マニュアル通りの「ロボットのような」サービスになってしまうことです。本来「おもてなし」は、ゲスト一人ひとりの状況や感情を読み取り、柔軟に対応する個人の感性や創造性が不可欠です。言語化は、あくまで基礎となる指針であり、その上に従業員一人ひとりの個性や人間性を乗せることで、真の感動が生まれます。
このバランスを取るためには、言語化された基準は「最低限の品質保証」と「最高の体験へのガイドライン」として位置づけ、その範囲内での個人の裁量や工夫を積極的に奨励する文化を醸成することが重要です。例えば、「基本を忠実に守りつつ、ゲストの反応を見て+αの提案を心がける」といった形で、言語化の範囲と個人の創造性の領域を明確にすることが求められます。
言葉の限界と「空気感」の重要性
どれほど詳細に言語化しても、言葉では表現しきれない「空気感」や「直感」といった要素が「おもてなし」には存在します。ホテルの空間が醸し出す雰囲気、従業員の表情や声のトーン、ゲストとの間に流れる心地よい間合いなど、非言語的な要素がゲストの体験に与える影響は計り知れません。
言語化は、これらの非言語的要素の重要性を従業員に意識させ、それを引き出すための土台作りに貢献しますが、決してすべてを言葉で網羅しようとするべきではありません。むしろ、言語化を通じて「おもてなしの精神」を共有し、その精神に基づいた個々の感性を磨く機会と捉えるべきでしょう。現場でのOJTやメンター制度を通じて、言葉では伝えきれない「暗黙知」を継承していく努力も不可欠です。
トップダウンとボトムアップの融合
「おもてなしの言語化」は、経営層のビジョンと現場の知見が融合して初めて成功します。経営層が一方的に理想の「おもてなし」を押し付けても、現場の実情に合わなければ絵に描いた餅となってしまいます。逆に、現場の意見だけを反映させても、ホテルのブランド戦略や長期的なビジョンと乖離する可能性があります。
このため、言語化のプロセスにおいては、経営層が明確な方向性を示しつつ、現場の従業員が積極的に意見を出し合い、具体的な行動指針の策定に参画できるような仕組みを作ることが重要です。ワークショップや意見交換会を定期的に開催し、双方向のコミュニケーションを通じて、全員が納得感を持って取り組めるようなプロセスを設計することが求められます。
継続的なコミットメントと組織文化への定着
「おもてなしの言語化」は、一度実施すれば終わりというものではありません。ゲストのニーズや市場環境の変化に合わせ、常に内容を見直し、改善していく継続的な努力が必要です。また、言語化された「おもてなし」が、単なるルールブックとしてではなく、ホテルの組織文化として深く根付くためには、経営層からの強いコミットメントと、日々の運用における徹底した実践が不可欠です。
定期的な研修、成功事例の共有、表彰制度の導入など、従業員が「おもてなしの言語化」を意識し、実践し続けるためのインセンティブやサポート体制を構築することも重要です。これにより、「おもてなしの言語化」は、ホテルのDNAとなり、持続的な競争優位性を生み出す源泉となるでしょう。
まとめ
2025年のホテル業界において、競争の激化とゲストニーズの多様化は、ホテル運営に新たな挑戦を突きつけています。このような時代において、日本が誇る「おもてなし」の価値を最大限に引き出し、持続可能な成長を実現するためには、その曖昧さを解消し、組織全体で共有可能な「言語」として確立することが不可欠です。
「おもてなしの言語化」は、単なるサービスマニュアルの作成に留まらず、ホテルの哲学とゲストへの深い理解に基づき、具体的な行動とその意図を明確にするプロセスです。これにより、サービス品質の均一化と向上、従業員教育の効率化と定着促進、顧客満足度の向上とロイヤルティ構築、そしてホテルのブランド価値の明確化と強化といった多岐にわたるメリットがもたらされます。
もちろん、言語化には画一化の罠や言葉の限界といった課題も存在します。しかし、これらを認識し、個人の創造性を尊重しつつ、トップダウンとボトムアップの融合を図り、継続的な改善サイクルを回すことで、これらの課題は克服可能です。
「おもてなしの言語化」は、非テクノロジーの側面からホテルの「人間力」を最大限に引き出し、ホテリエ一人ひとりが自身の仕事に誇りを持ち、主体的にゲストに感動を与えるサービスを提供するための羅針盤となります。それは、単に効率性を追求するだけでなく、ゲストとの間に深い人間的な繋がりを築き、記憶に残る唯一無二の体験を創造するための、2025年以降のホテル運営において最も重要な戦略の一つと言えるでしょう。
ホテルが提供する「おもてなし」が言語化され、組織全体で共有・実践されることで、ゲストは一貫した質の高いサービスを享受し、ホテルは揺るぎないブランドを確立することができます。この取り組みが、未来のホテル業界の発展を支える強固な基盤となることを確信しています。


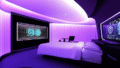
コメント