はじめに:スクラップ&ビルドから「再生」の時代へ
2025年、ホテル業界の開発トレンドは大きな転換期を迎えています。インバウンド需要の回復と国内旅行の活発化を背景に、都市部から地方に至るまで新たなホテルの開業ラッシュが続いていますが、その潮流の中でひときゆわ異彩を放つ動きが加速しています。それが、既存建物をホテルへとコンバージョン(用途転換)する、いわゆる「再生建築」です。オフィスビルや倉庫、銀行などがホテルに生まれ変わる事例はこれまでも散見されましたが、今、特に注目を集めているのが、地域の歴史や文化を象徴する「公共建築」のホテルへの再生です。
このトレンドを象徴する興味深いニュースが報じられました。
三重・伊賀の坂倉準三設計の元市庁舎がホテルと図書館に再生!?〈MARU。architecture〉が改修を担当。
https://casabrutus.com/categories/architecture/461519
この記事では、日本のモダニズム建築を代表する建築家、坂倉準三が設計した三重県伊賀市の旧市庁舎が、ホテルと図書館を併設した複合施設として再生される計画が報じられています。単なる遊休資産の活用に留まらず、歴史的価値を持つ公共建築が、宿泊機能と地域の知の拠点という新たな役割を担って生まれ変わる。この挑戦は、これからのホテル開発のあり方、そしてホテルが地域社会で果たすべき役割について、私たちに多くの示唆を与えてくれます。本記事では、この事例を糸口に、なぜ今、公共建築のホテルへのコンバージョンが注目されるのか、その背景と可能性、そしてホテル運営者が乗り越えるべき課題について深掘りしていきます。
なぜ今、公共建築のホテルコンバージョンが加速するのか
かつて地域の中心であった市庁舎や学校、郵便局といった公共建築が、統廃合や老朽化によりその役目を終え、活用されないまま放置されるケースは全国的な課題となっています。これらの建物をホテルとして再生する動きが活発化している背景には、単なるビジネスチャンスを超えた、いくつかの複合的な要因が存在します。
1. サステナビリティと文化継承への意識の高まり
SDGsへの関心が社会全体で高まる中、建設業界においてもスクラップ&ビルド型の開発モデルが見直されつつあります。既存の建物を解体せず、その構造躯体や意匠を活かして再生することは、建設廃棄物の削減やCO2排出量の抑制に繋がり、環境負荷を大幅に低減します。さらに、公共建築は地域のランドマークとして、人々の記憶に深く刻まれている存在です。その建物を保存・活用することは、地域の歴史やアイデンティティを次世代に継承するという文化的な意義も持ち合わせています。こうしたサステナブルな開発思想が、デベロッパーだけでなく、宿泊するゲストや地域住民からも支持を集め始めているのです。
2. 「物語」がもたらす唯一無二の宿泊体験
現代の旅行者は、単に快適な客室に泊まるだけでなく、その土地ならではの特別な体験を求めています。歴史的建築物を再生したホテルは、その成り立ち自体が強力な「物語」を持っています。元市庁舎の議場をラウンジに、校長室をスイートルームに、といったユニークな空間は、新築のホテルでは決して真似のできない唯一無二の価値を生み出します。ゲストは、建物の歴史に思いを馳せながら滞在することで、深い満足感と記憶に残る体験を得ることができるのです。これは、価格競争から脱却し、高付加価値なホテルを目指す上で極めて重要な要素と言えるでしょう。当ブログの過去記事『物語を売るホテル。価格競争から脱却するストーリーテリング戦略』でも論じたように、体験価値の源泉となるストーリーは、強力な競争優位性となります。
3. 地域活性化の起爆剤としての期待
人口減少や高齢化に悩む地方にとって、交流人口の拡大は喫緊の課題です。地域の象徴的な建物を再生したホテルは、新たな観光の核となり、地域全体に経済的な波及効果をもたらすポテンシャルを秘めています。伊賀市の事例のように、図書館といった公共施設を併設することで、宿泊客だけでなく地域住民も日常的に集う交流拠点が生まれます。これは、ホテルが単なる宿泊施設に留まらず、街の賑わいを創出する「ハブ」としての役割を担うことを意味します。まさに、『「ラブローカル」が鍵。ホテルが街の「HUB」になる新戦略』で提唱したコンセプトを具現化する動きと言えるでしょう。
コンバージョンホテルの運営における挑戦と課題
公共建築の再生は大きな可能性を秘める一方で、その実現と運営には特有の難しさも伴います。ホテル事業者やホテリエは、これらの課題を深く理解し、戦略的に向き合う必要があります。
1. 設計・施工における制約との戦い
歴史的価値を持つ建物の改修は、常に「保存」と「機能性」のジレンマを抱えます。オリジナルの意匠や構造を最大限尊重しながら、現代の建築基準法や消防法、バリアフリー基準に適合させることは、技術的にもコスト的にも極めて難易度の高い作業です。例えば、古い建物の断熱性や遮音性を現代のホテルの水準まで引き上げるには、大掛かりな工事が必要となり、予算を圧迫する要因となります。また、予期せぬ構造上の問題が工事中に発覚することも少なくありません。こうした技術的な課題を乗り越え、唯一無二の空間価値を創造するためには、『建築が「生きる」ホテル。アダプティブ・デザインが創る次世代の宿泊体験』で触れたような、既存の制約を創造性へと転換する設計思想が不可欠です。
2. 運営効率とゲスト体験の最適化
ホテルとして設計されていない建物を転用する場合、運営上の非効率性が生じやすいという課題があります。例えば、客室のレイアウトが不均一であったり、スタッフの動線が長くなったり、バックヤードのスペースが十分に確保できなかったり、といった問題です。これらの制約は、人件費や清掃コストの上昇に直結します。運営側は、これらのハード面の不利を、ソフト面の工夫でいかにカバーするかという知恵が問われます。例えば、不均一な客室を逆手にとって、一部屋一部屋に異なる個性を持たせ、リピーターを飽きさせない工夫を凝らす。あるいは、非効率な動線を補うために、DXツールを積極的に導入し、スタッフ間の情報連携を密にする、といった対策が考えられます。
3. 地域社会との共存共栄
地域の宝である公共建築を預かる以上、ホテルは地域社会に対して開かれ、貢献する存在でなければなりません。開発段階から地域住民への丁寧な説明と合意形成を怠れば、思わぬ反対運動に直面するリスクもあります。「自分たちの市庁舎が、観光客だけのための閉鎖的な高級ホテルになってしまうのではないか」という不安を払拭し、地域住民が誇りを持ち、愛着を感じられる施設にしていく必要があります。伊賀市の事例のように、図書館やカフェ、イベントスペースなど、地域住民が日常的に利用できる機能を併設することは、地域との良好な関係を築く上で非常に有効なアプローチです。ホテルは、地域コミュニティの一員として、『街の価値を創造するホテル。再開発プロジェクトにおける新たな役割』を担っていくという強い意志が求められます。
まとめ:ホテルは「街の記憶」を紡ぐメディアになる
三重県伊賀市の元市庁舎再生のニュースは、ホテル業界が単なる宿泊サービスの提供者から、地域の文化資本を活用し、新たな価値を創造する「プロデューサー」へと進化していく未来を予感させます。公共建築のコンバージョンは、サステナビリティ、文化継承、地域創生という現代社会の要請に応えながら、ホテル自身も他にはない強力なブランド価値を構築できる、Win-Winの戦略と言えるでしょう。
もちろん、その道のりは平坦ではありません。設計・施工の技術的なハードル、運営効率の課題、そして地域社会との丁寧な対話など、乗り越えるべき壁は数多く存在します。しかし、これらの困難に真摯に向き合い、建物の持つ「記憶」や「物語」を宿泊体験へと昇華させることができた時、そのホテルは単なる「泊まる場所」を超え、ゲストと地域、そして過去と未来を繋ぐ「メディア」のような存在になるはずです。
2025年以降、私たちはますます多くの「再生ホテル」の誕生を目にすることになるでしょう。その一つひとつが、どのような物語を紡ぎ、街にどのような変化をもたらしていくのか。ホテル業界に関わる者として、その動向から目が離せません。

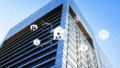
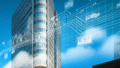
コメント