はじめに
2025年、ホテル業界はかつてないほどの変化の波に直面しています。インバウンド需要の回復、国内旅行の再活性化といった明るい兆しがある一方で、深刻化する人手不足、従業員の高齢化、そして事業承継の難しさといった構造的な課題が、多くのホテル、特に地域に根差した老舗ホテルを苦しめています。テクノロジーの進化はこれらの課題の一部を解決する可能性を秘めていますが、ホテルの本質的な価値である「おもてなし」や「地域とのつながり」は、やはり「人」によって紡がれるものです。
今回、私たちはあるニュース記事に注目しました。それは、長年にわたり高校野球の東京代表校の常宿として親しまれてきた「甲子園ホテル夕立荘」が、高齢化による負担を理由に、今大会での受け入れを終了するというものです。このニュースは、単なる一ホテルの閉館話に留まらず、日本のホテル業界全体が直面する「人」にまつわる運営の課題、そしてその持続可能性について深く考えさせるものです。
本稿では、この甲子園ホテル夕立荘の事例を起点に、テクノロジーだけでは解決し得ない、ホテル運営における「人」と「地域」に焦点を当てた課題とその解決策について、多角的に考察していきます。ホテルの未来を考える上で、この「人」と「地域」という根源的なテーマは避けて通れないからです。
老舗ホテルが直面する現実:甲子園ホテル夕立荘の事例
2025年、夏の甲子園。多くの球児が夢見る聖地での戦いの裏側で、長年彼らを支え続けてきた一つの老舗ホテルが、その歴史に区切りをつけました。東京新聞デジタルが報じた「高校野球・東京代表の常宿「甲子園ホテル夕立荘」今大会で受け入れ終了 高齢化で負担…球児を思う故の決断」というニュースは、多くの関係者に衝撃を与えました。
甲子園ホテル夕立荘は、半世紀以上にわたり、高校球児たちの宿舎として、彼らの夢を支え、多くの感動の瞬間を見守ってきました。そのサービスは、単に宿泊施設を提供するだけでなく、球児たちの体調管理から精神的なサポートまで、まさに「第二の家」として機能していたと言えるでしょう。しかし、記事が伝えるように、その運営を支えてきた従業員の「高齢化による負担」が、継続を困難にする決定的な要因となりました。
この事例が示唆するのは、老舗ホテルが持つ「無形の価値」と、それを維持するための「有形の限界」との間の深刻なギャップです。夕立荘が提供してきたのは、単なるベッドや食事ではありません。それは、球児たちの記憶に深く刻まれる「おもてなし」であり、彼らの挑戦を後押しする「安心感」でした。これらの価値は、長年の経験と情熱を持つ「人」によってのみ生み出されるものです。
しかし、その「人」が高齢化し、肉体的・精神的な負担が増大すれば、どれほど強い情熱があっても、サービスを維持することは難しくなります。特に、高校野球のように、選手たちの健康管理や精神状態に細心の注意を払う必要がある宿泊形態では、その負担は計り知れません。夕立荘の決断は、単なる経営判断ではなく、「球児を思う故」の苦渋の選択であったことが、その重みを物語っています。
このニュースは、多くの老舗ホテルが直面している現実を浮き彫りにします。長年の歴史の中で培われたブランド、顧客との深い絆、そして地域社会における特別な存在感。これらはホテルの大きな強みである一方で、その伝統を未来へと繋ぐための「人」という資本が、今、限界を迎えつつあるのです。
高齢化と事業承継の課題:ホテル業界の共通項
甲子園ホテル夕立荘の事例は、特定のホテルだけの問題ではありません。日本のホテル業界全体、特に地方の中小規模のホテルや旅館において、従業員の高齢化とそれに伴う事業承継の課題は、喫緊の経営課題となっています。2025年現在、この問題はさらに深刻化しており、多くのホテルが存続の危機に瀕しています。
従業員の高齢化がもたらす影響
ホテル業界は、労働集約型の産業であり、「人」の力がサービスの質を大きく左右します。長年ホテルで働き、熟練した技術と深い知識を持つベテラン従業員は、まさにホテルの宝です。彼らは、顧客のニーズを先読みし、きめ細やかなサービスを提供し、若手従業員を育成する上で不可欠な存在です。しかし、彼らの高齢化が進むと、以下のような問題が生じます。
- 労働力の低下:肉体労働が多いホテル業務において、高齢の従業員は体力的な限界に直面しやすくなります。清掃、荷物運び、レストランでのサービスなど、多岐にわたる業務の効率が低下する可能性があります。
- 新たなスキルの習得の遅れ:デジタル化や新しいサービスモデルの導入が進む中で、高齢の従業員が新しいシステムやテクノロジーへの適応に時間を要する場合があります。これにより、業務のDX化が滞ることもあります。
- 後継者育成の遅れ:ベテラン従業員が持つ知識やノウハウが、組織内で適切に共有・継承されないまま引退してしまうリスクが高まります。これは、ホテルのサービス品質を維持する上で致命的な問題となり得ます。過去の記事でも「総支配人候補」が育たない。ホテル業界の未来を左右するサクセッションプランニング戦略として、リーダーシップの継承の重要性を指摘しています。
深刻化する事業承継問題
従業員の高齢化と並行して、経営者の高齢化と後継者不足も深刻です。特に家族経営や個人経営のホテルでは、以下の課題が顕在化しています。
- 後継者候補の不在:若年層の都市部への流出、ホテル業界への魅力低下などにより、事業を継ぐ意思のある親族がいないケースが増えています。
- 経営ノウハウの継承困難:長年の経験と勘に頼ってきた経営スタイルでは、属人化したノウハウが多く、体系的な継承が難しい場合があります。
- 多額の投資とリスク:老朽化した施設の改修や新しいサービスへの投資は、多額の資金を要し、後継者にとって大きな負担となります。
これらの課題は、多くの老舗ホテルが、たとえ収益性が高くても、最終的に廃業を選択せざるを得ない状況に追い込んでいます。地域に愛され、独自の文化を築いてきたホテルが姿を消すことは、単に一つの企業がなくなるだけでなく、その地域にとってかけがえのない財産が失われることを意味します。
この状況を打開するためには、従来の「人手はいるもの」という前提を見直し、「いかに人を活かし、人を育てるか」という視点での抜本的な戦略転換が不可欠です。テクノロジーの導入ももちろん重要ですが、それはあくまで「人」が提供する価値を最大化するための手段であり、目的ではありません。従業員一人ひとりが長く働き続けられる環境を整備し、その経験とスキルを次世代に確実に継承していくための具体的な取り組みが、今、求められています。
地域コミュニティとの共生:単なる宿泊施設を超えて
甲子園ホテル夕立荘の事例は、ホテルが地域社会において果たす役割の大きさを改めて浮き彫りにしました。このホテルは、単に宿泊施設として機能するだけでなく、高校野球という特定の文化やコミュニティにとって、かけがえのない「場所」であり、「記憶」の拠り所でした。ホテルが地域と深く結びつき、単なるビジネスを超えた価値を提供する「地域共生型ホテル」の重要性が、今、再認識されています。
ホテルが提供する「場所」の価値
多くの老舗ホテルは、その地域にとってのランドマークであり、歴史や文化を物語る存在です。夕立荘が高校球児にとっての「常宿」であったように、ホテルは特定の顧客層やコミュニティにとって、単なる宿泊以上の意味を持つことがあります。それは、家族の思い出の場所であったり、ビジネスの拠点であったり、あるいは地域のイベントの中心であったりします。
このようなホテルは、地域住民にとっては誇りであり、訪問者にとっては地域文化を体験する窓口となります。ホテルの存在自体が、地域の魅力を高め、観光客を呼び込む磁力となるのです。過去の記事でも、「目的地」になるホテル。森トラストの戦略に学ぶ、地域共創の新時代や「ラブローカル」が鍵。ホテルが街の「HUB」になる新戦略として、ホテルが地域との連携を深め、その中心的な存在となることの重要性を論じています。
ホテルの閉館が地域に与える影響
このような地域に根差したホテルが閉館することは、単に一つのビジネスがなくなる以上の影響を地域社会に与えます。具体的には、以下のような側面が挙げられます。
- 経済的損失:雇用喪失、関連産業(飲食店、土産物店、交通機関など)への影響、観光客減少による地域経済の停滞。
- 文化的損失:地域の歴史や伝統を伝える場所の喪失、特定のコミュニティ(夕立荘の事例では高校野球関係者)にとっての精神的拠点の喪失。
- 社会心理的影響:地域住民のアイデンティティの一部が失われることによる喪失感、地域の活気低下。
夕立荘の閉館は、球児たちだけでなく、長年その活動を支えてきた人々、そして地域住民にとっても大きな寂しさを伴うものです。これは、ホテルが地域経済の歯車であると同時に、地域の「心」の一部でもあることを示しています。
地域共生型ホテルへの展望
このような状況を踏まえ、今後のホテル運営においては、地域コミュニティとの共生を一層意識した戦略が不可欠です。単に宿泊客を呼び込むだけでなく、地域住民も利用できる施設やサービスを提供し、地域イベントの拠点となるなど、多角的な関わり方を通じて、ホテルの存在価値を高めることができます。
例えば、地元の食材を積極的に活用したレストラン、地域文化を体験できるアクティビティの提供、住民向けのイベントスペースとしての貸し出しなどが考えられます。これにより、ホテルは地域経済の活性化に貢献し、住民との絆を深め、結果としてホテルの持続可能性を高めることができるでしょう。地域に愛され、必要とされるホテルこそが、厳しい時代を乗り越える真の強さを持つと言えます。
「人」の価値を再認識する時代:経験と情熱の継承
ホテル業界における高齢化と事業承継の課題を深く掘り下げると、最終的に行き着くのは「人」の価値、そしてその経験と情熱をいかに次世代に継承していくかという根源的な問いです。テクノロジーが進化し、業務効率化が進む2025年においても、ホテルの「おもてなし」の核は、やはり人間の温かみと専門知識にあります。
熟練スタッフの持つ「おもてなしの心」と「現場の知恵」
甲子園ホテル夕立荘の事例で、ベテランスタッフが球児たちに提供してきた「第二の家」のような温かいサービスは、マニュアルでは決して再現できません。それは、長年の経験から培われた洞察力、個々のゲストに合わせた柔軟な対応、そして何よりも「相手を思いやる心」から生まれるものです。このような熟練スタッフは、単に業務をこなすだけでなく、ホテルの「ブランドを体現する存在」と言えるでしょう。
彼らが持つ「現場の知恵」もまた、計り知れない価値があります。予期せぬトラブルへの対処法、特定の顧客の嗜好に関する情報、効率的な清掃手順、地域との関係構築のコツなど、書物や研修だけでは得られない生きた知識が、ホテルの円滑な運営を支えています。これらの知識は、多くの場合、属人化しており、世代交代が進む中で失われやすい傾向にあります。
ホテリエの「感情労働」とやりがい
ホテル業は、顧客の感情に寄り添い、最高の体験を提供する「感情労働」の側面が非常に強い職業です。喜び、感謝、時には不満や怒りといった多様な感情に日々向き合いながら、常に笑顔とプロフェッショナリズムを保つことは、大きな精神的負担を伴います。過去の記事でも、感情労働を乗りこなせ。ホテリエが長く輝くための「セルフマネジメント」術として、この側面について深く考察しています。
しかし、この感情労働の先に、ゲストからの感謝の言葉や、忘れられない体験を提供できたという達成感があります。熟練スタッフは、このやりがいを原動力に長年働き続けてきました。彼らの引退は、単なる人手不足だけでなく、この「やりがい」と「情熱」の連鎖が途切れることにも繋がりかねません。若手ホテリエが、この仕事の深い魅力と価値を理解し、長く働き続けられるような環境を整備することが、持続可能なホテル運営には不可欠です。
経験と情熱を次世代に継承するための戦略
では、どのようにして熟練スタッフの経験と情熱を次世代に継承し、ホテルの「人」の価値を高めていくべきでしょうか。テクノロジーに依存しない、具体的な人材戦略が求められます。
- メンターシップ・制度の強化
ベテランスタッフと若手スタッフをペアにするメンターシップ制度を確立し、OJTだけでなく、日々の業務の中で非公式な知識や「おもてなしの心」を直接伝える機会を増やすことが重要です。過去の記事「教える」から「学び合う」へ。リバースメンタリングが拓くホテル組織の未来で提唱した「リバースメンタリング」のように、若手からベテランへ新しい視点を提供する機会も、双方の成長を促します。 - 知識・ノウハウの体系化
熟練スタッフの持つ知識やノウハウを、口頭伝承だけでなく、マニュアル化、動画化、あるいは社内Wikiのような形で体系的に記録し、誰もがアクセスできるようにする取り組みが必要です。これにより、属人化を防ぎ、効率的な学習を可能にします。 - 多世代共存型の職場環境構築
高齢の従業員が体力的な負担を感じずに働き続けられるような柔軟な勤務体系(短時間勤務、業務内容の調整など)や、バリアフリーな職場環境の整備が求められます。また、若手従業員が「このホテルで長く働きたい」と思えるような心理的安全性の高い組織文化を醸成することも重要です。 - キャリアパスの多様化
現場でのサービス提供だけでなく、人材育成、品質管理、地域連携のスペシャリストなど、多様なキャリアパスを用意することで、従業員が自身の経験とスキルを活かして長く貢献できる道筋を示すことができます。過去の記事「待ち」の育成では人は育たない。従業員の「キャリア自律」を促す新・人材開発論で述べたように、従業員の自律的なキャリア形成を支援する姿勢が求められます。
「人」という資本への投資は、短期的にはコストと見なされがちですが、長期的に見れば、ホテルのブランド価値を高め、顧客満足度を向上させ、持続的な成長を実現するための最も重要な戦略です。甲子園ホテル夕立荘の事例は、この「人」の価値を再認識し、その継承に真剣に取り組むことの重要性を私たちに教えてくれています。
持続可能なホテル運営への多角的なアプローチ
甲子園ホテル夕立荘の閉館が示唆するように、ホテル業界が直面する高齢化、人手不足、事業承継といった課題は、単一の解決策では乗り越えられない複合的なものです。持続可能なホテル運営を実現するためには、多角的な視点とアプローチが不可欠です。ここでは、テクノロジーに過度に依存せず、ホテルの本質的な価値を守りながら、未来へと繋ぐための戦略を考察します。
1. 事業承継モデルの多様化と柔軟な選択肢
家族経営や個人経営のホテルにとって、後継者が見つからない場合の選択肢は、閉館だけではありません。多様な事業承継モデルを検討することが重要です。
- M&A(合併・買収):地域のブランドを維持しつつ、大手ホテルチェーンや投資ファンドの傘下に入ることで、資金力や人材、運営ノウハウを獲得し、事業を継続させる道です。これにより、ホテルの伝統や従業員の雇用を守ることが可能になります。買収劇の裏側。ホテルM&Aが加速する本当の理由でも触れたように、業界再編の動きは加速しています。
- ソフトブランド化:独立系ホテルの個性を保ちながら、大手ブランドのマーケティング力や予約システムを活用する戦略です。これにより、集客力を高めつつ、ホテルの独自性を維持できます。「個性」と「巨大資本」の融合。ホテル業界で急増する「ソフトブランド」戦略は、この有効な手段の一つです。
- 地域連携による運営支援:地域DMO(観光地域づくり法人)や地域の商工会議所、他のホテルとの連携を通じて、共同で人材を育成したり、運営ノウハウを共有したりする仕組みを構築することも考えられます。競合が手を組む日。ホテル間連携という生存戦略は、この文脈で重要な示唆を与えます。
2. 人材戦略の再構築と多様な働き方の推進
従業員の高齢化と人手不足に対応するためには、従来の採用・育成・定着の枠組みを見直す必要があります。
- 多様な人材の活用:定年退職者の再雇用、外国人材の積極的な採用、短時間勤務やリモートワーク(一部業務)など、多様な働き方を許容することで、幅広い人材を確保します。特に、若年層の人材定着戦略は喫緊の課題です。
- リスキリング(学び直し)の支援:既存従業員が新しいスキル(デジタルツール操作、多言語対応、マーケティングなど)を習得できるよう、研修プログラムや学習機会を提供します。これにより、従業員の市場価値を高め、キャリアの選択肢を広げることができます。
- エンプロイヤー・ブランディングの強化:ホテルを「働きたい場所」として魅力的に見せるためのブランディング活動を強化します。従業員の満足度向上、働きがいの創出、キャリアパスの明確化などを通じて、採用力を高めます。なぜ、あなたのホテルは「選ばれない」のか?採用ミスマッチを防ぐエンプロイヤー・ブランディング戦略も参考にしてください。
3. 体験価値の再定義と地域資源との連携
「客室」を売る時代から「体験」を売る時代へと移行する中で、ホテルの提供価値を再定義し、地域資源と連携させることが重要です。
- 地域文化・体験コンテンツの創出:地元の職人とのコラボレーション、歴史的建造物の活用、自然体験ツアーなど、その地域ならではのユニークな体験コンテンツを開発します。これにより、宿泊客はホテル滞在だけでなく、地域全体を深く楽しむことができます。客単価2割増の衝撃。「体験コンテンツ」がホテル経営の主役になる日や体験価値を収益に変える。タビマエ・ナカ・アトで設計するホテル戦略が参考になります。
- 地域住民との交流拠点化:ホテル内のカフェやレストランを地域住民にも開放したり、ワークショップやイベントスペースとして提供したりすることで、ホテルを地域コミュニティのハブとして機能させます。
4. 物理的施設の工夫とリノベーション
老朽化した施設は、顧客満足度だけでなく、従業員の働きやすさにも影響を与えます。大規模な建て替えが困難な場合でも、戦略的なリノベーションが有効です。
- バリアフリー化とユニバーサルデザイン:高齢の従業員や多様なゲストが快適に利用できるような施設改修を進めます。
- 多機能空間の創出:客室やロビーを、宿泊以外の用途(コワーキングスペース、イベント会場、地域住民の交流スペースなど)にも利用できるよう改修することで、収益源の多様化と地域貢献を両立させます。ホテルリノベーション戦略:成功への道筋と運営のポイントで詳細を解説しています。
これらのアプローチは、それぞれが独立しているのではなく、相互に連携し合うことで最大の効果を発揮します。ホテルの経営者は、自らのホテルの特性、地域の状況、そして将来のビジョンを踏まえ、最適な組み合わせを見出すことが求められます。
未来への提言:伝統と革新のバランス
甲子園ホテル夕立荘の事例は、ホテル業界が直面する課題の根深さを浮き彫りにしましたが、同時に、未来への重要な示唆を与えています。それは、伝統をただ守るだけでなく、現代の社会変化に対応するための「革新」が不可欠であるという事実です。2025年、ホテル経営者は、この伝統と革新のバランスをいかに取り、持続可能な未来を築いていくかという、重い問いに直面しています。
テクノロジーは「人」を支えるツールである
本稿では、テクノロジーとは直接関連しない運営課題に焦点を当ててきましたが、それはテクノロジーを否定するものではありません。むしろ、テクノロジーは、高齢化や人手不足といった課題に対し、「人」が提供する価値を最大化するための強力なツールとして機能します。
例えば、AIを活用したレベニューマネジメントは、熟練の勘と経験を補完し、収益最適化を支援します。スマートチェックインシステムやロボットによる清掃は、従業員の負担を軽減し、より「人」にしかできないおもてなしの業務に集中できる時間を作り出します。しかし、これらのテクノロジーは、あくまで「手段」であり、ホテルの本質的な魅力である「人」による温かいサービスや、地域との深い繋がりを代替するものではありません。テクノロジーを導入する際は、その目的が「人の価値を向上させること」にあるかを常に問い直す必要があります。
ホテルの「物語」を再構築する力
甲子園ホテル夕立荘が半世紀以上にわたり球児たちに愛されたのは、単に宿泊施設としての機能だけでなく、彼らの「物語」の一部となる場所であったからです。ホテルは、単なる建物やサービスではなく、そこで生まれる「体験」や「記憶」、「物語」を売る場所です。これは物語を売るホテル。価格競争から脱却するストーリーテリング戦略でも強調した点です。
高齢化や事業承継の課題に直面する老舗ホテルは、自らの歴史や地域との関わり、そして顧客との間に築いてきた絆を再評価し、それを現代の顧客に響く「物語」として再構築する力が必要です。その物語を語り継ぎ、新たな価値を創造していくのは、やはり「人」です。従業員一人ひとりがその物語の担い手となり、誇りを持って働くことができる環境こそが、ホテルの持続的な成長を支える基盤となります。
経営者の「決断力」と「ビジョン」
最終的に、ホテルの未来を左右するのは、経営者の「決断力」と「ビジョン」です。閉館という苦渋の決断を下した甲子園ホテル夕立荘の経営者も、また、その決断の重みに向き合ったことでしょう。しかし、閉館だけが選択肢ではありません。事業承継、リノベーション、新たなコンセプトの導入、地域との連携強化など、多岐にわたる選択肢の中から、自らのホテルの強みと弱み、そして市場のニーズを冷静に見極め、未来を見据えた戦略的な決断を下すことが求められます。
その際、目先の利益だけでなく、ホテルの文化的価値、地域社会への貢献、そして従業員の幸福といった多面的な要素を考慮に入れる必要があります。ホテルの経営は、単なるビジネスではなく、地域社会、従業員、そして顧客の「人生」に深く関わる事業であることを忘れてはなりません。
2025年以降、ホテル業界はさらなる変革期を迎えるでしょう。この変化の波を乗りこなし、未来へと繋ぐためには、テクノロジーの活用はもちろんのこと、「人」の価値を最大限に引き出し、地域と共に歩むという、ホテルの根源的な使命を再認識することが、最も重要な経営戦略となるはずです。
まとめ
2025年のホテル業界は、その成長と変革の裏側で、従業員の高齢化、深刻な人手不足、そして事業承継の困難という、根深い構造的課題に直面しています。長年にわたり高校球児たちの「第二の家」として愛されてきた甲子園ホテル夕立荘の閉館は、この現実を象徴する出来事であり、テクノロジーだけでは解決しきれない「人」と「地域」にまつわる運営の課題を私たちに突きつけました。
本稿では、この事例を起点に、以下の主要な考察を展開しました。
- 老舗ホテルの「無形の価値」と「有形の限界」:夕立荘が提供してきた「おもてなし」は、長年の経験と情熱を持つ「人」によって生み出されるものであり、その「人」の高齢化が事業継続を困難にする現実。
- 高齢化と事業承継のホテル業界共通課題:熟練スタッフの労働力低下、ノウハウ継承の困難、後継者不足が、多くのホテルを廃業に追い込む要因となっていること。
- 地域コミュニティとの共生:ホテルが単なる宿泊施設を超え、地域文化の担い手やコミュニティのハブとして機能する重要性、そして閉館が地域に与える多大な影響。
- 「人」の価値の再認識と継承戦略:熟練スタッフの持つ「おもてなしの心」と「現場の知恵」を、メンターシップ制度、知識の体系化、多世代共存型の職場環境構築、多様なキャリアパスを通じて次世代に継承することの重要性。
- 持続可能な運営への多角的なアプローチ:M&Aやソフトブランド化、地域連携といった事業承継モデルの多様化、多様な人材活用やリスキリング、エンプロイヤー・ブランディング強化による人材戦略の再構築、地域資源と連携した体験価値の再定義、そして戦略的な施設リノベーションの有効性。
- 伝統と革新のバランス:テクノロジーは「人」を支えるツールであり、ホテルの「物語」を再構築する力を持ち、最終的には経営者の「決断力」と「ビジョン」が未来を拓く鍵となること。
ホテル業界の未来は、単に最新テクノロジーを導入することだけでは描けません。むしろ、ホテルの核となる「人」への投資、地域社会との深い連携、そして長年培われてきた伝統と文化を、現代のニーズに合わせて柔軟に「革新」していく勇気が求められます。
甲子園ホテル夕立荘の物語は、一つの終わりを告げましたが、その決断の背景にある課題は、他の多くのホテルにとって、自らの運営を見つめ直し、持続可能な未来を創造するための貴重な教訓となるはずです。ホテルが提供する本質的な価値とは何か、それをいかに未来へと繋いでいくのか。この問いに真摯に向き合うことこそが、2025年以降のホテル業界に求められる最も重要な視点であると、私たちは考えます。

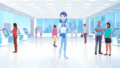
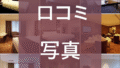
コメント