はじめに
2025年、日本のホテル業界は史上最高の活況を呈している一方で、深刻な構造的課題に直面している。訪日外国人観光客数が1月に過去最高の378万人を記録し、大阪・関西万博の開催を控えて需要が急拡大する中、新規ホテル供給が大幅に減少するという前代未聞の事態が発生している。建設費の高騰と労働力不足が重なり、ホテル業界全体が供給不足という新たな課題に直面している現状を詳しく解説する。
記録的なインバウンド需要の急拡大
2025年1月、訪日客数が過去最高を更新
日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2025年1月の訪日外客数は378万1,200人となり、前年同月比40.6%増という驚異的な伸びを記録した。これは2024年12月の348万9,800人を大きく上回り、単月として初めて370万人を突破した過去最高の記録となった。
特に注目すべきは、韓国(96万7,100人)、中国(98万300人)、台湾(59万3,400人)といった主要市場からの訪日客が軒並み増加し、韓国、台湾、オーストラリアでは単月過去最高を更新している点である。中国からの訪日客に至っては前年同月比135.6%増という大幅な伸びを示している。
万博効果でさらなる需要増加が確実
2025年4月13日から10月13日にかけて開催される大阪・関西万博では、期間中の来場者数が2,820万人と予想されており、そのうち約350万人(12%)が海外からの来場者と見込まれている。この万博効果により、関西圏を中心とした宿泊需要のさらなる増加が確実視されている。
実際に、大阪府内の宿泊施設における万博開催期間中の予約数は、前年同期比で既に倍を超える状況となっており、需要の旺盛さを物語っている。
建設費高騰が新規供給を直撃
2年間で建設費が41%上昇
一方で、ホテル建設費の高騰が深刻な問題となっている。国土交通省の建築着工統計によると、全国のホテル建築費の坪単価は2022年の138.3万円から2024年には195.0万円へと、わずか2年間で41.1%という急激な上昇を記録した。
構造別で見ると、木造の建築費は2022年の73.3万円から2024年には123.1万円へと68.4%上昇し、鉄筋鉄骨コンクリート造では182.2万円から324.4万円へと78.1%もの大幅な上昇を示している。これにより、従来は比較的安価だった木造建築も、鉄骨造の建築費(164.7万円)に近づくレベルまで高騰している。
建設費高騰の背景
建設費高騰の主な要因として、以下が挙げられる:
- 建築資材価格の上昇:鉄鋼、木材、コンクリートなどの基礎資材の価格が大幅に上昇
- 人件費の高騰:建設業界の深刻な人手不足により、施工人件費が急上昇
- エネルギーコストの増大:電力・燃料費の高騰が建設プロセス全体に影響
- 規制強化:建築基準の厳格化により、追加的なコストが発生
地域別の格差も拡大
都道府県別の建設費を見ると、香川県(339.2万円/坪)、兵庫県(277.8万円/坪)、北海道(246.6万円/坪)といった地域では特に高い水準となっている一方、石川県(52.5万円/坪)、三重県(59.9万円/坪)など、比較的低い水準を維持している地域もあり、地域間格差が拡大している。
新規ホテル供給の大幅減少
2025年以降の開業予定数が激減
建設費高騰の直接的な影響として、2025年以降の新規ホテル開業予定数が大幅に減少している。特に東京、大阪、京都といった主要観光都市では、ホテル供給が大幅に制限される状況となっている。
サヴィルズ・ジャパンの調査によると、コロナ禍によるプロジェクトの中止に加え、建設費の高騰と労働力不足が重なり、新規ホテル供給は大幅に抑制される見通しとなっている。これは、過去数年間にわたって続いてきたホテル開業ラッシュが完全に終息したことを意味する。
プロジェクトの中止・延期が相次ぐ
建設費の高騰により、計画段階にあったホテルプロジェクトの中止や延期が相次いでいる。特に中規模のホテル事業者にとって、当初の事業計画から大幅にコストが増大したプロジェクトを継続することは困難となっており、投資回収の見通しが立たないケースが多発している。
人手不足が拍車をかける供給制約
正規・非正規ともに50%超の不足率
帝国データバンクの調査では、旅館・ホテル業界の人手不足割合が2025年1月時点で正規・非正規社員ともに50%を超えた。これは全業種平均を大幅に上回る深刻な水準である。
宿泊現場では、フロントスタッフ、調理スタッフ、清掃スタッフなどの確保が間に合わず、十分な需要があるにもかかわらず客室稼働率を制限せざるを得ない状況が生じている。これは、供給能力があっても実際のサービス提供が困難になるという、新たな形の供給制約を生み出している。
建設業界の人手不足も深刻化
ホテル運営だけでなく、建設業界においても深刻な人手不足が新規供給を制約している。熟練した建設作業員の不足により、工事期間の長期化やコストの増大が避けられない状況となっている。
既存ホテルへの影響と機会
客室料金の大幅上昇
供給制約と旺盛な需要により、既存ホテルの客室料金は大幅に上昇している。大阪のアパホテル全体の平均価格は、2024年4月の1万円から2025年4月には1万4,500円へと約1.5倍に上昇し、その上昇率は東京を上回る水準となっている。
高級ホテルでは更に顕著な料金上昇が見られ、万博期間中の大阪では一流ホテルのスイートルームが1泊130万円を超えるケースも出現している。
既存ホテルの投資価値が向上
新規供給が制限される中、既存ホテルの資産価値は大幅に向上している。2024年の国内ホテル投資額は速報値で1.1兆円に達し、年間不動産取引総額の20%を占めるという過去最高の水準を記録した。
供給制約により、既存ホテルの競争優位性が高まり、ADR(平均客室料金)とRevPAR(客室あたり売上高)の持続的な上昇が期待されている。
ホテル運営への戦略的影響
収益管理の重要性が増大
供給制約により、ホテル運営においては収益管理(レベニューマネジメント)の重要性がこれまで以上に高まっている。限られた客室供給を最大限有効活用するため、価格設定の最適化や需要予測の精度向上が競争優位性を左右する重要な要素となっている。
運営効率化への投資が急務
人手不足に対応するため、ホテル運営の効率化投資が急務となっている。非接触型チェックイン・チェックアウトシステム、AIを活用した顧客対応、清掃ロボットの導入など、省人化技術への投資が収益性確保の鍵となっている。
エリア戦略の見直し
新規供給が制限される中、既存ホテルにとっては立地の重要性がより一層高まっている。主要観光エリアや交通アクセスの良い立地にあるホテルは、競争優位性を維持・拡大する絶好の機会を得ている。
今後の展望と課題
供給不足の長期化は避けられない
建設費高騰と人手不足という構造的要因により、ホテルの供給不足は今後数年間にわたって継続することが予想される。新規供給の回復には、これらの根本的な課題の解決が必要であり、短期的な改善は困難な状況である。
地方市場への分散効果
一方で、主要都市での供給不足により、地方市場への需要分散効果も期待されている。再訪日観光客の増加により、従来の観光地から地方への観光需要の拡大が進んでおり、地方のホテル市場にとっては新たな成長機会となっている。
2025年度市場は引き続き拡大
帝国データバンクの予測によると、2025年度の旅館・ホテル市場は引き続き拡大が期待される。2024年度の市場規模は5.5兆円と過去最高を記録する見込みであり、供給制約にもかかわらず市場全体の成長は継続するとみられている。
まとめ
2025年のホテル業界は、記録的な需要増加と深刻な供給制約という相反する状況に直面している。建設費の高騰と人手不足により新規供給が大幅に減少する一方、インバウンド需要の急拡大と万博効果により需要は史上最高レベルに達している。
この供給不足は既存ホテルにとって収益向上の大きな機会となっているが、同時に運営効率化とサービス品質の維持という新たな課題も生み出している。ホテル業界で働く DX担当者にとって、この構造的変化に対応するための戦略的な取り組みが、今後の競争優位性を決定する重要な要素となるだろう。
業界全体としては、テクノロジーの活用による省人化と効率化の推進、収益管理の高度化、そして持続可能な成長モデルの確立が、この新たな事業環境における成功の鍵となると考えられる。


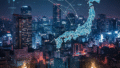
コメント