はじめに:宿泊売上だけではない、新たな収益の柱
インバウンド観光の本格的な回復や国内旅行の活発化を受け、多くのホテルで客室稼働率(OCC)や平均客単価(ADR)が改善傾向にあります。宿泊部門の売上が回復することは喜ばしい一方、これからのホテル経営では、宿泊以外の収益源をいかにして確立・拡大していくかが、持続的な成長のための重要な鍵となります。
先日、「訪日ラボ」に掲載された山陰地方のインバウンド人気ホテルに関するニュースでは、ランキングと共に「セルフレジ導入で売上1.2倍&業務効率化を両立」という興味深い記述がありました。これは、テクノロジーの活用が単なるコスト削減や省人化に留まらず、顧客の追加消費を促し、売上向上に直接貢献する可能性を示唆しています。
そこで本記事では、この「館内消費」を最大化するためのマーケティング戦略、特にテクノロジーを活用した「アップセル」と「クロスセル」に焦点を当て、その具体的な手法と成功のポイントについて深く掘り下げていきます。これは、顧客体験価値を高め、結果としてLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を向上させるための重要なアプローチです。
なぜ今、アップセルとクロスセルが重要なのか?
まず、基本的な用語の定義から確認しましょう。
- アップセル:顧客が当初検討していた商品やサービスよりも、上位の高価なものを提案し、購入してもらうこと。(例:予約されたスタンダードルームから、眺望の良いデラックスルームへのアップグレード提案)
- クロスセル:ある商品やサービスの購入を検討している顧客に対し、関連する別の商品やサービスを提案し、併せて購入してもらうこと。(例:宿泊予約客へのディナープランやスパトリートメントの提案)
これらの施策が今、ホテル業界で重要視される背景には、いくつかの理由があります。
1. LTV(顧客生涯価値)の向上
新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの数倍かかると言われています(1:5の法則)。一度の滞在で顧客が支払う金額(客単価)を高めることは、LTVを向上させる直接的な手段です。質の高いアップセルやクロスセルによって滞在の満足度が高まれば、顧客は「このホテルは自分のことをよく理解してくれる」「期待以上の体験ができた」と感じ、再訪意欲が高まります。つまり、アップセル/クロスセルは目先の売上増だけでなく、優良なリピーターを育成するための投資でもあるのです。
2. 顧客満足度の向上という「本質」
アップセルやクロスセルを単なる「売り込み」と捉えるのは誤りです。その本質は、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズを先回りして満たし、「より豊かで快適な滞在」を提供することにあります。例えば、記念日旅行で予約したカップルに対し、ホテル側から「お祝いにシャンパンをお部屋にご用意するプランはいかがですか?」と提案されれば、それは「押し売り」ではなく「気の利いたおもてなし」と受け取られるでしょう。顧客の予約情報や属性を元にパーソナライズされた提案を行うことで、アップセル/クロスセルは顧客満足度を劇的に向上させる強力なツールとなり得ます。
3. データ活用の時代
PMS(ホテル管理システム)やCRM(顧客関係管理システム)の進化により、ホテルは膨大な顧客データを保有しています。過去の宿泊履歴、食事の好み、利用したアクティビティ、記念日情報といったデータを分析することで、「どのような顧客に、どのタイミングで、何を提案すれば響くのか」という仮説を立て、実行することが可能になりました。勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいた科学的なアプローチが、アップセル/クロスセル戦略の成功確率を飛躍的に高めます。
テクノロジーを活用したアップセル/クロスセルの具体策
では、具体的にどのようなテクノロジーを活用して、効果的なアップセル/クロスセルを実践できるのでしょうか。顧客の滞在フェーズごとに見ていきましょう。
フェーズ1:予約完了後~チェックイン前(プレステイ)
顧客の期待感が最も高まっているこの時期は、アップセルの絶好の機会です。
活用ツール:予約確認メール、ホテル専用アプリ、事前チェックインシステム
- 部屋のアップグレード提案:予約確認メール内に、「追加料金で高層階のお部屋へ」「角部屋の広いお部屋へ」といったアップグレードの案内を魅力的な写真付きで掲載します。限定オファーであることを示唆すると、特別感が高まります。
- 追加パッケージの販売:アーリーチェックインやレイトチェックアウト、朝食の追加、記念日向けのケーキやフラワーアレンジメント、空港送迎サービスなどを、オプションとして分かりやすく提示します。事前決済まで完了できれば、当日の手間も省け、顧客・ホテル双方にメリットがあります。
フェーズ2:チェックイン時
対面または非対面での最初の接点です。スムーズな手続きと共に、最後のダメ押し提案が可能です。
活用ツール:スマートチェックイン端末、フロントのタブレット
- スマートチェックイン端末での提案:セルフチェックインのプロセス中に、端末の画面上で「本日に限り、デラックスルームに特別価格でアップグレードできます」といったオファーを表示します。対面での交渉が苦手な顧客にも、気軽に選択してもらえる可能性があります。
- フロントスタッフによる提案:PMSと連携したタブレットで顧客情報(リピーター、記念日など)を確認しながら、スタッフが「いつもご利用ありがとうございます。よろしければ、当館自慢のスイートルームからの眺めもお楽しみになりませんか?」とパーソナライズされたトークで提案します。
フェーズ3:滞在中(インステイ)
滞在中の体験価値を最大化し、館内消費を促す最も重要なフェーズです。
活用ツール:客室タブレット、ホテル専用アプリ、館内デジタルサイネージ
- 客室タブレット:これは最強のクロスセルツールと言えます。ルームサービスのメニューを美しい写真と共に表示し、タップ一つで注文できるようにするだけでなく、以下のような多様な提案が可能です。
・レストランやバーの空席情報をリアルタイムで表示し、予約を受け付ける。
・スパのトリートメントメニューを動画で紹介し、希望時間を予約させる。
・「本日15時~17時限定 ハッピーアワー」のような時間限定クーポンをプッシュ通知で配信する。
・地域の観光情報やアクティビティを紹介し、予約代行を受け付ける。
・客室で気に入ったアメニティやリネン、地域の特産品などを購入できるEC機能を持たせる。 - ホテル専用アプリ:顧客が自身のスマートフォンを通じて、客室タブレットと同様のサービスを受けられるようにします。館内のどこにいても、レストランの予約やプッシュ通知の確認が可能です。
- 館内デジタルサイネージ:エレベーターホールやレストラン前に設置し、ディナーのコースメニューや、バーテンダーおすすめのカクテルなどを映像で紹介。偶発的な利用意欲を喚起します。
成功のための3つのポイント
テクノロジーを導入するだけでは、アップセル/クロスセルは成功しません。以下の3つのポイントを意識することが不可欠です。
1. 徹底したパーソナライゼーション
全ての顧客に同じ提案をしても、響く確率は低いでしょう。予約情報(誰と、何のために、何泊するのか)や過去の利用履歴に基づき、提案を最適化することが重要です。ビジネス利用の顧客にファミリープランを提案しても意味がありません。逆に、小さなお子様連れの家族には、ベビーベッドの無料貸し出しや、子供向けメニューが豊富なレストランを案内することが喜ばれます。
2. 最適なタイミングでの提案
提案はタイミングが命です。チェックインで疲れている顧客に長々とオプションを説明するのは逆効果かもしれません。しかし、部屋で一息ついた頃に客室タブレットに届く「ウェルカムドリンクのハッピーアワー」の案内は、喜んで受け入れられる可能性があります。顧客の行動や心理状態を予測し、最適なタイミングで「そっと」背中を押すようなアプローチが求められます。
3. 「おもてなし」としてのコミュニケーション設計
最も重要なのは、全ての提案が「売り込み」ではなく「より良い滞在のための心遣い」として顧客に受け取られるようにコミュニケーションを設計することです。そのためには、デジタルツールと人的サービスの連携が欠かせません。例えば、客室タブレットでスパを予約した顧客に対し、廊下で会ったスタッフが「〇〇様、後ほどスパのご予約ありがとうございます。どうぞごゆっくりおくつろぎください」と一言添えるだけで、顧客体験は格段に向上します。テクノロジーはあくまで手段であり、おもてなしの心を伝えるための補助ツールであるという意識が大切です。
まとめ:LTVの最大化が未来のホテル経営を創る
テクノロジーを駆使したアップセルおよびクロスセル戦略は、単に客単価を上げるための小手先のテクニックではありません。それは、顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、データに基づいて最高の滞在体験を先回りして提案する、次世代の「おもてなし」の形です。
この戦略が成功すれば、売上向上はもちろんのこと、顧客満足度とロイヤリティが向上し、結果としてホテルのLTVは最大化されます。それは、口コミ評価の向上や優良リピーターの増加に繋がり、ホテルのブランド価値そのものを高める持続的な成長サイクルを生み出します。
宿泊予約を獲得するまでのマーケティング(集客)に注力するホテルは多いですが、これからは、顧客がホテルに滞在している時間(インステイ)の体験価値をいかにデザインし、収益に繋げていくかという視点が、ホテル間の競争を勝ち抜く上で決定的な差となるでしょう。まずは自社の顧客層を分析し、客室タブレットの導入や予約確認メールの工夫など、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。

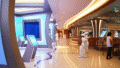

コメント