はじめに
2025年現在、アジアのホテル業界はパンデミックからの回復途上にありますが、その道のりは決して一様ではありません。一見すると観光客の増加や経済活動の再開により活況を呈しているように見えますが、その実態は地域や部門によって大きく異なる「不均一な回復」という複雑な様相を呈しています。特に、ホテル運営の重要な柱であるF&B(料飲)部門とMICE(会議、報奨旅行、コンベンション、展示会)部門は、それぞれ異なる課題に直面し、その回復の度合いがホテル全体の収益性や持続可能性に大きな影響を与えています。
本稿では、Hotel News Resourceが2025年10月22日に報じた記事を基に、アジアのホテル業界におけるこの「不均一な回復」の実態を深く掘り下げ、特にF&BとMICE部門が直面する具体的な課題と、それらに対する現場レベルでの対応策について考察します。
パンデミック後の「不均一な回復」の実態
Hotel News Resourceの記事が指摘するように、アジア太平洋地域のホテル業界は、パンデミックからの回復において顕著な地域差を見せています。東南アジア諸国の一部が力強い回復を遂げる一方で、香港、日本、中国本土といった主要市場では、いまだ回復の足取りが重い状況が続いています。
この不均一性は、各国の市場再開戦略、国内観光と国際観光のバランス、そして経済状況の違いに起因しています。例えば、早期に国境を開放し、積極的な観光誘致策を打ち出した国々は、国際観光客の流入をいち早く取り戻し、ホテル稼働率や収益を向上させました。しかし、厳格な入国規制を長く維持した地域や、国内消費の低迷が続く地域では、ホテルの回復が遅れ、特に国際的なビジネスイベントや大規模な会議に依存するMICE部門は大きな打撃を受けました。
現場のホテリエからは、「隣国はもうパンデミック前以上の活気を取り戻しているのに、うちはまだ団体客が戻らない」「海外からのMICE誘致が思うように進まず、宴会場が空いている日が多い」といった切実な声が聞かれます。この地域間のギャップは、ホテル経営者にとって、自社の市場特性を正確に把握し、地域に合わせた戦略を策定することの重要性を改めて浮き彫りにしています。
F&B部門が直面する「コスト圧力」という現実
アジアのホテル業界全体に共通する喫緊の課題の一つが、F&B部門を直撃する「コスト圧力」です。記事でも触れられているように、人件費の高騰と原材料費の上昇は、ホテルのF&B部門の利益率を大きく圧迫しています。
人件費高騰の背景と現場の苦悩
パンデミック期間中の人材流出は、多くのホテルで深刻な人材不足を招きました。需要が回復するにつれて、ホテルは再びスタッフを確保しようとしますが、労働市場の競争激化により、賃上げなしには優秀な人材を惹きつけ、定着させることが困難になっています。特にF&B部門は、調理師、サービススタッフ、バーテンダーなど専門性の高い人材を必要としますが、これらの職種での人材確保は一層困難です。
あるホテルの料飲部長は、「人が足りないから既存スタッフの負担が増え、離職に繋がる悪循環に陥っている。かといって賃上げすれば利益が圧迫される。質の高いサービスを維持するためには、どうしても人手が必要なのに、どうすれば良いのか」と頭を抱えます。また、若手ホテリエからは、「給与が上がらないのに仕事量だけが増える」という不満の声も聞かれ、モチベーションの低下や早期離職の一因となっています。これは、ホテル人材危機を乗り越える:総務人事が拓く「無償育成」と「定着戦略」でも指摘されている、ホテル業界全体の人材戦略の根深い課題と直結しています。
原材料費高騰と利益率への影響
世界的なインフレやサプライチェーンの混乱は、食材、飲料、消耗品といったF&B部門の原材料費を軒並み高騰させています。特に、高品質な食材を求める高級ホテルでは、この影響は甚大です。コスト増をそのまま価格に転嫁すれば顧客離れを招く恐れがあり、かといって価格を据え置けば利益が大幅に減少します。
現場のシェフは、「これまで使っていた食材の価格が20%も上がった。品質を落とすわけにはいかないし、メニュー価格を上げればお客様が来なくなる。日々、原価計算とメニュー開発に頭を悩ませている」と語ります。このような状況下で、ホテルのF&B部門は、食材の仕入れ先の見直し、廃棄ロスの削減、効率的なメニュー構成など、あらゆる面でコスト管理を徹底することが求められています。
CreditorWatchの2024年4月のビジネスリスク指数が示すように、ホスピタリティビジネスはB2B支払いの不履行が増加し、倒産リスクが高い状況にあります。これは、特に中小規模のホテルや独立系レストランにとって、資金繰りの悪化と経営の脆弱性を示唆しており、コスト圧力への対応が喫緊の課題であることを裏付けています。
MICE部門の回復戦略と課題
F&B部門と並び、ホテルの収益の大きな部分を占めるMICE部門も、パンデミックからの回復において独自の課題を抱えています。
国際MICEの回復の遅れと国内MICEへのシフト
国際的な会議や展示会は、国境を越える移動の制限や企業の出張費削減の影響を最も長く受けました。多くの国で入国規制が緩和された現在でも、大規模な国際MICEイベントの開催には、依然として慎重な姿勢が見られます。これは、参加者の移動コスト、安全への懸念、そしてハイブリッド形式(オンラインとオフラインの融合)への移行による物理的な参加意欲の低下などが複合的に影響しているためです。
この状況に対応するため、多くのホテルは国内MICE市場への注力を強化しています。しかし、国内MICEの需要喚起には、地域特性を活かしたユニークな体験の提供や、企業のニーズに合わせた柔軟なプランニングが不可欠です。例えば、地域の文化体験と組み合わせたチームビルディングプログラムや、サステナビリティに配慮したMICEパッケージなどが求められています。
ハイブリッドMICEへの対応と技術投資
パンデミックを機に普及したハイブリッドMICEは、参加者の利便性を高める一方で、ホテルにとっては新たな技術投資と運用負荷を意味します。高品質な映像・音響設備、安定したインターネット環境、そしてオンライン参加者とオフライン参加者の双方に満足度の高い体験を提供するノウハウが求められます。
あるホテルの宴会担当者は、「ハイブリッドMICEの準備は、従来のイベントの倍の手間がかかる。IT部門との連携も必須だし、トラブルが発生すれば即座に対応しなければならない。しかし、これを疎かにすれば、現代のMICE需要には応えられない」と語ります。この技術投資は、初期費用だけでなく、運用のための専門知識を持つ人材の育成や外部パートナーとの連携も必要とし、ホテルの経営資源を圧迫する要因にもなり得ます。
地域差がもたらす戦略の多様性
アジアにおける「不均一な回復」は、各地域のホテル経営者に異なる戦略を要求しています。
東南アジアの成功要因
タイ、ベトナム、インドネシアといった東南アジア諸国は、国際観光客の早期回復と国内市場の活性化により、比較的堅調な回復を見せています。これらの国々は、政府主導の観光誘致策に加え、ビーチリゾートや文化体験といった独自の魅力を積極的にアピールし、多様な旅行者のニーズに応えてきました。また、比較的低い物価水準も、旅行者にとっての魅力となっています。
現地のホテリエは、「パンデミック中も国内旅行の需要は一定数あり、国際観光客が戻ってきてからは、さらに勢いが増した。特に、デジタルマーケティングを強化し、SNSを活用した情報発信が功を奏している」と語ります。この成功は、北海観光衰退の警鐘:ホテル業界が学ぶ「大胆な適応」と「未来戦略」で示唆されているように、市場の変化に迅速かつ大胆に適応することの重要性を物語っています。
香港・日本・中国本土が抱える固有の課題
一方で、香港、日本、中国本土は、それぞれ異なる理由で回復に課題を抱えています。
- 香港:政治的な不安定要素や厳格な規制が長期化した影響で、国際的なビジネスハブとしての魅力が一時的に低下しました。MICE需要の回復も遅れており、ホテルは国内需要の喚起や、よりパーソナルな体験提供にシフトする模索を続けています。
- 日本:インバウンド需要は急速に回復しているものの、地方都市や特定のセクターではまだ回復が遅れています。また、人手不足と人件費高騰は深刻で、F&B部門をはじめとする現場の負担は大きいままです。ホテルは、高付加価値な体験提供や、地域連携による新たな魅力創出に力を入れています。大手ホテルの「収益偏重」が招く危機:ブティックに学ぶ「真のホスピタリティ」再構築で述べられているように、単なる収益追求ではない、本質的なホスピタリティの再定義が求められています。
- 中国本土:国内経済の減速、不動産市場の低迷、そして地政学的な緊張が、消費者の旅行意欲や企業のMICE支出に影響を与えています。国内観光は回復しつつあるものの、国際観光の本格的な回復には時間がかかると見られており、ホテルは内需を掘り起こすための多様な戦略を模索しています。
これらの地域では、ホテル経営者は市場の変動に敏感に対応し、柔軟な価格戦略、ターゲット顧客の再定義、そして新たな収益源の開拓が不可欠です。
ホテル業界が取り組むべき「持続可能な回復」
アジアのホテル業界がこの「不均一な回復」を乗り越え、持続可能な成長を遂げるためには、以下のような多角的なアプローチが求められます。
1. 効率化とコスト管理の徹底
F&B部門のコスト圧力に対応するためには、単なる経費削減だけでなく、サプライチェーンの最適化、食品廃棄の削減、エネルギー効率の向上など、運営全体の効率化が不可欠です。例えば、AIを活用した需要予測により、食材の仕入れ量を最適化したり、エネルギー管理システムを導入して光熱費を削減したりする取り組みが有効です。
2. 人材戦略の再構築
人件費高騰と人材不足は、ホテル業界全体の喫緊の課題です。魅力的な労働環境の整備、公正な報酬体系、キャリアパスの明確化、そして継続的な研修プログラムの提供を通じて、従業員のエンゲージメントを高め、定着率を向上させる必要があります。特に、現場スタッフのスキルアップは、サービスの質を維持・向上させる上で不可欠です。ホテル人事の未来戦略:データ駆動型ワークフォースが築く「持続可能な人材基盤」で提唱されているように、データに基づいた人材育成戦略が重要になります。
3. F&B/MICEにおける付加価値の創出
単に食事や場所を提供するだけでなく、記憶に残る体験やパーソナルなサービスを提供することで、顧客ロイヤルティを高め、価格競争から脱却することが重要です。地元の食材を活かしたユニークなメニュー開発、テーマ性を持たせたイベントの企画、あるいは顧客の健康やウェルビーイングに配慮したF&Bプログラムの導入などが考えられます。MICEにおいては、単なる会場提供に留まらず、企画段階から顧客と密接に連携し、イベントの成功をサポートするコンサルティング機能の強化も求められます。
4. 地域コミュニティとの連携強化
地域の魅力をホテル体験に取り入れることで、観光客にとっての付加価値を高めるだけでなく、地域経済への貢献も実現できます。地元の生産者からの食材調達、地域の文化イベントとの連携、地元住民向けのサービス提供など、ホテルが地域社会の「ハブ」となるような取り組みは、ブランド価値向上にも繋がります。
まとめ
アジアのホテル業界は、パンデミックからの回復という大きな波の中で、地域や部門によって異なる「不均一な回復」という現実と向き合っています。特にF&B部門が直面するコスト圧力と、MICE部門の回復の遅れは、ホテル経営者にとって看過できない課題です。
この複雑な状況を乗り越えるためには、画一的な戦略ではなく、各市場の特性と課題を深く理解した上で、現場レベルでの具体的な対応が求められます。効率化とコスト管理の徹底、人材戦略の再構築、F&B/MICEにおける付加価値の創出、そして地域コミュニティとの連携強化は、ホテルが持続可能な成長を遂げるための重要な鍵となるでしょう。アジアのホテル業界は、この困難な局面を乗り越え、新たなホスピタリティの形を創造していくことが期待されます。
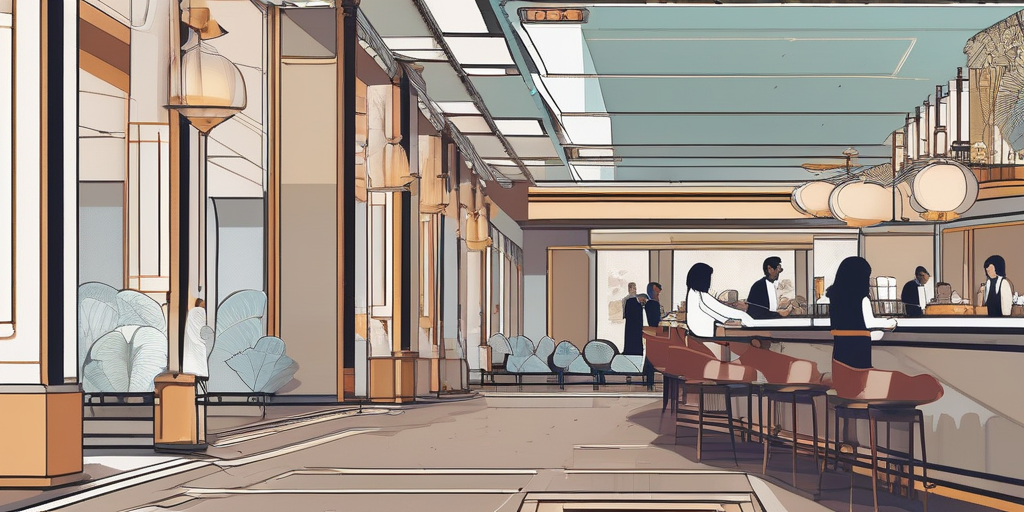
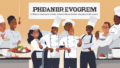

コメント