リーダー不在の危機。ホテル業界の未来を左右する後継者育成戦略
ホテル業界は今、華やかなイメージとは裏腹に、深刻なリーダー不足という課題に直面しています。インバウンド需要の急回復に沸く一方で、現場を牽引してきた経験豊富なベテラン層は次々とリタイアを迎え、将来を期待された若手・中堅層の離職にも歯止めがかかっていません。結果として、総支配人や部門長といった組織の舵取りを担うべきキーポジションの後継者が見つからず、場当たり的な人材配置に終始しているホテルも少なくないのではないでしょうか。
こうした状況を打開し、組織の持続的な成長を実現するために不可欠なのが、戦略的な「サクセッションプランニング(後継者育成計画)」です。これは、将来のリーダー候補を早期に見出し、計画的に育成することで、企業の未来を盤石にするための重要な経営戦略です。本記事では、ホテル業界の人事担当者様に向けて、サクセッションプランニングの重要性から具体的な実践ステップ、そして成功の鍵までを詳しく解説します。
なぜ今、ホテルでサクセッションプランニングが不可欠なのか?
「目の前の人手不足の対応で手一杯で、将来のリーダー育成まで手が回らない」。そうした声が聞こえてきそうですが、未来への投資を怠ることは、より深刻な事態を招きかねません。今こそサクセッションプランニングに取り組むべき理由は、大きく4つあります。
1. 深刻化する人材獲得競争
労働人口の減少は、ホテル業界にとって特に深刻な問題です。優秀な人材の獲得競争は業界内にとどまらず、他業界との間でも激化しています。特に、経営を担えるほどの経験とスキルを持つ人材を外部から採用することは、ますます困難かつ高コストになっています。自社内で次世代リーダーを計画的に育成することは、外部環境に左右されない安定した組織運営の生命線となります。
2. 独自の「おもてなし文化」の継承
ホテルの競争力の源泉は、そのホテルならではのサービス哲学や価値観、すなわち「文化」にあります。長年培われてきた独自の文化は、一朝一夕で身につくものではありません。自社の文化を深く理解し、体現できる内部人材をリーダーとして育成することこそが、ブランド価値を守り、高めていく上で最も確実な方法と言えるでしょう。
3. 従業員エンゲージメントとリテンションの向上
優秀な従業員ほど、自身のキャリアの将来像を意識しています。「このホテルで働き続ければ、将来は支配人や部門長を目指せる」という明確なキャリアパスが見えることは、仕事へのモチベーションを大きく向上させます。サクセッションプランニングは、従業員にとって単なる育成計画ではなく、自身の成長と未来への期待そのものです。結果として、エンゲージメントが高まり、優秀な人材のリテンション(人材定着)に繋がります。
4. 事業継続計画(BCP)の一環として
総支配人の急な退職や長期離脱は、ホテルの運営に計り知れない影響を与えます。サクセッションプランニングは、こうした不測の事態に備えるリスクマネジメントの観点からも極めて重要です。常に次世代のリーダー候補が準備されている状態にあれば、有事の際にも事業を停滞させることなく、スムーズな移行と運営の継続が可能になります。
ホテルにおけるサクセッションプランニング実践の5ステップ
では、具体的にどのようにサクセッションプランニングを進めていけばよいのでしょうか。ここでは、実践的な5つのステップをご紹介します。
ステップ1:キーポジションの特定
まず、自社の事業戦略上、将来にわたって不可欠となる「キーポジション」を明確に定義します。総支配人、副総支配人はもちろんのこと、宿泊部長、料飲部長、セールス&マーケティング部長、管理部門長など、そのポジションが空席になった場合に事業への影響が大きい役職をすべて洗い出します。その際、現在の役割だけでなく、5年後、10年後に求められるであろう役割の変化まで見据えることが重要です。
ステップ2:コンピテンシー・モデルの定義
次に、特定したキーポジションごとに、求められる能力やスキル、資質(コンピテンシー)を具体的に定義します。例えば、総支配人であれば、高度なリーダーシップや計数管理能力はもちろん、マーケティング戦略の立案能力、地域社会との関係構築能力、そして変化に対応する柔軟性などが挙げられます。このコンピテンシー・モデルは、候補者の評価や育成計画の土台となるため、経営層と現場の意見を交えながら慎重に策定する必要があります。このアプローチは、以前の記事「脱・属人化。コンピテンシー・モデルで築く、次世代ホテリエ育成術」で解説した考え方を応用したものです。
ステップ3:候補者の特定と評価(タレントレビュー)
定義したコンピテンシー・モデルに基づき、将来のリーダー候補者(タレントプール)を特定します。上司による推薦だけでなく、自己申告制度を取り入れたり、日々のパフォーマンス評価データを活用したりすることで、多角的な視点から候補者を発掘します。特定した候補者については、「9ボックスグリッド」のようなフレームワークを用いて評価・分類すると効果的です。これは、縦軸に「ポテンシャル(潜在能力)」、横軸に「パフォーマンス(現在の実績)」を置き、人材を9つのマスに分類する手法で、誰にどのような育成が必要かを可視化するのに役立ちます。
ステップ4:個別育成計画(IDP)の策定と実行
候補者一人ひとりの強みと伸ばすべき点に合わせて、個別育成計画(Individual Development Plan)を作成します。ここで重要なのが、「70:20:10の法則」です。人の成長は「70%が仕事上の経験」「20%が他者からの薫陶(コーチングやメンタリング)」「10%が研修」によってもたらされるという理論です。
経験(70%): 新規ホテルの開業プロジェクトリーダーへの任命、収益改善が求められる部門への異動、他部門を経験させるジョブローテーションなど、意図的に挑戦的な課題(ストレッチアサインメント)を与え、経験を通じて成長を促します。
他者からの学び(20%): 経営層や総支配人がメンターとなり、定期的に対話の機会を持つ。外部のプロフェッショナルコーチによるコーチングを導入する。
研修(10%): リーダーシップ研修や経営大学院の短期プログラムへの参加、財務・マーケティングなどの専門知識を学ぶ機会を提供する。
ステップ5:モニタリングとフィードバック
計画は実行して終わりではありません。定期的な1on1ミーティングを通じて、本人と上司、人事が三位一体となって育成計画の進捗を確認し、タイムリーなフィードバックを行います。また、年に一度は経営層も交えた「タレントレビュー会議」を開催し、候補者全体の成長度合いを評価し、翌年の計画を見直すサイクルを確立することが重要です。
サクセッションプランニングを形骸化させないための3つの要点
多くの企業でサクセッションプランニングが導入されながらも、いつの間にか形骸化してしまうケースが見られます。そうならないために、特に以下の3つの点が重要です。
ポイント1:経営トップの強力なコミットメント
サクセッションプランニングは、人事部門だけの仕事ではありません。総支配人や役員といった経営トップが「次世代の育成こそが最重要の経営課題である」という強い意志を持ち、自ら候補者との対話やメンタリングに時間を割く姿勢が不可欠です。トップのコミットメントが、組織全体の育成文化を醸成します。
ポイント2:公平性と透明性の担保
誰が、どのような基準で候補者として選ばれているのか。このプロセスが不透明だと、「結局は上司のお気に入り人事で決まる」といった不満や憶測を生み、従業員の士気を下げてしまいます。選定基準や評価プロセスを可能な限りオープンにし、従業員の納得感を高める努力が求められます。また、今回候補者から外れた従業員に対しても、その理由を丁寧に説明し、別のキャリアパスの可能性を示すといった配慮が組織への信頼を繋ぎ止めます。
ポイント3:テクノロジー(タレントマネジメントシステム)の活用
従業員一人ひとりのスキル、キャリア、評価、研修履歴といった人材データをExcelなどで属人的に管理するには限界があります。タレントマネジメントシステムを導入すれば、これらの情報を一元管理し、客観的なデータに基づいて候補者を発掘したり、最適な育成プランを立案したりすることが可能になります。かつてバックオフィス業務の効率化でRPAが活用されたように、人事領域においてもテクノロジーの活用は、戦略の精度と実行力を飛躍的に高める鍵となります。
まとめ
サクセッションプランニングは、単なる欠員補充のための仕組みではありません。それは、組織の未来図を描き、従業員の成長意欲という最も貴重な資源に火をつける、極めて戦略的な投資です。
「今のうちのホテルに、そんな大掛かりな制度を導入する余裕はない」と感じるかもしれません。しかし、最初から完璧な制度を目指す必要はありません。まずは、自社にとって最も重要なキーポジションを一つ特定し、その候補者となりうる従業員と「5年後、どうなっていたいか」を真剣に話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。
変化の激しい時代において、計画的な人材育成への取り組みこそが、貴社のホテルを未来へと導く揺るぎない礎となるはずです。

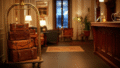

コメント