はじめに:都市観光ホテルの新たな戦い方
新型コロナウイルスのパンデミックが落ち着き、インバウンド観光客が急速に回復する中、日本のホテル業界、特に都市部のホテルは新たな競争の時代に突入しています。円安を追い風に訪日客数は増加の一途をたどり、ホテルの客室単価(ADR)も上昇傾向にありますが、その一方で顧客の期待値も高まっています。もはや、快適なベッドと清潔な客室、便利な立地というだけでは、数多あるホテルの中から選ばれる理由にはなり得ません。価格競争から一歩抜け出し、顧客に唯一無二の体験価値を提供できるかどうかが、今後のホテル経営の大きな分水嶺となるでしょう。
このような状況下で、ひときわ異彩を放ち、多くの旅行者から絶大な支持を集めているのが、星野リゾートが展開する都市観光ホテルブランド「OMO(おも)」です。OMOは「寝るだけでは終わらせない、旅のテンションを上げる都市観光ホテル」をコンセプトに掲げ、従来のビジネスホテルやシティホテルとは一線を画すアプローチで、都市観光のあり方そのものを再定義しようとしています。今回は、このOMOブランドの取り組みを深掘りし、これからのホテル運営が目指すべき方向性について考察します。
星野リゾート「OMO」とは何か?
「OMO」は、星野リゾートが都市観光に特化して展開するホテルブランドです。その最大の特徴は、宿泊を旅のゴールではなく、街を楽しむための拠点と位置づけている点にあります。ブランド名の「OMO」は、おもてなしの「おも」や、面白い(おもい)の「おも」など、様々な意味が込められていると言われています。
OMOブランドは、提供するサービスの幅に応じて「OMO1」「OMO3」「OMO5」「OMO7」といったナンバリングがされており、旅行者のスタイルや目的に合わせて選ぶことができます。
- OMO1(カプセルホテル):気軽な旅の拠点。
- OMO3(ベーシックホテル):朝食やラウンジはなく、シンプルに街を楽しむ拠点。
- OMO5(ブティックホテル):カフェがあり、デザイン性の高い空間で街歩きをサポート。
- OMO7(フルサービスホテル):レストランや特別なアクティビティを備え、都市観光をフルサポート。
このナンバリングにより、ブランドコンセプトを維持しつつも、多様なニーズに応える柔軟な展開を可能にしています。ターゲットは出張目的のビジネスパーソンではなく、その街の文化や食、歴史を深く体験したいと願う観光客です。OMOは、彼らの知的好奇心を満たし、「旅のテンションを上げる」ための様々な仕掛けを用意しています。
OMOの体験価値を支える2つの柱
では、OMOは具体的にどのようにして「旅のテンションを上げる」体験を創造しているのでしょうか。その中核をなすのが、「Go-KINJO」と「OMOベース」という2つのサービスです。
柱1:「Go-KINJO」- ホテルが街の案内人になる
「Go-KINJO」は、ホテルスタッフが「ご近所ガイド OMOレンジャー」となり、ホテル周辺の街の魅力を案内するサービスです。これは単なるコンシェルジュサービスとは異なり、より能動的で、エンターテイメント性に富んでいます。
ご近所マップ
OMOのロビーに入ると、まず目に飛び込んでくるのが巨大な「ご近所マップ」です。これは、スタッフが実際に歩いて見つけた、ガイドブックには載っていないようなディープな情報やおすすめスポットが満載の地図です。単なる情報の羅列ではなく、スタッフの手書きコメントやイラストが添えられ、見ているだけでワクワクするような工夫が凝らされています。ゲストはこのマップを見ながら旅の計画を立て、スタッフと会話することで、旅への期待感を高めていきます。
ご近所アクティビティ
OMOレンジャーが案内する街歩きツアーも、「Go-KINJO」の目玉です。例えば、「OMO5東京大塚」では都電荒川線沿線の魅力を探るツアー、「OMO3札幌すすきの」では地元民しか知らないようなお店で「はしご酒」を楽しむツアーなどが企画されています。これらのツアーは、単に場所を案内するだけでなく、その土地の歴史や文化、人々の暮らしに触れることができるように設計されています。OMOレンジャーのユニークな解説を聞きながら街を歩くことで、ゲストはただの観光客ではなく、その街の一員になったかのような感覚を味わうことができるのです。
この「Go-KINJO」サービスは、ホテルが地域社会と深く連携し、地域の魅力を「コンテンツ」として宿泊客に提供する画期的な取り組みと言えます。ホテルはもはや宿泊機能を提供する箱ではなく、地域への入り口、すなわち「ハブ」としての役割を担っているのです。
柱2:「OMOベース」- 旅の作戦基地となるパブリックスペース
もう一つの柱が、旅の拠点となるパブリックスペース「OMOベース」です。これは、フロント、ラウンジ、カフェ、ライブラリーといった機能を融合させた、OMOの心臓部とも言える空間です。
前述の「ご近所マップ」が設置されているのもこのOMOベースであり、ゲストはここで旅の情報を収集したり、OMOレンジャーに相談したり、あるいはゲスト同士で情報交換をしたりします。空間デザインも非常にユニークで、その土地の文化や産業をモチーフにしたインテリアが施されており、滞在するだけでその街の空気を感じることができます。
OMOベースは、チェックイン・チェックアウトのためだけに通過する場所ではありません。旅の始まりに計画を練り、街歩きの途中で一休みし、一日の終わりにはその日の出来事を振り返る。そんな風に、旅のあらゆる場面で活用される「作戦基地」として機能しています。この空間が、ゲストとスタッフ、そしてゲスト同士の偶発的なコミュニケーションを生み出し、旅をより豊かなものにしているのです。
ホテル運営への示唆:OMOから何を学ぶべきか
OMOの成功は、他のホテル、特に都市部で競争にさらされているホテルにとって多くの示唆を与えてくれます。
1. 「地域共創」という発想
OMOの強みは、ホテル単体でサービスを完結させるのではなく、積極的に地域を巻き込んでいる点にあります。近隣の飲食店や商店、職人、歴史家といった地域資源は、ホテルにとって最高の「パートナー」です。彼らと連携し、共に体験価値を創り上げていく「共創」の視点が不可欠です。これは、単に提携レストランの割引券を渡すといったレベルの話ではありません。地域のストーリーを掘り起こし、それをホテルのサービスとしてゲストにどう魅力的に伝えるかを考える、いわば「地域プロデューサー」としての役割がホテルには求められています。
2. スタッフの役割の再定義と価値向上
OMOレンジャーの存在は、ホテルスタッフの役割が大きく変化していることを示唆しています。定型的なフロント業務やオペレーションをこなすだけでなく、自らが「地域の専門家」「ゲストの旅の伴走者」となることが求められます。これは、スタッフにとって大きな挑戦であると同時に、自身の仕事に誇りと専門性を持つ絶好の機会でもあります。テクノロジーによる業務効率化(DX)が進む一方で、人間にしかできない付加価値の高いサービスとは何か。その一つの答えが、OMOレンジャーのような役割にあると言えるでしょう。スタッフの知的好奇心や探究心を刺激し、それをゲストへのサービスに還元する仕組みづくりは、従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)の両方を高める上で極めて重要です。
3. 「マイクロツーリズム」の視点を都市観光へ
コロナ禍で注目された「マイクロツーリズム(近距離旅行)」ですが、その本質は「身近な魅力の再発見」にあります。OMOのアプローチは、このマイクロツーリズムの視点を巧みに都市観光に応用したものです。遠方からの旅行者だけでなく、近隣に住む人々にとっても、OMOのアクティビティは自分たちの街を新たな視点で見つめ直すきっかけになります。全てのホテルは、自らの「ご近所」に眠る魅力を掘り起こし、それを独自のコンテンツとして発信するポテンシャルを秘めているのです。
まとめ:ホテルは「地域のショーケース」へ
星野リゾート「OMO」の事例は、これからの都市観光ホテルが目指すべき一つの理想像を示しています。それは、単に宿泊という機能を提供する「点」としての存在から、地域全体を巻き込み、旅の体験を豊かにする「面」の中心、すなわち「地域のショーケース」へと進化していく姿です。
もちろん、全てのホテルがOMOと全く同じことをする必要はありません。重要なのは、その思想を学び、自ホテルの立地や規模、ターゲット顧客に合わせて応用していくことです。自ホテルの「ご近所」には、どんな魅力が眠っているでしょうか。スタッフは、その魅力をゲストに伝える「案内人」になれるでしょうか。そして、ホテル全体で、ゲストの「旅のテンションを上げる」ための仕掛けを考えられているでしょうか。
テクノロジーを活用した効率化も重要ですが、最終的に顧客の心を掴むのは、そこでしか得られない特別な体験と、人の温かみが感じられるおもてなしです。OMOの成功は、その普遍的な真理を改めて私たちに教えてくれているのかもしれません。

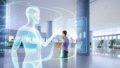

コメント