はじめに
ホテル業界において、サステナビリティ、特にSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みは、もはや単なる企業の社会的責任(CSR)活動の枠を超え、重要なビジネス戦略として位置づけられています。2025年を迎える現在、顧客の消費行動は大きく変化し、環境や社会に配慮した企業やサービスを選ぶ傾向が顕著です。特にホテルを選ぶ際、単なる快適さや立地だけでなく、そのホテルがどのような価値観を持ち、どのような社会貢献をしているかという点が、顧客の意思決定に影響を与えるようになっています。
本稿では、ホテルがSDGsを「おもてなし」の核として取り入れ、地域社会との連携を通じてどのようにブランド価値を高め、ビジネス上の優位性を確立しているのかを深く掘り下げます。具体的な事例を交えながら、その実践がもたらす多角的なメリットと、現場が直面する課題、そしてそれを乗り越えるための具体的なアプローチについて考察します。
SDGsを「おもてなし」の核とするホテル戦略
ホテル業界におけるSDGsの取り組みは多岐にわたりますが、中でも地域との連携を深め、独自の「おもてなし」を創出する戦略は、顧客に強い印象を残し、ブランドの差別化に大きく貢献します。札幌のホテルが実践している取り組みは、その好例と言えるでしょう。
TOKYO HEADLINE WEBの記事「札幌の歴史と歩む、2つの名ホテルのSDGsな「おもてなし」」は、札幌グランドホテルと札幌パークホテルの事例を紹介しています。これらのホテルは、札幌の中心地にありながら、敷地内でハーブや野菜を自ら栽培・収穫し、その食材をレストランで提供するというユニークな取り組みを行っています。シェフたちは、自社栽培の野菜について「野菜本来の味」「鮮度が素晴らしい」と絶賛しており、この取り組みが料理の品質向上に直結していることが伺えます。
参照元記事: https://news.yahoo.co.jp/articles/af9a0b930bbed12a3cdb8c9d1a05abf16605fc32
この事例が示すのは、SDGsが単なる環境規制への対応や社会貢献活動に留まらず、ホテルのコアとなるサービス、すなわち「食」を通じた「おもてなし」の質そのものを高める戦略として機能している点です。自社で食材を生産するという具体的な行動は、サプライチェーンの透明性を確保し、フードロスの削減にも貢献します。さらに、この取り組み自体がホテルのストーリーとなり、顧客との深いエンゲージメントを生み出す源泉となるのです。
「自ら栽培」がもたらす多角的な価値
ホテルが自ら食材を栽培する取り組みは、一見すると手間がかかり、非効率に見えるかもしれません。しかし、その実践は多角的な価値をホテルにもたらします。
品質と差別化
自社栽培の最大のメリットは、食材の品質と鮮度を最大限に保証できる点です。収穫から提供までの時間を極限まで短縮することで、野菜本来の風味や栄養価を損なうことなく顧客に届けることが可能になります。これは、外部から仕入れる食材では実現しにくい、ホテル独自の強みとなります。また、市場では手に入りにくい珍しい品種や、特定の調理法に適した野菜を栽培することで、他ホテルとの明確な差別化を図り、食体験の付加価値を高めることができます。
コストと効率性
サプライチェーンの短縮は、輸送コストの削減に直結します。外部業者に依存せず、自社で生産から消費までを一貫して行うことで、流通にかかる費用や時間を大幅に削減できます。また、必要な量を必要な時に収穫できるため、フードロスの削減にも貢献します。これは、環境負荷の低減だけでなく、食材廃棄にかかるコストの削減という経済的なメリットも生み出します。
ブランドストーリーと顧客エンゲージメント
自社栽培の取り組みは、ホテルにとって強力なブランドストーリーとなります。顧客は、単に美味しい料理を味わうだけでなく、「この食材がどこで、どのように育ったのか」という背景を知ることで、より深い感動と共感を覚えます。農園の見学ツアーや、収穫体験などのプログラムを提供することで、顧客はホテルの価値観に触れ、よりパーソナルな体験を得ることができます。このような体験は、単なる宿泊を超えた記憶に残る滞在となり、顧客ロイヤルティの向上に繋がります。
地域社会への貢献
地域に根ざしたホテルにとって、自社栽培は地域社会への貢献にも繋がります。敷地内の限られたスペースであっても、都市部での農業実践は、地域の緑化に貢献し、環境教育の場となる可能性も秘めています。また、将来的には地域農家との連携を深め、栽培ノウハウの共有や、地域特産品のPRなど、より広範な地域活性化に寄与することも考えられます。
従業員のモチベーション向上
農業経験のないスタッフが栽培に携わることは、新たなスキル習得の機会となり、業務への満足度向上に繋がります。土に触れ、作物が育つ過程を間近で見ることは、食に対する理解を深め、お客様への説明にも説得力を持たせます。また、宿泊部門、料飲部門、そして栽培に携わるスタッフが一体となってプロジェクトを進めることで、部署間の連携が強化され、チームビルディングにも貢献します。
現場の泥臭い課題と具体的な取り組み
自社栽培という取り組みは、多くのメリットをもたらす一方で、現場には特有の泥臭い課題が存在します。これらを認識し、具体的な対策を講じることが、持続可能な運営には不可欠です。
農業知識と労力の課題
ホテルスタッフの多くは、農業の専門知識を持っていません。土壌管理、病害虫対策、適切な水やり、収穫時期の見極めなど、学ぶべきことは多岐にわたります。また、栽培は季節や天候に左右されやすく、予測不能な事態に対応する柔軟性も求められます。
具体的な取り組みとしては、外部の農業専門家を招いた研修の実施や、近隣の農家との連携によるノウハウの共有が挙げられます。また、初期段階では栽培面積を限定し、経験を積みながら徐々に規模を拡大していくスモールスタートも有効です。水やりや温度管理など、一部の作業にIoTセンサーや自動灌水システムを導入することで、スタッフの負担を軽減し、効率化を図ることも可能です。
収穫量の不安定性とレストランでの活用
天候不順や病害虫の影響で、計画通りの収穫量が得られないこともあります。そうなると、レストランでのメニュー提供に影響が出たり、外部からの仕入れが必要になったりする可能性があります。
具体的な取り組みとしては、複数の品種を栽培してリスクを分散する、外部仕入れ先との連携を密にしてバックアップ体制を構築する、といった方法があります。また、収穫量の変動に合わせてメニューを柔軟に変更できる体制を整えることも重要です。例えば、「本日のホテル農園野菜」として、その日に収穫できたものを提供するなど、希少性を逆手に取ったマーケティング戦略も考えられます。
部門間の連携とコミュニケーション
栽培部門(または栽培担当者)、料飲部門(シェフ)、宿泊部門(フロントやコンシェルジュ)の間での密な連携は不可欠です。栽培状況や収穫見込み、メニューへの活用方法、そしてお客様への説明内容など、情報共有が滞ると、せっかくの取り組みが十分に活かされません。
具体的な取り組みとしては、定期的な合同ミーティングの開催や、情報共有のためのデジタルツールの導入が有効です。シェフが自ら農園に足を運び、栽培スタッフと直接対話することで、食材への理解を深め、より創造的なメニュー開発に繋がることもあります。宿泊部門のスタッフは、農園の取り組みを深く理解し、お客様にそのストーリーを魅力的に伝える役割を担います。
現場スタッフのリアルな声
実際に栽培に携わるスタッフからは、以下のような声が聞かれます。「最初は土いじりに抵抗がありましたが、お客様から『この野菜、本当に美味しいですね!』と言われると、大変だったことが報われます。自分の育てたものが直接お客様の喜びになるのは、他の業務ではなかなか味わえない経験です。」また、シェフからは「自社で育てた野菜は、まるで生きているようです。収穫したばかりの瑞々しさや力強い香りは、どんな高級食材にも劣りません。この素材をどう活かすか、料理人としての腕が試されますね。」といった、食材への深い愛情と、お客様への提供価値へのこだわりが感じられます。
このような現場の声を拾い上げ、スタッフのモチベーション維持に繋げることは、持続的なSDGs戦略において極めて重要です。
SDGs戦略がもたらすビジネス的メリット
SDGsを核とした「おもてなし」戦略は、ホテルの持続可能な成長に不可欠なビジネス的メリットをもたらします。
レピュテーションの向上とブランド力強化
環境や社会に配慮したホテルとして認知されることで、企業のレピュテーションが向上します。これは、メディア露出の機会を増やし、ブランドイメージを強化する効果があります。特に、環境意識の高いミレニアル世代やZ世代の顧客層にとって、SDGsへの取り組みはホテル選びの重要な要素となるため、新たな顧客層の獲得にも繋がります。
顧客ロイヤルティの構築
SDGsへの取り組みは、顧客との間に共通の価値観を生み出します。ホテルが掲げる理念に共感する顧客は、単なるサービス利用者ではなく、ホテルの「ファン」となり、リピート率の向上や口コミによる新規顧客の獲得に貢献します。ホテルが提供する体験が、単なる消費ではなく、社会貢献の一部であるという意識は、顧客の滞在価値を大きく高めます。
この点については、過去記事「CO2ゼロSTAYが創るホテルの新価値:環境貢献と顧客エンゲージメントの融合」でも触れられています。環境貢献が顧客エンゲージメントに直結するという考え方は、SDGs戦略の根幹をなすものです。
新たな収益源の創出
自社農園で栽培した野菜やハーブを、レストランでの提供だけでなく、ホテルショップで販売したり、体験プログラム(収穫体験、料理教室など)として提供したりすることで、新たな収益源を創出できます。これらの商品は、ホテルのストーリーを体現するものであり、高い付加価値を持つため、通常の物販とは異なる価格設定が可能です。
人材採用・定着への影響
SDGsへの積極的な取り組みは、優秀な人材の採用にも良い影響を与えます。社会貢献性の高い企業で働きたいと考える求職者にとって、ホテルのSDGs戦略は魅力的な要素となります。また、従業員自身がホテルの社会的な意義を理解し、その一員であることに誇りを感じることで、従業員エンゲージメントが高まり、離職率の低下にも繋がります。これは、ホテル業界が抱える人材不足という課題への有効な解決策の一つとなり得ます。
地域との共生を通じてユニークな価値を創出するホテル戦略については、「「たった一人」哲学が拓く未来:地域と共生するユニークホテルの持続戦略」でも詳細に分析されています。SDGsは、まさにこのような「たった一人」の哲学が、地域全体、ひいては地球規模の持続可能性へと繋がる具体的な行動を促すものです。
持続可能な「おもてなし」の未来
ホテル業界におけるSDGsは、単なる流行や義務ではなく、ホテルの存在意義そのものを問い直し、未来を切り拓くための重要な戦略です。自社栽培のような具体的な取り組みは、環境負荷の低減、地域社会への貢献、顧客体験の深化、従業員エンゲージメントの向上、そして最終的には収益性の向上という、多岐にわたるメリットをホテルにもたらします。
2025年以降も、顧客の環境意識や社会貢献への関心はさらに高まることが予想されます。このような時代において、ホテルが選ばれ続けるためには、単に豪華な設備やサービスを提供するだけでなく、「どのような価値観を持ち、どのような社会貢献をしているのか」というメッセージを明確に打ち出し、それを具体的な行動で示すことが不可欠です。SDGsを核とした「おもてなし」は、ホテルのブランド価値を最大化し、持続可能な成長を実現するための羅針盤となるでしょう。
まとめ
ホテル業界におけるSDGs戦略は、もはや選択肢ではなく、必須のビジネス戦略となっています。札幌のホテルの事例が示すように、自社栽培という一見地道な取り組みが、食材の品質向上、コスト削減、ブランドストーリーの構築、地域貢献、従業員モチベーション向上といった多角的な価値を生み出し、ホテルの競争優位性を確立しています。
現場では、農業知識の習得や収穫量の不安定性、部門間の連携といった泥臭い課題に直面しますが、これらを乗り越えるための具体的な取り組みと、スタッフの努力が、顧客に深い感動と共感をもたらします。SDGsを核とした「おもてなし」は、顧客、従業員、地域社会、そして地球環境、全てのステークホルダーにとって価値ある未来を創造する可能性を秘めており、ホテル業界の持続可能な成長を牽引する力となるでしょう。

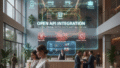
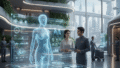
コメント